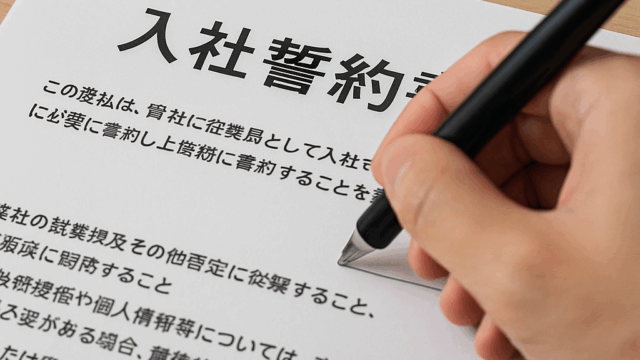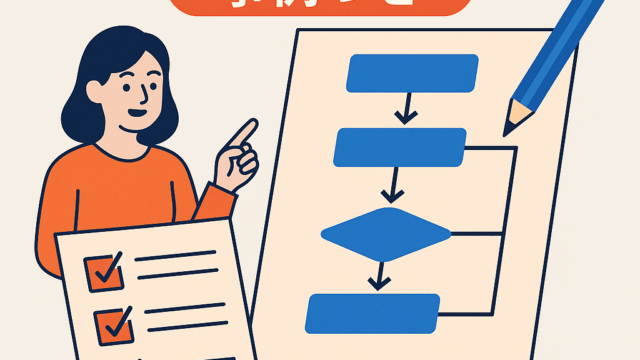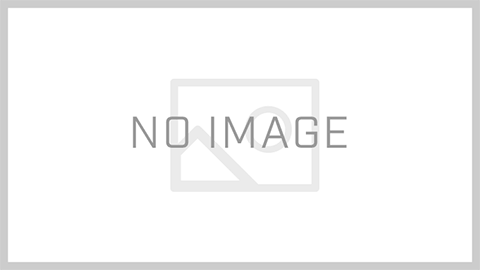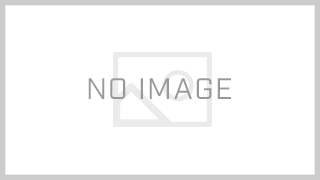こんにちは。
ひらおか社会保険労務士事務所の平岡です。
近年、採用市場は「売手市場」と言われ、特に新卒採用は年々難しさを増しています。
せっかく内定を出しても「入社直前の辞退」や「入社後すぐの退職」に直面する企業も少なくありません。
厚生労働省の統計によれば、新卒3年以内の離職率は高校卒で38.4%、大学卒で34.9%と高い水準です(令和3年3月卒業者)。
今回は、このような離職リスクに対して企業が取れる法的・実務的な対策について解説いたします。
【1. 内定は「労働契約」になる?】
内定とは、入社予定日を始期とする「解約権留保付労働契約」として法的に認められることがあります(大日本印刷事件・最判昭和54年7月20日)。
つまり、法的には内定段階でも一定の拘束力を持つ「契約」とみなされる可能性があります。
【2. 入社直前の内定辞退は防げる?】
民法627条・628条により、原則として労働契約は労働者の自由意思で解約が可能です。
「やむを得ない事由」がある場合には即時退職も認められ、法的に内定辞退そのものを防止することは困難です。
【3. 入社直後の退職にも“うまい手”はない】
入社後すぐに退職されても、内定辞退と同様に法律で直接防止する方法はありません。
そのため、企業は間接的な防止策を講じる必要があります。
【4. 企業が取れる実務的な防止策】
(1)有期労働契約の活用
試用期間に相当する数か月間を「有期契約」とすることで、期間中の即時退職を一定程度防げる可能性があります。
ただし、実態によっては「試用期間」と見なされるリスクもあるため、記載内容には注意が必要です。
(2)誓約書の取得
内定辞退や早期退職をしない旨の誓約書を取る例もありますが、労働基準法5条・民法90条に抵触するおそれがあり、法的効力は限定的です。
(3)損害賠償記載による抑止
内定通知書に「場合によっては損害賠償請求の可能性がある」旨を記載することで、心理的な抑止力になる可能性があります。
ただし、労働契約における「違約金の定め」や「賠償予定」は無効(労基法16条)となるため注意が必要です。
(4)身元保証書の活用
損害が発生した場合、保証人に対して請求する道もありますが、民法改正により極度額の設定や契約書の書面化が必須となっており、慎重な運用が必要です。
【5. 実は一番効果的なのは“ミスマッチを防ぐ工夫”】
法的な制限が多い中で、企業ができる最も有効な対策は、採用前の相互理解を深めることです。
- インターンシップの活用
- 社員との座談会
- 業務内容の見える化
こうした取り組みにより、入社後のギャップを減らすことが、早期退職の防止につながります。
【まとめとお問い合わせ】
「内定辞退」や「早期退職」は、企業にとって避けたい課題の一つです。
とはいえ、法律的に“縛る”ことは難しく、できることは「予防」と「リスク対応の仕組みづくり」です。
採用・退職に関するご相談、誓約書や内定通知書の見直しなど、実務面でのサポートをご希望の際は、どうぞお気軽にご相談ください。