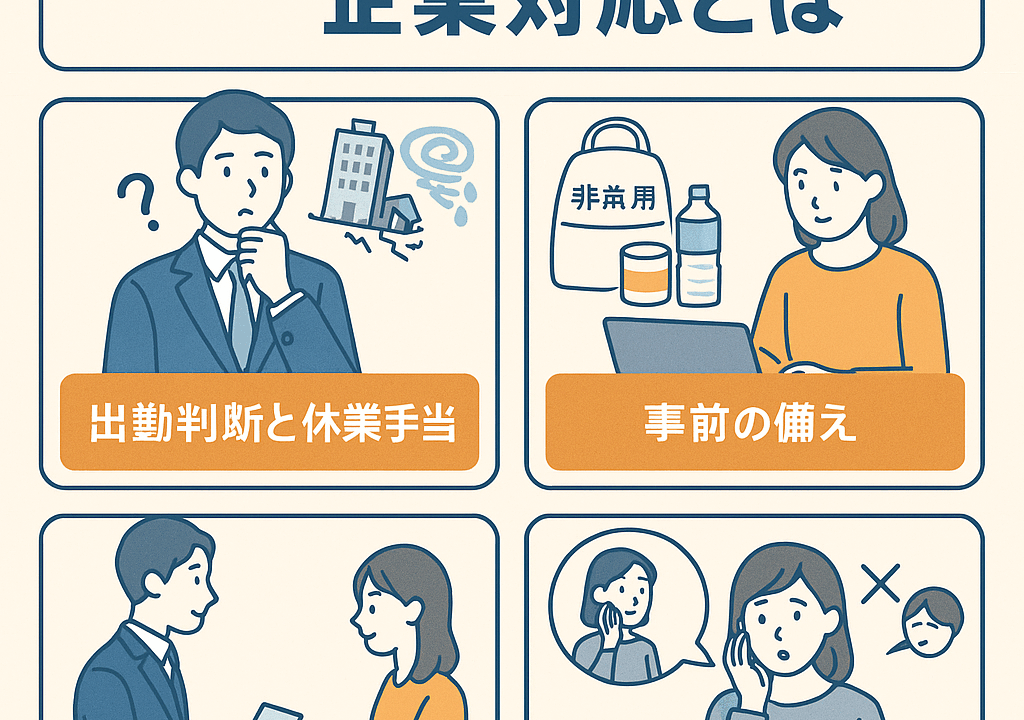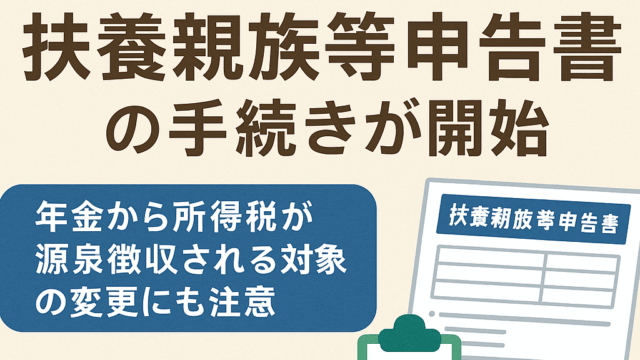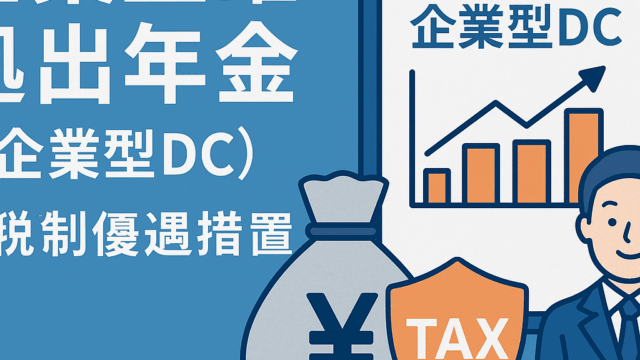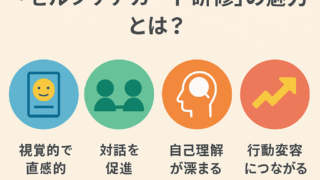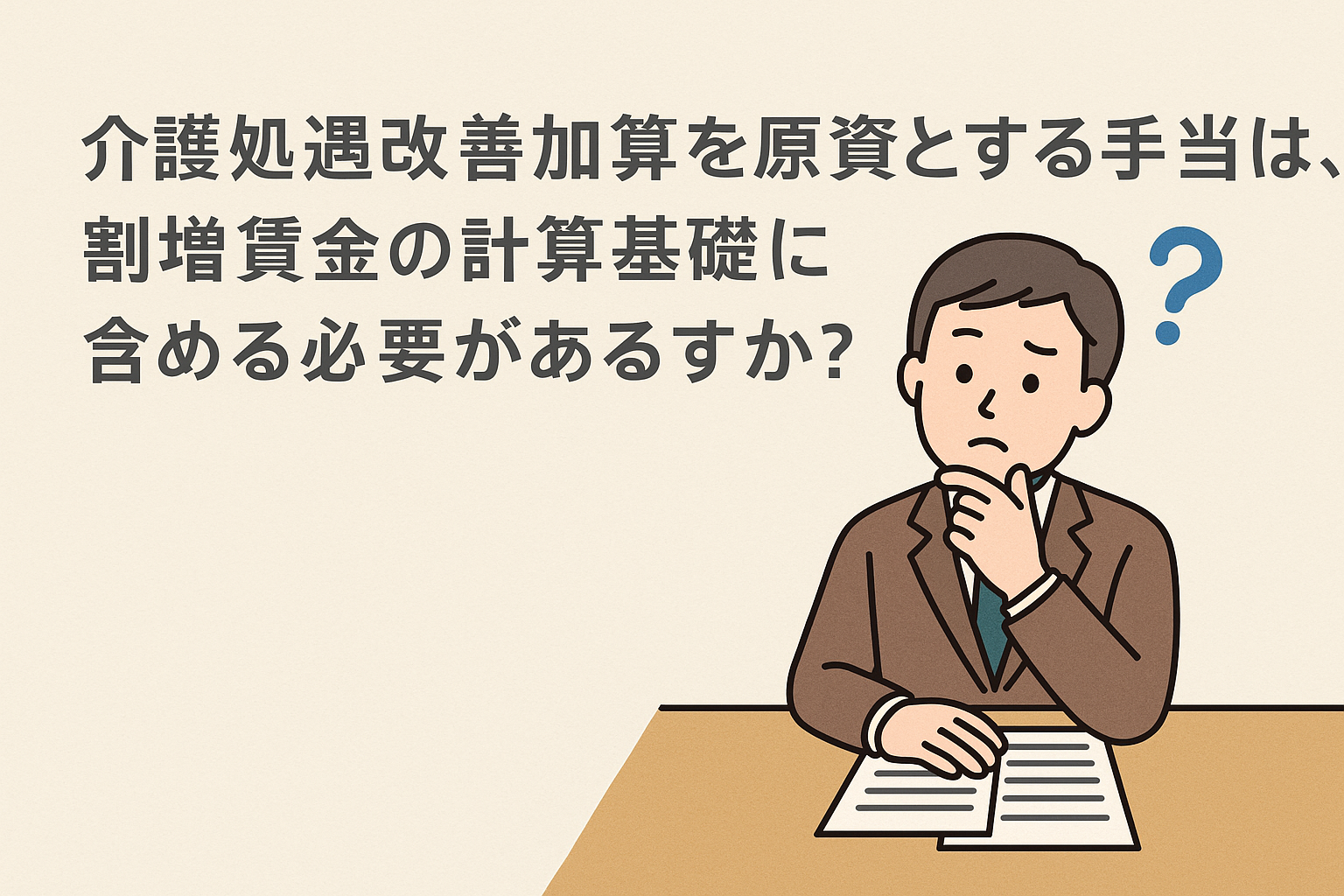近年、全国各地で地震や台風、大雨などの自然災害が相次いでいます。
企業には、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があり、この義務は自然災害時にも適用されます。
本記事では、自然災害が発生したときの企業対応と、事前に準備しておくべきポイントを解説します。
1. 出勤判断と休業手当
自然災害の発生は予測できないため、出勤可否の判断基準をあらかじめ決めておくことが重要です。
- 会社の判断で休業する場合
→ 「会社都合の休業」となり、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要です。
ただし、建物倒壊や設備破損など不可抗力のケースでは、支払い義務は発生しません。 - 従業員が自ら出勤を控えた場合
→ 休業手当の支払い義務はなく、欠勤扱いとなります。
この場合でも、有給休暇の取得推奨や特別休暇制度の整備を行うと安心です。
📌 事例
台風で鉄道が全面運休となり、多数の従業員が出勤困難に。
会社は「出勤できる人のみ出勤」と指示しましたが、出勤できなかった人は欠勤扱いに。ただし、有給休暇の取得を推奨し、従業員が安心して休めるよう配慮しました。
2. 給与の非常時払い
災害により従業員や家族が被災し、急な出費が必要になる場合、労働者が請求すれば給与の非常時払いに応じる必要があります。
これは「すでに働いた分の給与」を前倒しで支払う制度であり、いわゆる前借りではありません。
📌 事例
地震で自宅が損壊し、従業員が急きょ転居を余儀なくされたケース。
引っ越し費用の負担が大きく、給与の非常時払いを申請 → 会社はすでに働いた分を支払い、従業員の生活をサポートしました。
3. 事前に備えるべき自然災害対策
企業は「防災対策」と「事業継続」の両面から備えを進める必要があります。
- 防災対策例
避難経路の確保、安否確認ルール、防災訓練、非常用物資の備蓄、耐震補強 など - 事業継続対策例
優先業務の整理、テレワーク体制、仕入先や生産拠点の分散、業務引継ぎルールの整備 など
📌 事例
ある製造業では、工場が被災して操業できなくなった際に備え、代替生産できる協力工場と契約を締結。
実際の地震発生時、協力工場での生産を即時スタートでき、主要取引先への納期を守ることができました。
4. テレワーク環境での災害対応
テレワークは災害時の有効な手段ですが、停電や通信障害などのリスクがあります。
そのため、モバイルバッテリー貸与・ポケットWi-Fiの確保・クラウドバックアップなどの備えが有効です。
📌 事例
豪雨で自宅周辺が浸水し、在宅勤務中の従業員が停電で業務ストップ。
会社はモバイルバッテリーを事前に配布していたため、復旧までの間は最低限の業務を継続できました。
5. 労働時間・労災・保険料への影響
- 時間外労働:災害復旧対応などの場合、労基署の許可を得れば36協定の上限を超える労働も可能。
- 労災認定:自然災害による被災は原則労災にあたりませんが、作業環境や業務内容によって認定される場合があります。
- 社会保険料・労働保険料:災害で納付が困難な場合、申請により納付猶予を受けられる制度があります。
📌 事例
通勤途中に大雨で道路が冠水し、従業員が被災 → 原則として「通勤災害」と認定され、労災保険給付の対象となりました。
6. メンタルヘルスケアの重要性
災害による被災は従業員に大きなストレスを与えます。
相談窓口の設置や外部専門機関との連携など、心のケア体制を整えておくことも企業の大切な役割です。
📌 事例
地震で家族が被災した従業員に対し、会社が臨時で社内相談窓口を設置。
専門家との連携で、心理的なサポートを提供し、安心して業務に復帰できるよう支援しました。
まとめ
自然災害は「いつ、どこで」発生するかわかりません。
企業は、従業員の安全を守り、事業を継続・早期復旧させるために 平時からの準備が不可欠 です。
御社でもこの機会に、災害時の対応マニュアルや就業規則の整備を見直してみてはいかがでしょうか。
✅ 初回相談は無料です。災害時の労務対応や規程整備についてもお気軽にご相談ください。