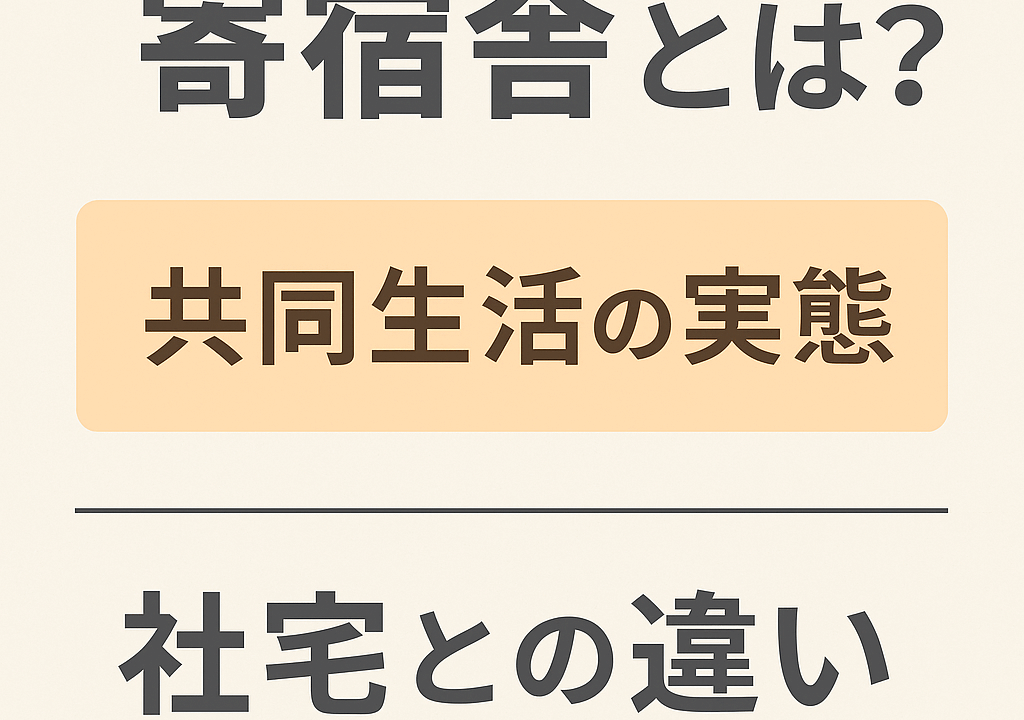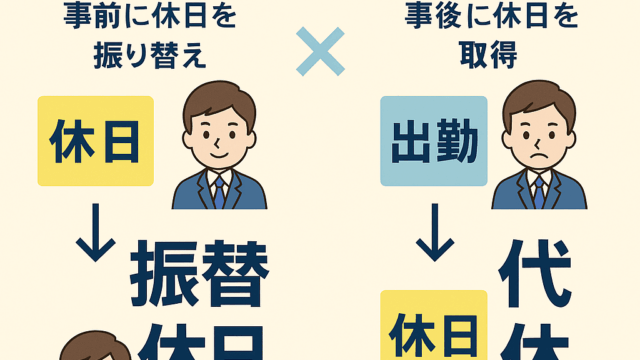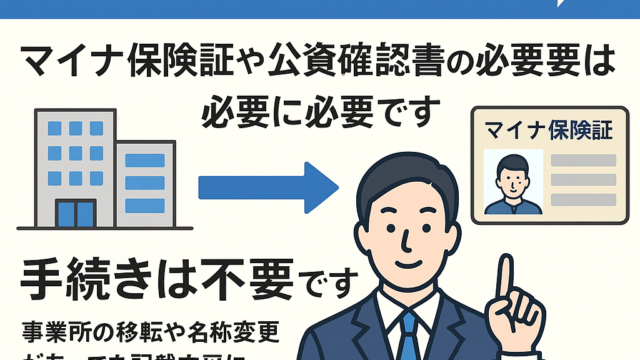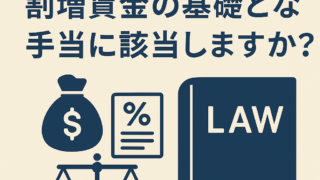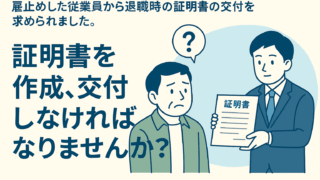労働基準法では、労働条件だけでなく、労働者の生活環境についても一定のルールが定められています。そのひとつが「寄宿舎」に関する規定です。
今回は、労働基準法における寄宿舎の定義と、社宅などとの違いをわかりやすく解説します。
寄宿舎の定義
労働基準法10章の適用を受ける「事業附属寄宿舎」は、通達(昭和23年基発508号)により、次の条件すべてを満たすものとされています。
- 常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えているもの
- 事業経営の必要上、その一部として設けられた施設であり、事業との関連性をもつもの
また、寄宿舎に該当するかどうかの判断は、以下の基準を総合的に考慮して行われます。
- 相当人数の労働者が宿泊しているか
- 施設が独立または区画された場所であるか
- 単なる共同設備(便所・炊事場などの共用)にとどまらず、起居・寝食などを一定の規律や制限のもと共同で行っているか
寄宿舎に含まれないもの
一方で、次のような施設は「寄宿舎」には含まれません。
- 社宅のように、それぞれの労働者が独立した生活を営む住居
- 住み込み労働者が少人数で事業主家族と生活を共にする場合
つまり、単なる「会社が用意した住居」と「規律ある共同生活の場」とでは、法律上の取り扱いが異なるのです。
事例でみる「寄宿舎」の判断
事例1:製造業の工場寮
ある工場では、従業員50名のうち20名が敷地内の寮に入居しています。
部屋は2人1室で、食堂・浴場・門限があり、生活のルールも定められています。
→ この場合、労働基準法上の「寄宿舎」に該当し、寄宿舎規則を作成・届出する必要があります。
事例2:社宅マンション
会社が賃貸マンションを借り上げ、従業員に貸与しています。
各部屋は完全に独立しており、生活ルールや共同生活はありません。
→ この場合は「社宅」と扱われ、寄宿舎には該当しません。
実務上のポイント
寄宿舎に該当する場合、寄宿舎規則の作成と労働基準監督署への届出が必要です。
これは就業規則と同様に法的義務があるため、実態を踏まえて正しく判断することが求められます。
📌 まとめ
- 寄宿舎とは「相当数の労働者が共同生活を営む事業附属の施設」
- 社宅や住み込みなど独立した生活は含まれない
- 寄宿舎に該当する場合は「寄宿舎規則」の届出が必要
✅ もし御社の施設が「寄宿舎にあたるのかどうか判断が難しい…」という場合は、専門家にご相談ください。
制度に基づいた適切な対応をとることで、労務リスクを未然に防ぐことができます。