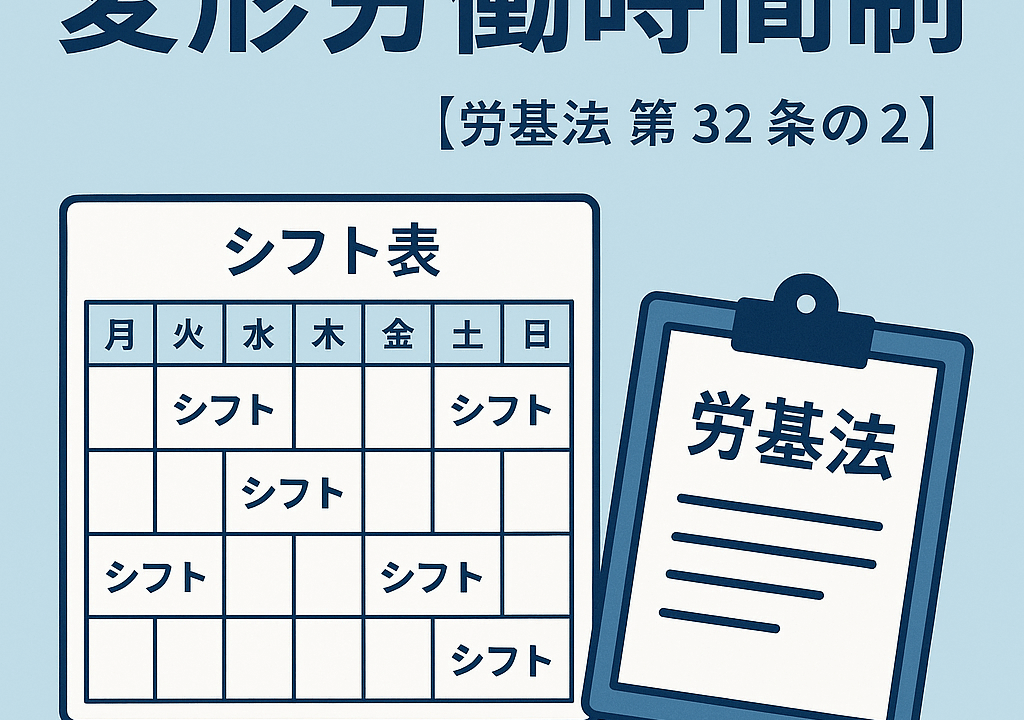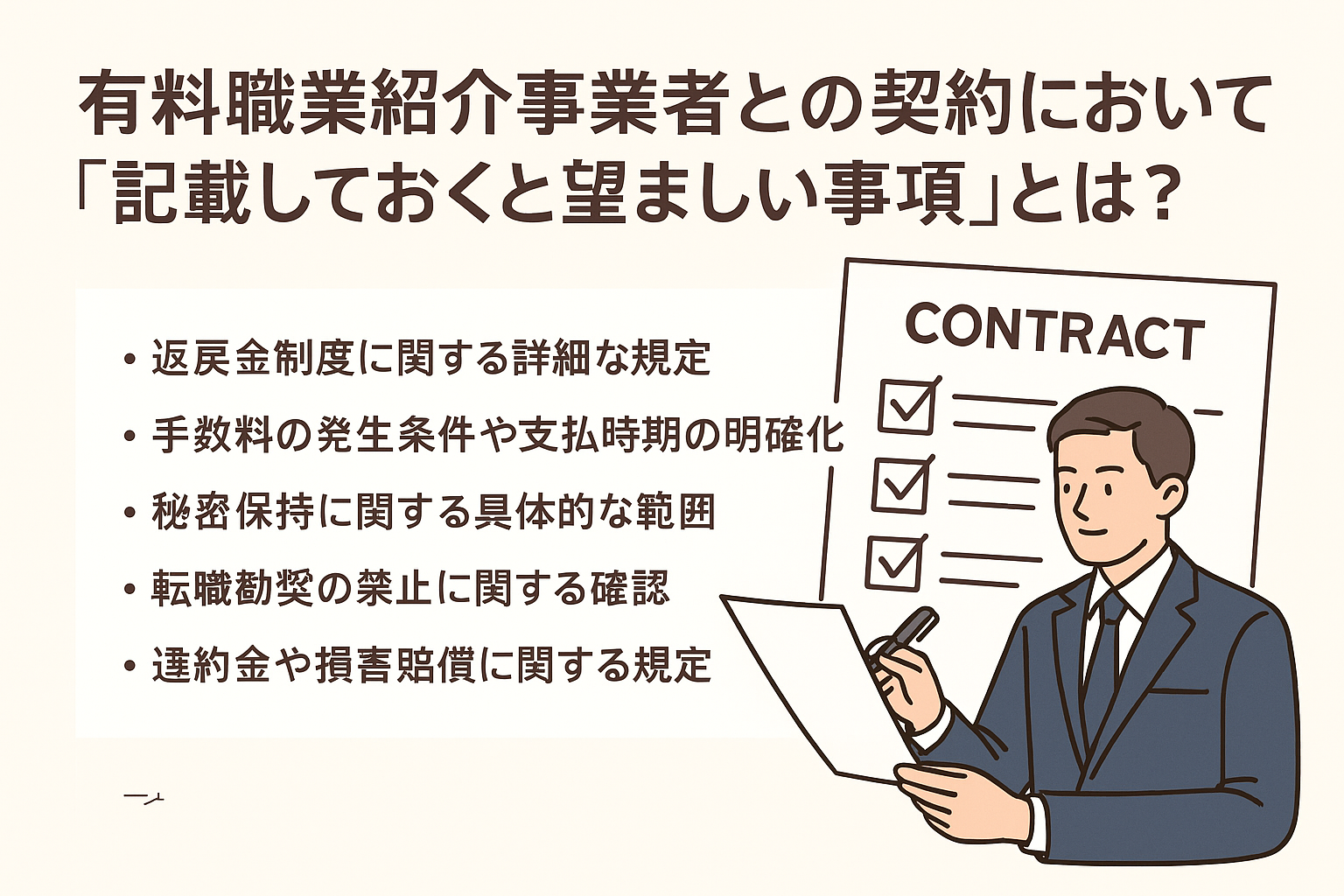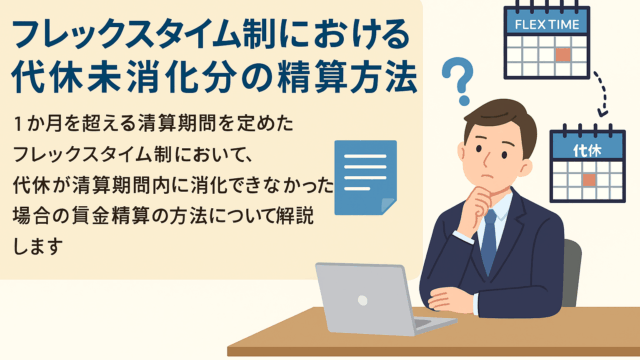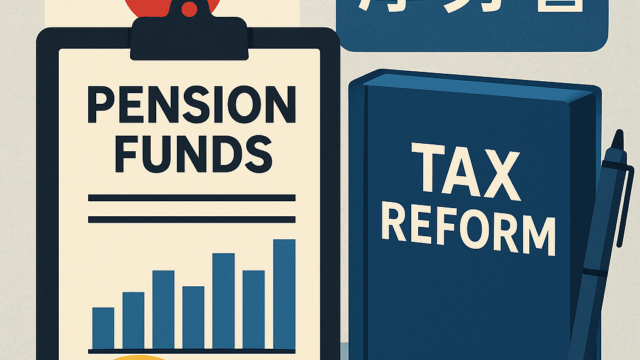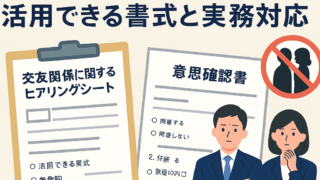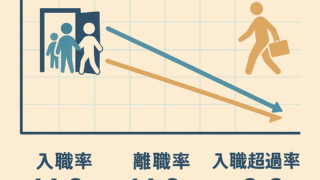企業の労務管理においてよく活用される制度の一つに「1か月単位の変形労働時間制」があります。繁忙期と閑散期で労働時間を柔軟に調整できる便利な仕組みですが、導入にあたっては注意すべき法律上の要件があります。
今回は、労働基準法 第32条の2および関連通達に基づき、「労働時間の特定」について解説します。
変形労働時間制の基本ルール
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、以下の点がポイントです。
- 就業規則等により、各日・各週の労働時間をあらかじめ具体的に定める必要がある
- 「平均すれば週40時間(旧法では週46時間)以内だからOK」という運用は不可
- 使用者が「業務の都合で自由にシフトを変更できる」ような制度は認められない
- 就業規則には労働時間の長さだけでなく、始業・終業の時刻を定める必要がある(労基法第89条)
つまり、単なる「平均調整」ではなく、事前にルールを明確化することが重要です。
実務でのよくある誤解(事例)
❌ 誤った運用例
ある小売業の会社が「1か月単位の変形労働時間制を導入」としながら、実際には店長の裁量でシフトを都度変更していました。結果として、労働時間の特定が事前にされていないため「制度として無効」とされ、未払い残業代の請求リスクが発生しました。
⭕ 正しい運用例
同じ小売業でも、就業規則に「変形期間を1か月とし、各日の所定労働時間と始終業時刻を別表に定める」と明記。従業員代表との協定を経て労基署に届出をしたケースでは、制度が適法に機能し、繁忙期の残業代コストを適正に抑えることができました。
根拠法令・参考情報
- 【条文】労働基準法 第32条の2(1か月単位の変形労働時間)
- 【通達】昭和63年1月1日 基発第1号
- 【関連】都道府県労働基準局長 基発第150号(労基法関係解釈例規)
まとめ
変形労働時間制は便利な制度ですが、「就業規則等で具体的に労働時間を特定する」ことが必須条件です。誤った導入をすると、制度が無効となり、かえって企業のリスクが大きくなってしまいます。
労務管理の仕組みを整えたい方は、専門家に一度ご相談ください。