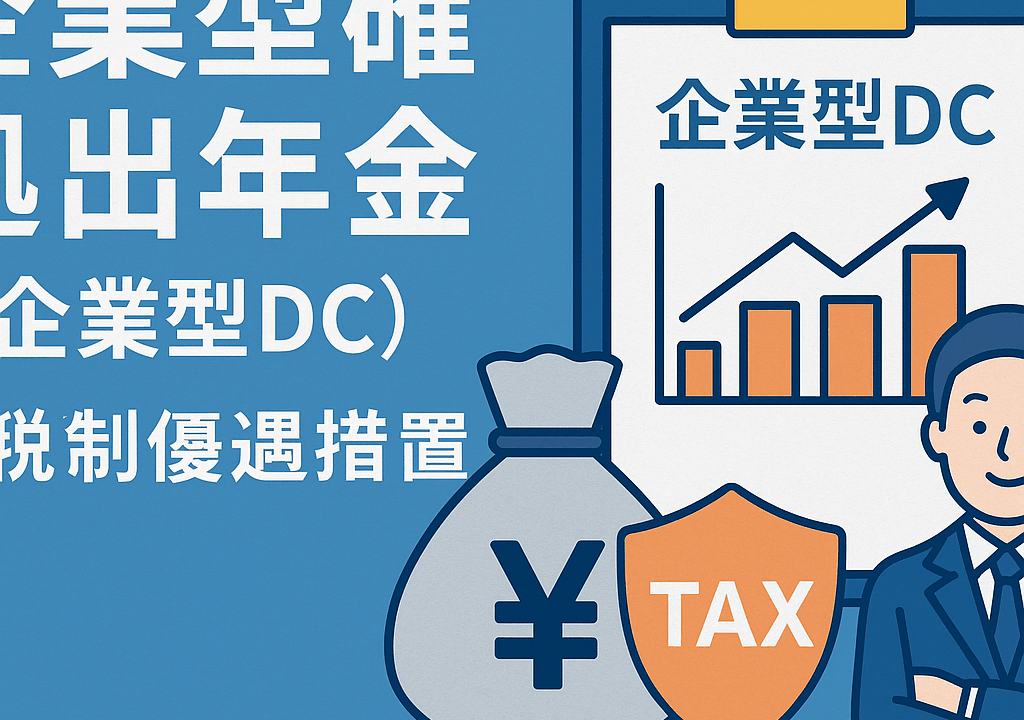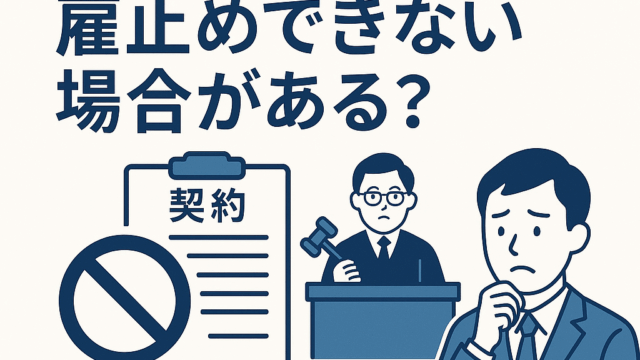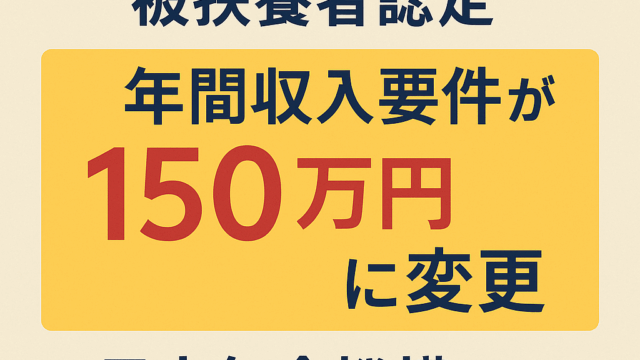2025/08/28 コラム
企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」)は、確定給付型年金(DB)に対して「拠出額は確定、給付額は未確定」 という特徴を持つ企業年金制度です。拠出した掛金を従業員自身が運用し、その成果に応じて将来の受給額が変動します。企業にとっては将来の年金債務を負わない点が大きな特徴であり、退職給付制度の選択肢として注目されています。
1.掛金と制度設計
(1)掛金の上限額
企業型DCの掛金は、確定拠出年金法に基づき上限が定められています。
- 他に企業年金がある場合:月額27,500円
- 他に企業年金がない場合:月額55,000円
この「他に企業年金がある」とは、確定給付企業年金や厚生年金基金などを指します。
制度設計にあたっては、役職や勤続年数に応じた掛金設定を行う企業が多いですが、法定上限を超える設定はできません。
(2)運用とスイッチング
加入者は、定期預金や投資信託等から商品を選び、自ら資産配分を決定します。
さらに、「スイッチング(預け替え)」により、既存の資産を別商品へ移すことも可能です。長期運用においては、このスイッチングを活用したリバランスが資産形成の鍵となります。
(3)受給開始年齢と制限
原則として60歳以降に受給が可能ですが、加入期間が短い場合は65歳や70歳に繰下げられるケースもあります(最低加入年数に応じて変動)。
受け取り方法は「一時金」または「年金形式」を選択でき、途中での引き出しは原則認められていません。
2.加入・運営の仕組み
企業型DCでは、制度運営にあたり 「運営管理機関」 を選定する必要があります。
運営管理機関は厚生労働大臣の登録を受けた金融機関(銀行・証券・保険会社等)で、以下の役割を担います。
- 加入者ごとの資産管理
- 運用商品の提示
- 情報提供・教育
企業は口座管理手数料を負担し、従業員は制度運用に直接の費用負担をしません。従業員にとっては、加入時に運用商品の選択を行うことが主な手続きとなります。
3.企業型DCにおける3つの税制優遇措置
(1)運用益の非課税
通常の金融商品の運用益には約20%の課税がありますが、企業型DCの運用益は非課税です。これは長期投資効果を最大化する要因となります。
(2)受給時の控除
- 一時金受取の場合:「退職所得控除」の適用
- 年金形式の場合:「公的年金等控除」の適用
これにより、同額の資産を受け取る場合でも税負担が大幅に軽減されます。
(3)マッチング拠出の全額所得控除
企業掛金に加えて、従業員が上乗せする「マッチング拠出」は全額が所得控除対象となり、所得税・住民税の軽減効果があります。
導入事例:製造業B社のケース
製造業のB社(従業員300名)は、従来の退職金制度を廃止し、企業型DCを導入しました。
- 管理職は月額30,000円、一般社員は20,000円を企業が拠出。
- 運営管理機関として証券会社を選定し、投資教育セミナーを実施。
- 従業員の3割がマッチング拠出を利用し、平均5,000円を追加拠出。
結果として、企業は退職給付債務を回避しつつ、従業員は非課税で効率的に老後資産を形成できる環境を整備。福利厚生制度としての魅力が高まり、人材採用にも効果が見られました。
まとめ
企業型DCは、企業の退職給付コストを平準化しつつ、従業員に大きな税制優遇をもたらす制度 です。
制度設計段階では「掛金水準の設定」「運営管理機関の選定」「投資教育の実施」が成功の鍵となります。
企業にとっては人材定着の手段、従業員にとっては老後資産形成の強力な手段として、今後さらに普及が見込まれます。
👉 企業年金制度の導入や労務管理のご相談は、専門家へお気軽にどうぞ。
初回相談無料・お問い合わせはこちら