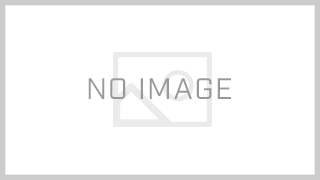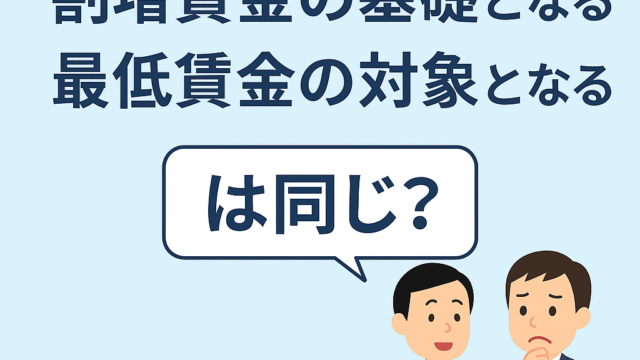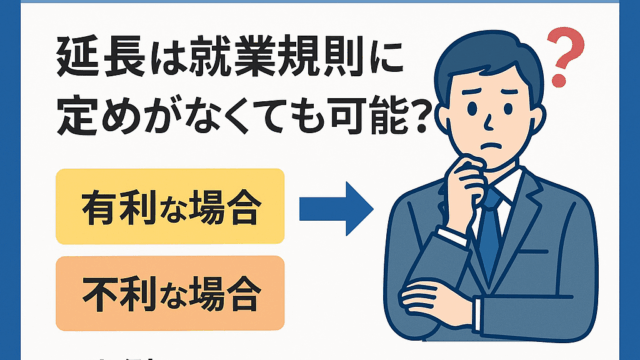こんにちは。
ひらおか社会保険労務士事務所の平岡です。
「従業員から“パワハラを受けた”と申告があり、どう対応してよいかわからない」
――これは、実際にご相談いただくことの多いケースです。
対応を誤ると、企業側が安全配慮義務違反を問われ、損害賠償を命じられることもあります。
今回は、パワハラ申告への“初動対応”で企業が注意すべきポイントと、実際にあった裁判例をもとに、リスク回避のヒントをご紹介します。
■ NG対応①:「本当にパワハラなのか?」と即断してしまう
申告の内容を確認する前に、「被害者側にも問題があるのでは?」「また大げさに言って…」といった態度をとるのは厳禁です。
実際、セクハラ申告を“虚偽”と決めつけて解雇した企業に慰謝料が命じられた裁判例(C社事件/大阪地裁)もあります。
申告を受けたときは、まず真摯に受け止め、冷静かつ丁寧に事実関係を確認していく姿勢が求められます。
■ NG対応②:被害者からの相談を“放置”してしまう
【さいたま市環境局事件(東京高裁)】では、パワハラの訴えを受けた上司が適切な対応をとらず、1,920万円の損害賠償命令が下されました。
被害申告を放置することは、「職場環境調整義務」の違反とみなされるリスクがあるのです。
最低でも、申告から20日以内に調査開始の通知を行うことが、法的リスクを回避するポイントです(公益通報者保護法との関係も含めて)。
■ 実務で重要なこと:加害者・被害者双方への対応バランス
パワハラ事案では、加害者に対してもヒアリングを行い、虚偽供述や反省態度の有無を見極めながら対応を進めます。
また、懲戒処分を行う際は、加害者のプライバシーにも配慮が必要です。
さらに、被害者への説明や必要に応じた配置転換など、丁寧なフォローと信頼回復措置が不可欠です。
■ まとめ:パワハラ対応は「備え」がすべて
パワハラ防止措置は、今や法的義務です。
しかし、制度や就業規則があっても、実際の対応が不十分であれば企業責任を問われかねません。
「何から整備すればいいかわからない」
「従業員からの申告に対応できる体制がない」
「懲戒処分をどう判断すればいいかわからない」
そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、以下のようなサポートが可能です:
✅ パワハラ初動対応のマニュアル作成
✅ 就業規則への調査協力義務の規定追加
✅ 被害者・加害者対応に関する社内研修
✅ 調査結果説明・懲戒判断の実務支援
▶︎ ご相談・お問い合わせはこちらから
早めの対応が、会社と従業員を守ります。
お気軽にご相談ください。