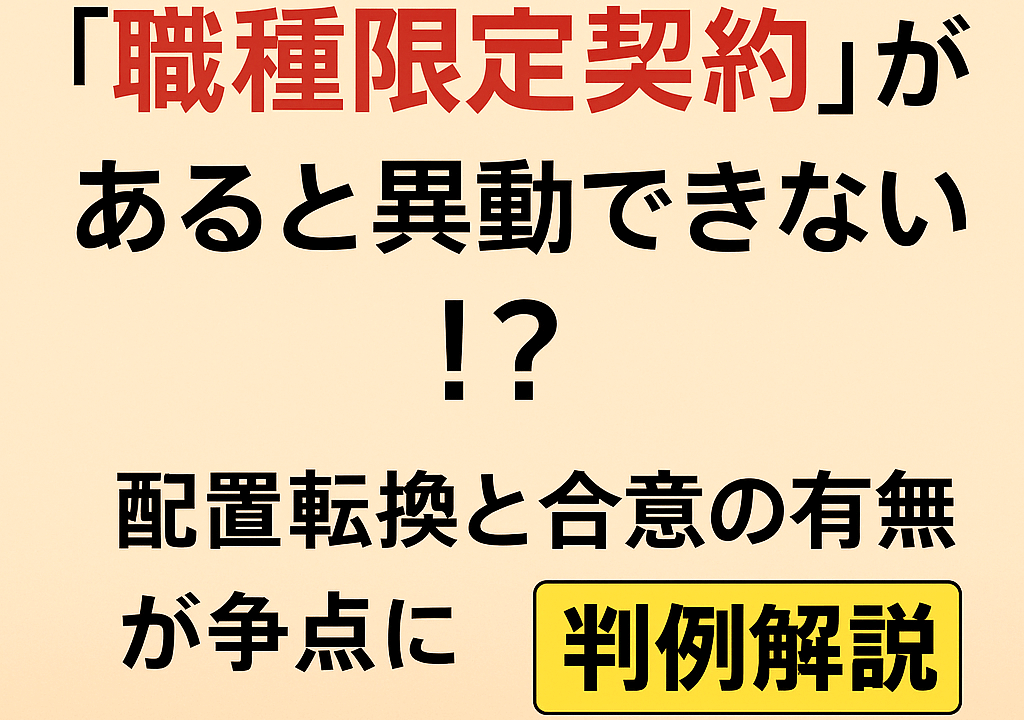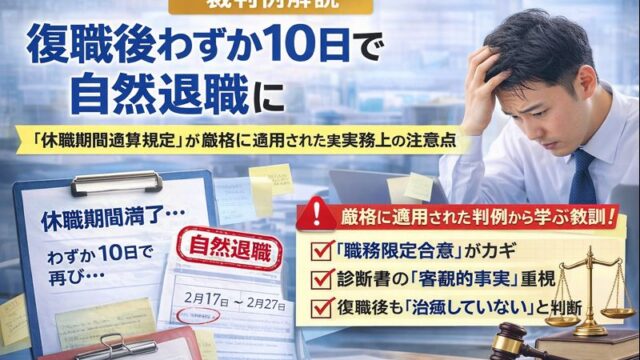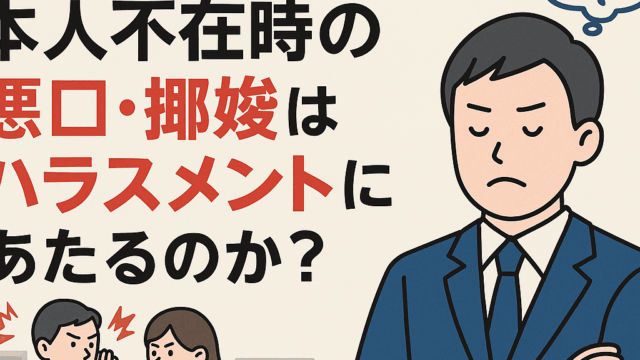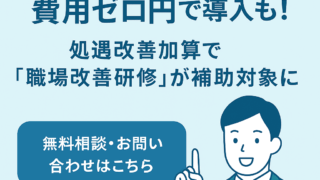~大阪高裁 令和7年1月23日判決/地方社会福祉協議会事件~
■ こんな判例、ご存じですか?
「この仕事しかやらない」という明確な合意はしていなくても、
実質的に“職種が限定された契約”だったと見なされた場合、
会社が勝手に配置転換してよいのでしょうか?
今回は、【黙示の職種限定契約】が争点となった注目の判例をご紹介します。
■ 事案の概要
ある地方の社会福祉協議会で、技術職として採用された労働者がいました。
しかし会社は、担当業務の必要性がなくなったとして、その職務自体を廃止。
労働者の同意を得ることなく、他の職務への配置転換を実施しました。
労働者はこの配置転換が「違法」だとして、裁判に訴えました。
■ 裁判の経過と結論
- 一審(京都地裁)
→ 職種限定合意は認めつつも、解雇を避けるための配置転換は適法と判断。 - 最高裁
→ 職種限定合意があるなら、その職種以外へ異動させる権限自体がなく、
配置転換は「権利の濫用」にあたると判断し、大阪高裁へ差戻し。 - 大阪高裁(令和7年1月23日)
→ 最高裁の判断に基づき、配置転換は違法であり損害賠償を認める判決。
■ 解説:企業が抱える難しさ
この判例は、企業にとって大きな示唆を与えます。
- 「黙示の職種限定合意」があると判断されれば、
たとえ部署がなくなっても他部署に異動させることができないのです。 - 異動できなければ、解雇しか選択肢がないケースもあり、
しかしその解雇が合理的かつ相当であるかは、別のハードルになります。 - 裁判では、職種の廃止が本当に必要だったのかという業務判断の合理性も問われます。
■ 企業が備えるべきポイント
- 採用時・契約時に職種を限定しない記載を行う
(「総合職」「業務内容:会社の指示する業務」など) - ジョブローテーション実績や辞令の記録を残しておく
- 職種変更がある可能性について、日常的に説明しておく
- 職種廃止の必要性を説明できるように、業務整理や組織再編の記録を保持する
■ まとめ
今回の判例は、企業が「当たり前」と思っていた人事異動が
必ずしも自由ではないことを教えてくれます。
「黙示の職種限定合意」があったか否かは、契約書の文面だけでなく、
実際の運用や人事方針が総合的に見られます。
対応を誤ると、異動が「違法」とされ、損害賠償を命じられるおそれも。
職種や配属に関する契約・運用の見直しは、今こそ必要です。