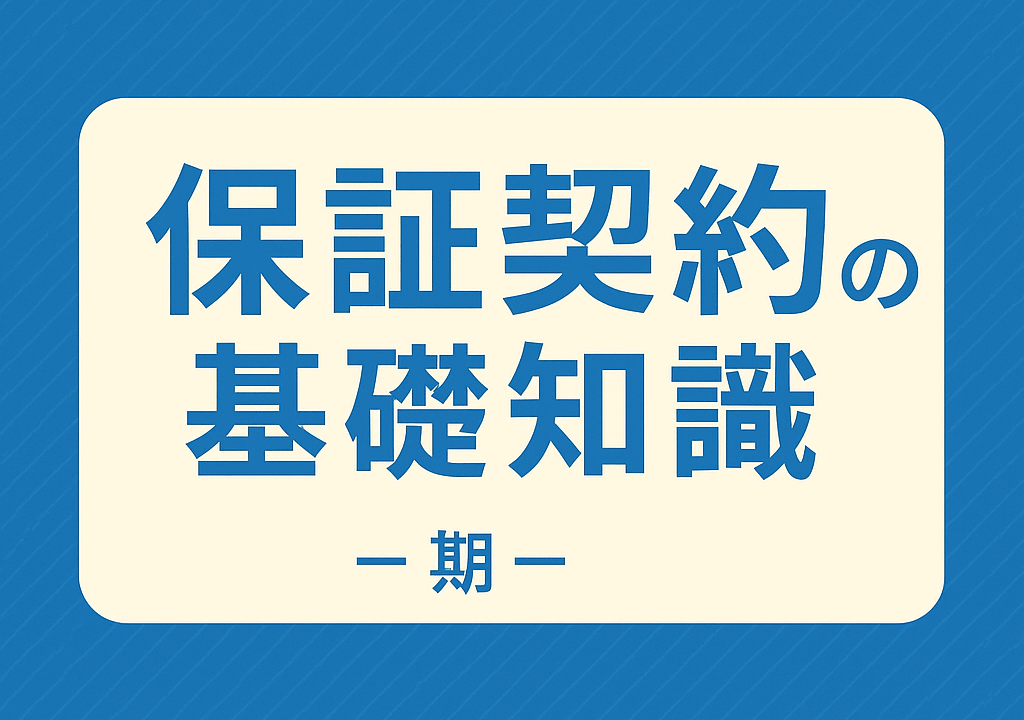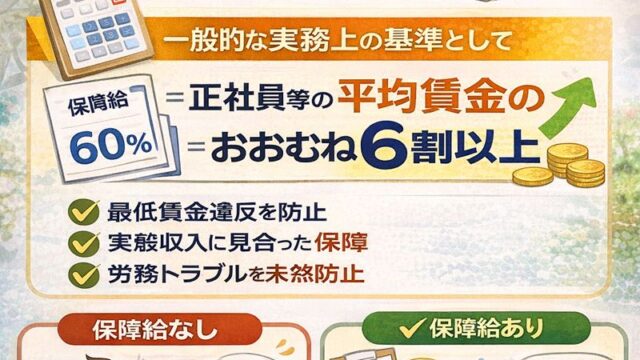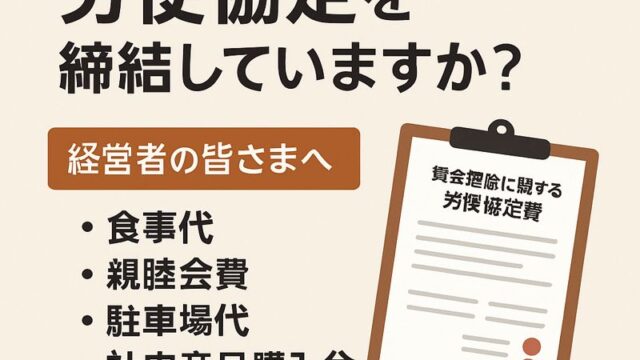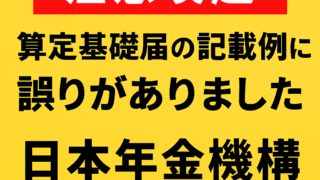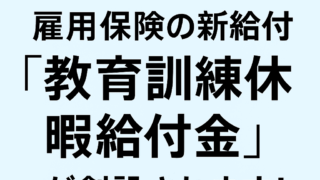~トラブルを防ぐために押さえたい民法のポイント~
2025/07/09|ひらおか社会保険労務士事務所
事業で従業員を雇う際に、「身元保証人」を求めるケースは今も珍しくありません。さらに中小企業では、社長が従業員に対して、事業用資金の借入について「保証人」となるよう依頼する場面もあります。
しかし、保証契約や身元保証制度を正しく理解していないと、契約自体が無効になることも。あるいは、後々、保証人とのトラブルに発展するリスクもあります。
民法における保証契約の基本事項をわかりやすくご紹介します。
1.保証債務の範囲
保証契約とは、「主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わって履行する義務を負う契約」です(民法第446条)。
そして保証人が負うのは、元本だけではありません。以下のような付随的な債務も含まれます(民法第447条)。
- 利息
- 違約金
- 損害賠償金
- その他、主債務に従たるすべてのもの
つまり、保証人の責任は非常に広範囲に及ぶのです。
ただし、保証人が主債務以上の責任を負うことはできません(民法第448条)。
2.保証契約には「書面または電磁的記録」が必要
保証契約は、口頭だけでは無効になります(民法第446条2項)。
必ず「書面」または「電磁的記録(PDF等)」で契約を交わす必要があります。
この規定は、保証人が安易に契約を結ばないよう、慎重な意思確認を促すために設けられたものです。
最近では、電子契約サービスを用いた保証契約も有効とされています。
3.保証人が持つ2つの「抗弁権」
保証人には、一定の条件下で債務の履行を拒める「抗弁権」があります。
(1)催告の抗弁権(民法第452条)
保証人は、債権者から請求を受けた際、「まず主たる債務者に請求してほしい」と主張できます。
ただし、これは裁判外の請求でもよいため、実効性は限定的です。また、主債務者が行方不明・破産などの場合は行使できません。
(2)検索の抗弁権(民法第453条)
主債務者に資力があるときは、「まずはその財産から取り立ててほしい」と主張できます。
この抗弁権を使ったにもかかわらず、債権者が主債務者への請求を怠った場合、保証人は本来なら得られた金額について責任を免れることができます(民法第455条)。
まとめ
保証契約は、単なる「形式的な約束」ではなく、法的責任の重い契約です。
経営者としても、労務管理の一環として関与する社労士としても、基本的な民法の規定を理解しておくことが重要です。
📌 労務管理・契約トラブルの防止をサポートします
ひらおか社会保険労務士事務所では、就業規則や契約書の整備など、法的リスクを回避する支援を行っています。