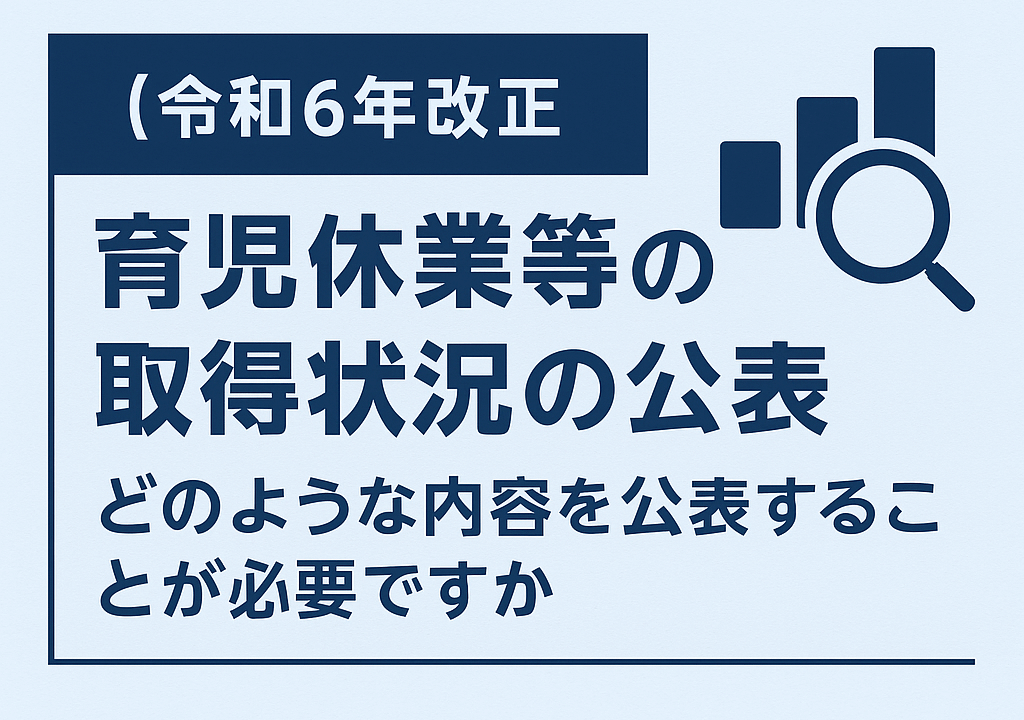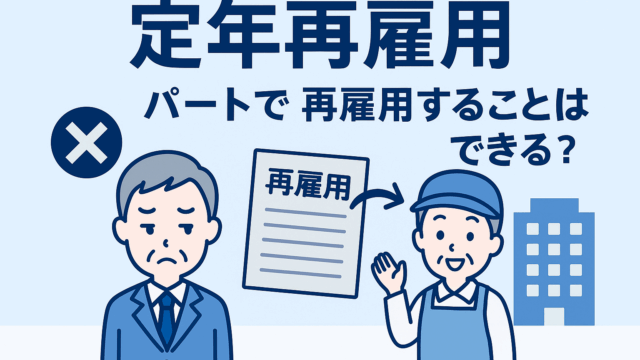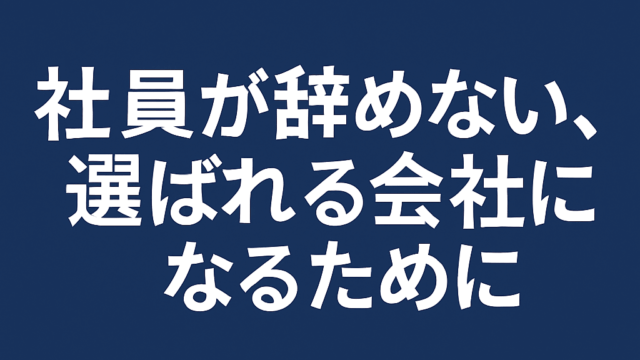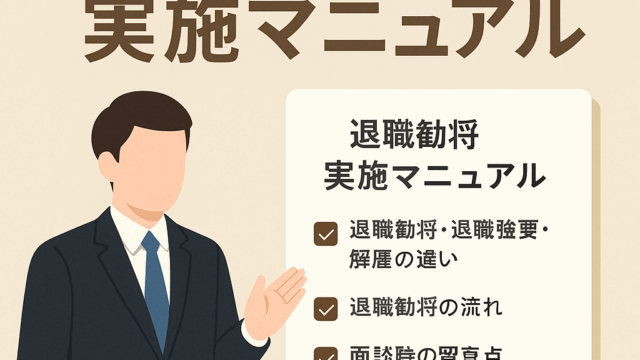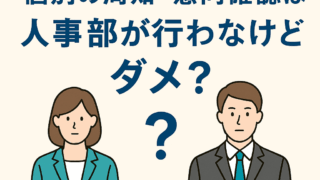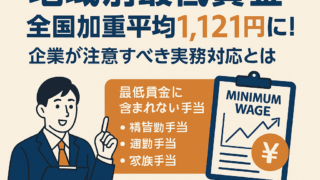こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
令和6年改正育児・介護休業法では、男性の育児休業取得促進を目的に、企業に対して「育児休業等の取得状況」を公表する義務が定められています。
では、どのような内容を公表すればよいのでしょうか。
公表すべき内容
法令(育児・介護休業法施行規則 第71条の6)によれば、以下①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。
① 男性育休取得率
- 分母:「公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者の数」
- 分子:「同じ年度に育児休業等を取得した男性労働者の数」
② 男性育休・休暇利用率
- 分母:「公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者の数」
- 分子:「同じ年度に育児休業等を取得した男性労働者の数」+「小学校就学前の子を養育する男性が利用した育児目的の休暇制度(※子の看護休暇等を除く)の利用者数」
実務でのポイント
- 「育児休業」だけでなく、企業独自の育児目的休暇を導入している場合は②で公表する方法も選択可能です。
- 公表方法は、企業ホームページへの掲載が一般的ですが、求人情報ページや採用サイトへの掲載も望ましいとされています。
- 改正により、令和7年10月1日以降は「養育両立支援休暇」も除外対象に加わる点に注意が必要です。
実務での事例
事例:製薬会社F社の取り組み
F社では男性の育児休業取得率を公表するだけでなく、社内制度として「育児参加特別休暇(3日)」を導入しました。
- 令和6年度:配偶者が出産した男性労働者 50名
- 育児休業取得者 20名
- 特別休暇利用者 15名
➡ 公表時は②の方式を選択し、取得率70%(=(20+15)÷50)と算出。
この公表により、採用応募者から「男性も育休や育児参加がしやすい会社だと感じた」という声が寄せられ、企業イメージ向上にもつながりました。
まとめ
- 公表内容は①「男性育休取得率」または②「男性育休+休暇利用率」
- 公表は企業ホームページ等で行うのが一般的
- 制度導入や運用の工夫次第で、取得率を高め、企業の魅力向上にもつながる
改正法対応は、単なる義務ではなく、人材確保や企業ブランディングにも直結します。