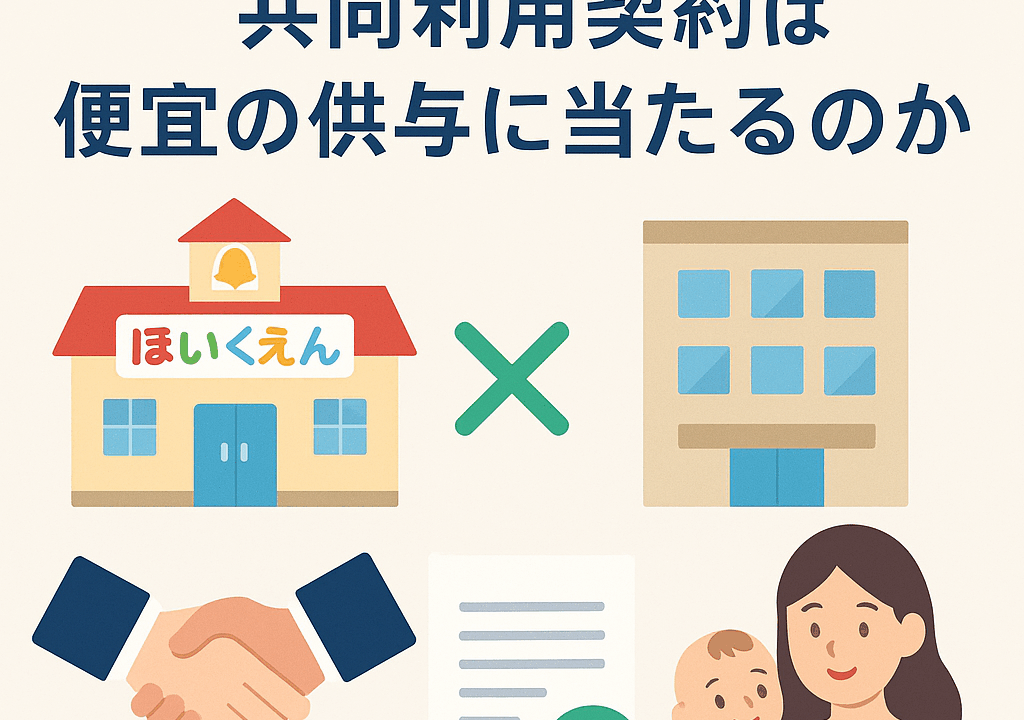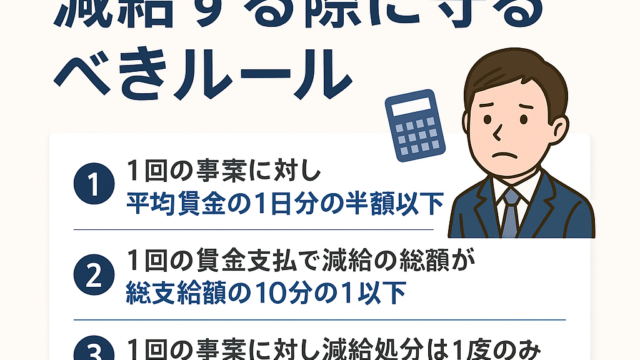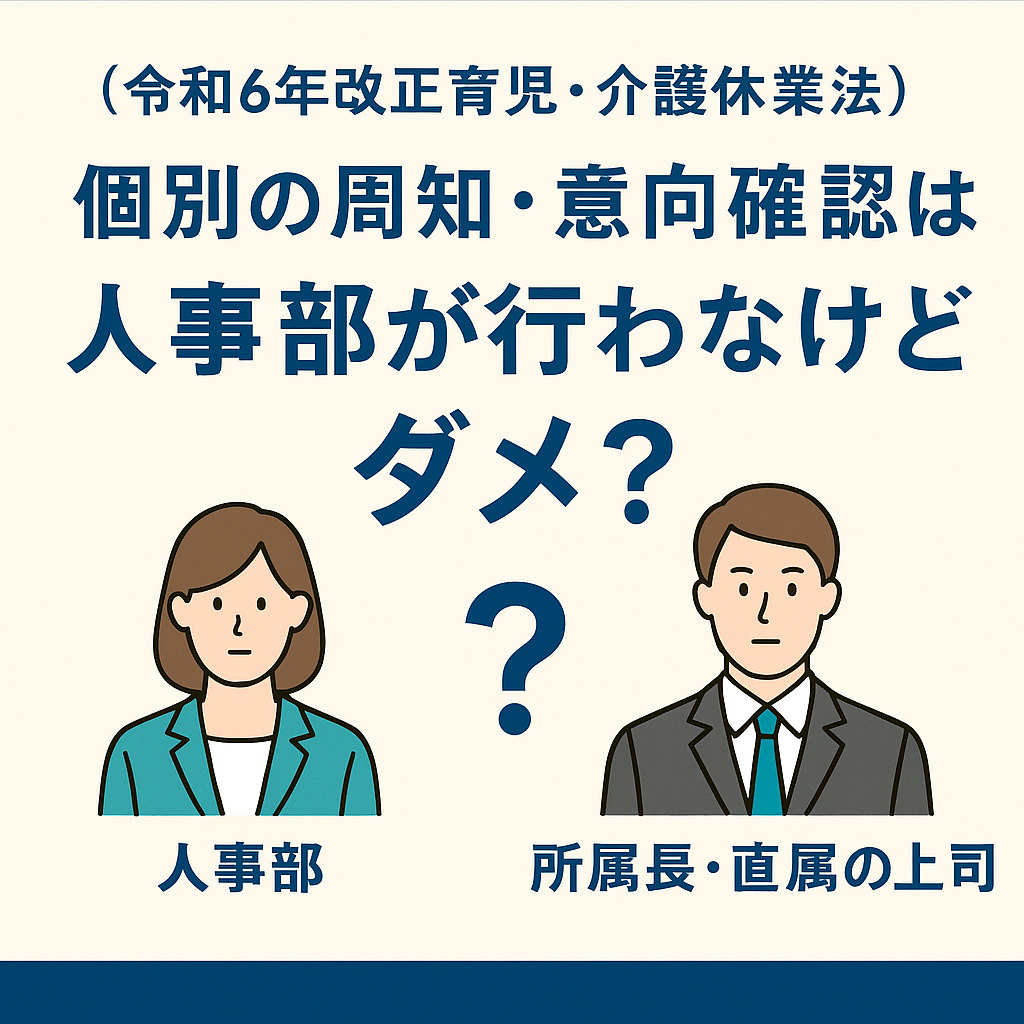こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
今回は、他の事業者が運営する企業主導型保育施設を共同利用する場合に、それが「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められるのかについて解説します。
「便宜の供与」とは?
令和6年改正育児・介護休業法では、事業主が従業員の仕事と育児の両立を支援するため、保育施設の設置運営やこれに準ずる措置を講じることが義務づけられています。
ここでいう「その他これに準ずる便宜の供与」とは、自社で保育施設を設置しなくても、実効性のある保育利用支援を提供していると認められる取り組みを指します。
認められるケース
事業主が以下のような取り組みを行った場合は「便宜の供与」として認められます。
- 他の事業者が運営する企業主導型保育施設と 共同利用契約を締結 する
- 契約に基づき、一定の従業員枠を確保 する
- さらに、保育料の一部または全部を事業主が負担 する
このように「手配(利用枠の確保)」と「費用負担」がそろっている場合、法が求める「便宜の供与」として認められます。
認められないケース
一方で、次のような場合は「便宜の供与」とは認められません。
- 事業主が共同利用契約を結んでおらず、労働者が自ら保育サービス利用の手続を行わなければならない場合
→ 「手配」の要件を満たさない - 契約上、事業主が費用を負担せず、従業員の利用料も通常どおりで減額されない場合
→ 「費用負担」の要件を満たさない
【事例】共同利用契約を活用した中小企業のケース
ある中小企業では、自社で保育所を設置することは難しかったため、近隣の企業主導型保育施設と共同利用契約を結びました。
- 契約により、常時5名分の従業員枠を確保
- 保育料については、会社が月額の半分を負担
この取り組みにより、育児中の従業員が安心して復職でき、特に女性従業員の定着率が向上しました。
結果的に、採用面でも「育児支援がある会社」としてアピールでき、人材確保につながりました。
実務でのポイント
- 契約内容を必ず確認
→ 従業員枠が実際に確保されているか、費用負担があるかを明文化することが必要です。 - 費用負担を制度化する
→ 福利厚生規程などに「会社が負担する割合」を明記するとトラブル防止につながります。 - 従業員への周知
→ 制度があっても知られていなければ活用されません。説明会や社内掲示で必ず周知しましょう。
まとめ
- 他の事業者が運営する企業主導型保育施設と 共同利用契約を結び、枠を確保+費用負担を行えば「便宜の供与」と認められる
- 逆に、契約がなく従業員が自分で手続する場合や、会社の費用負担がない場合は認められない
- 実務では、契約内容と費用負担の仕組みを明確にすることが重要
保育支援は「離職防止」「人材確保」に直結する重要な施策です。自社に最適な方法を一緒に検討してみませんか?
✅ 初回相談は無料です
育児・介護休業法への対応や福利厚生制度の設計について、お気軽にご相談ください。