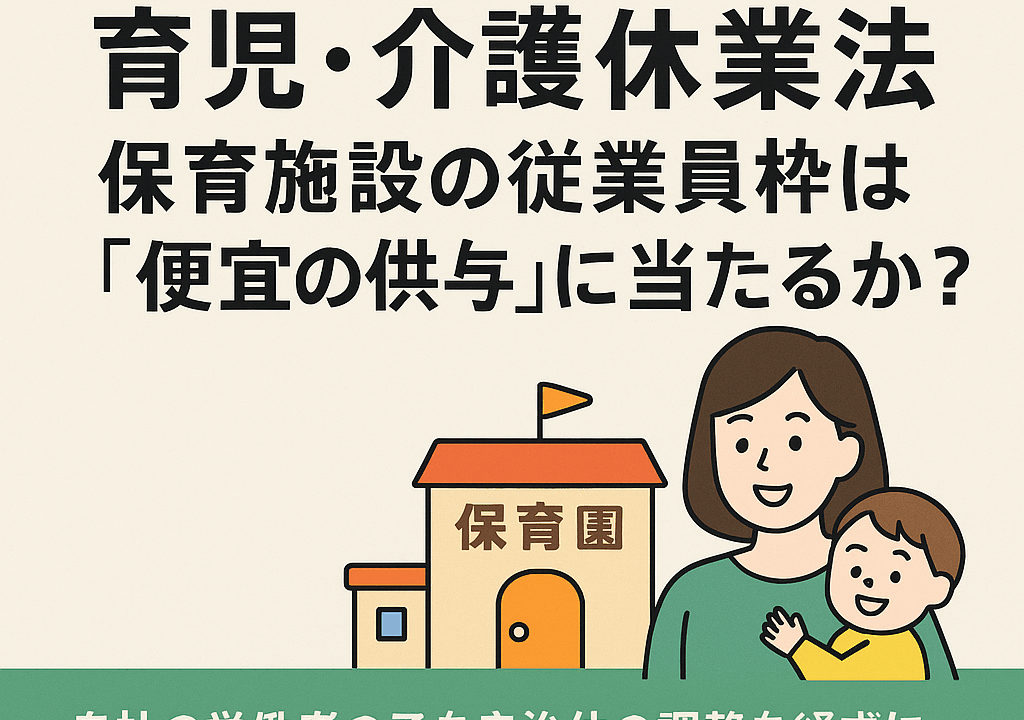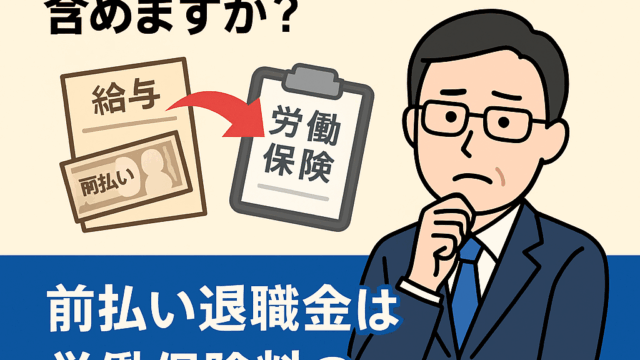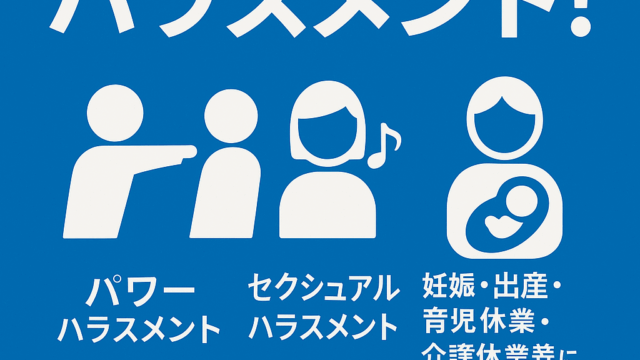こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
今回は、令和6年改正育児・介護休業法の実務対応に関連して、保育施設を運営する事業主が自社従業員の子どもを入園させる場合に「便宜の供与」と認められるかについて解説します。
「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」とは?
改正育児・介護休業法において、事業主は仕事と育児の両立を支援するため、保育施設の設置運営やそれに準ずる措置を講じることが求められています。
この「便宜の供与」に該当するかどうかは、入園の仕組みや従業員枠の運用方法によって判断が分かれます。
認められないケース
事業主が自社で設置運営する保育施設であっても、
- 自社従業員の子どもが 一般利用者と同様に自治体への利用申込・利用調整を経て入園 する場合
このようなケースは「便宜の供与」とは認められません。
→ 理由:自社従業員に対して特別な配慮がされていないため。
認められるケース
一方で、以下のような運用を行う場合は「便宜の供与」として認められます。
- 事業主が運営する保育施設に 従業員専用の入園枠(従業員枠)を設ける
- 自治体の利用調整を経ることなく、従業員が優先的に入園できる
ただし、この従業員枠があまりに少なく、利用を希望する従業員のほとんどが入園できないような場合は「便宜の供与」とは言えません。
【事例】従業員枠を設けた企業のケース
ある介護施設を運営する法人では、事業所内保育所を併設していました。
当初は地域住民と同じく自治体経由での申込が必要だったため、「便宜の供与」とは認められませんでした。
その後、従業員の声を受けて従業員枠(10名程度)を設置し、
- 保育園の空きがない地域でも安心して子どもを預けられる
- 早朝勤務や夜勤対応もしやすくなった
結果として、育児中の従業員の離職が大幅に減少し、企業の人材定着にもつながりました。
実務上の留意点
- 従業員枠は「実効性のある数」を確保すること
→ 実際に利用できる人数がいなければ「便宜の供与」とは言えません。 - 運用ルールを就業規則や社内規程に明記
→ 誰がどのように申込できるかを明確にしておくことが必要です。 - 人材定着・採用力強化に直結
→ 従業員が安心して育児と仕事を両立できる仕組みは、企業価値向上にもつながります。
まとめ
- 自治体を経由して入園する場合は「便宜の供与」とは認められない
- 自社で従業員枠を設け、優先的に入園できる場合は「便宜の供与」として認められる
- 枠の数が実効的であることが前提条件
育児期の従業員を支える仕組みは、労務管理だけでなく採用・定着の観点からも重要です。
運用ルールや規程整備にお悩みの際は、ぜひ専門家へご相談ください。
✅ 初回相談は無料です
育児・介護休業法への対応や就業規則の見直しについて、ぜひお気軽にご相談ください。