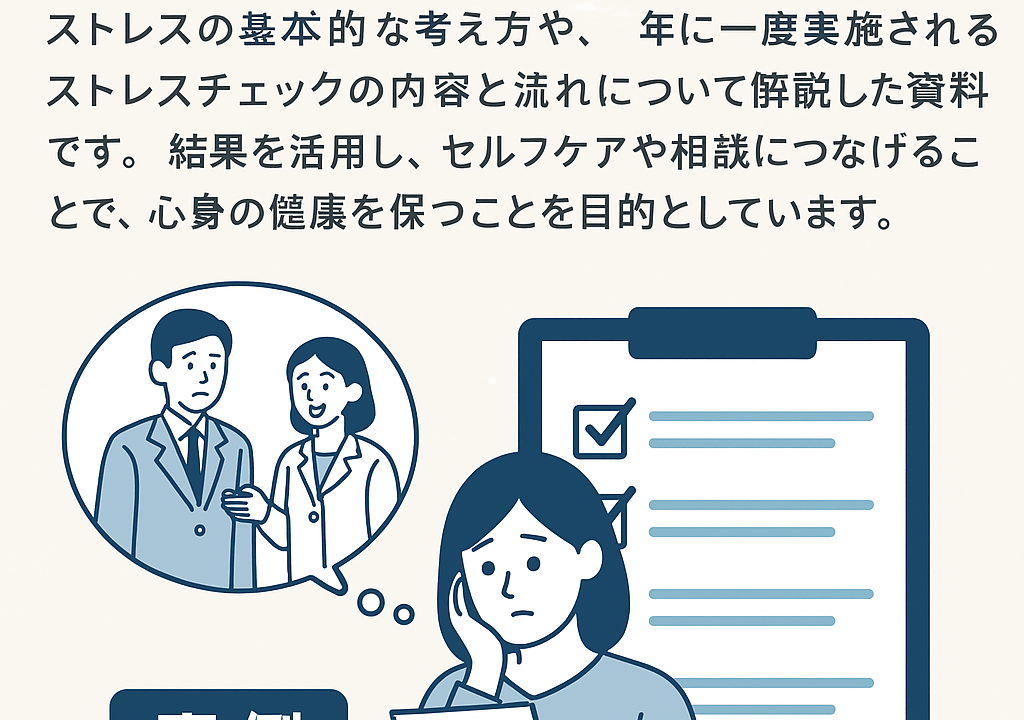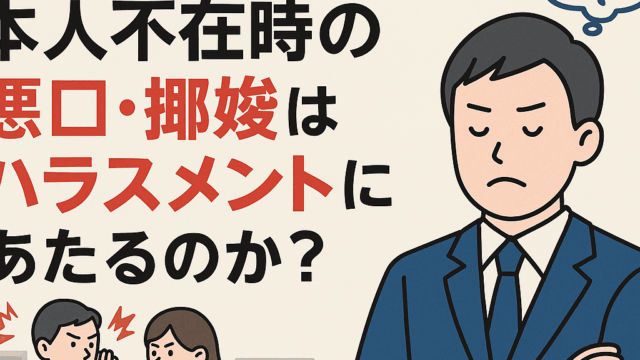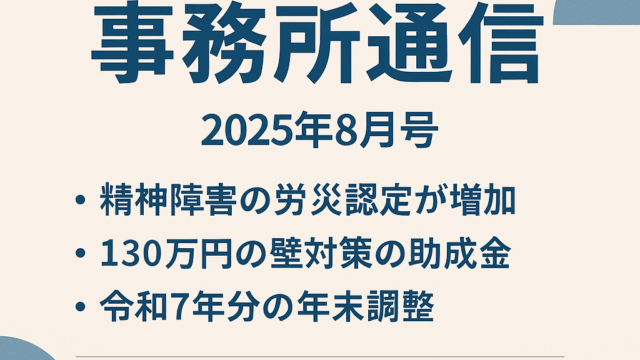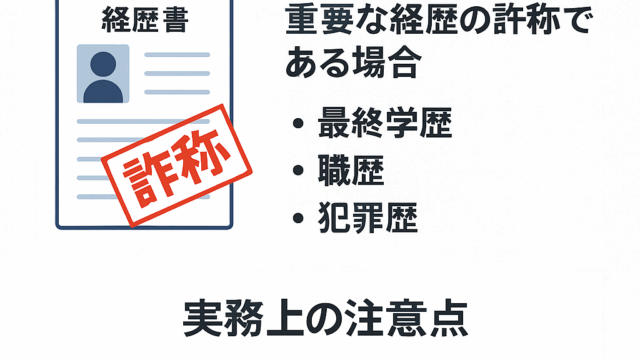働く中で誰もが避けられないのが「ストレス」です。厚生労働省では、従業員が常時50人以上いる事業場に対して、年1回のストレスチェック実施を義務づけています。今回は、ストレスの基本的な考え方やストレスチェックの流れ、そしてその効果的な活用方法についてご紹介します。
ストレスとは?
ストレスとは、外部から刺激を受けたときの心身の緊張状態をいいます。
ネガティブな要因(不安・人間関係のトラブルなど)だけでなく、嬉しい出来事や楽しいイベントもストレスの原因になります。
- 適度なストレス:仕事の集中力を高める
- 過度なストレス:心や身体が適応できず、メンタル不調や体調不良につながる
ストレス要因は大きく次の4種類に分けられます。
- 物理的ストレッサー(暑さ・寒さ・騒音など)
- 化学的ストレッサー(酸素不足・薬物など)
- 心理的ストレッサー(不安・心配など)
- 生物的ストレッサー(炎症・感染など)
ストレスチェックの流れ
ストレスチェックは、以下のステップで行われます。
- 質問票の記入(従業員が自分のストレス状況を回答)
- 評価・判定(医師が面接の要否を判断)
- 結果の通知(本人へフィードバック)
- 必要に応じた医師面接・職場改善
この仕組みは、従業員の心身の不調を未然に防ぐ「一次予防」を目的としています。
活用のポイント
ストレスチェックは、ただ「やる」だけでは意味がありません。結果を踏まえ、次のように活用していくことが重要です。
- セルフケアにつなげる
腹式呼吸やヨガ、適度な運動、趣味の時間など、自分に合った方法で心身をリフレッシュしましょう。 - 相談やサポートにつなげる
一人で抱え込まず、社内の相談窓口や産業医、外部の専門機関に早めに相談することが有効です。
【事例】ストレスチェックを職場改善に活かしたケース
ある製造業の会社では、毎年ストレスチェックを実施していましたが、単に結果を通知するだけで終わっていました。
しかし、ある年の結果で「特定の部署のストレス度が高い」ことが分かり、詳細を確認したところ、作業環境の暑さや残業時間の偏りが原因でした。
会社はその後、空調設備の改善と人員配置の見直しを行い、翌年のストレスチェックでは高ストレス者が大幅に減少。従業員満足度も向上しました。
まとめ
ストレスチェックは「義務だからやるもの」ではなく、従業員の健康を守り、組織のパフォーマンスを高める大切な仕組みです。
結果を活かし、セルフケアや相談体制の整備、さらには職場改善につなげていくことで、働きやすい職場づくりが実現できます。
👉 まずは「ストレスチェックの結果をどう活用するか」を社内で話し合ってみてはいかがでしょうか。
ストレスチェックの活用や体制づくりについて、専門家が伴走します。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。