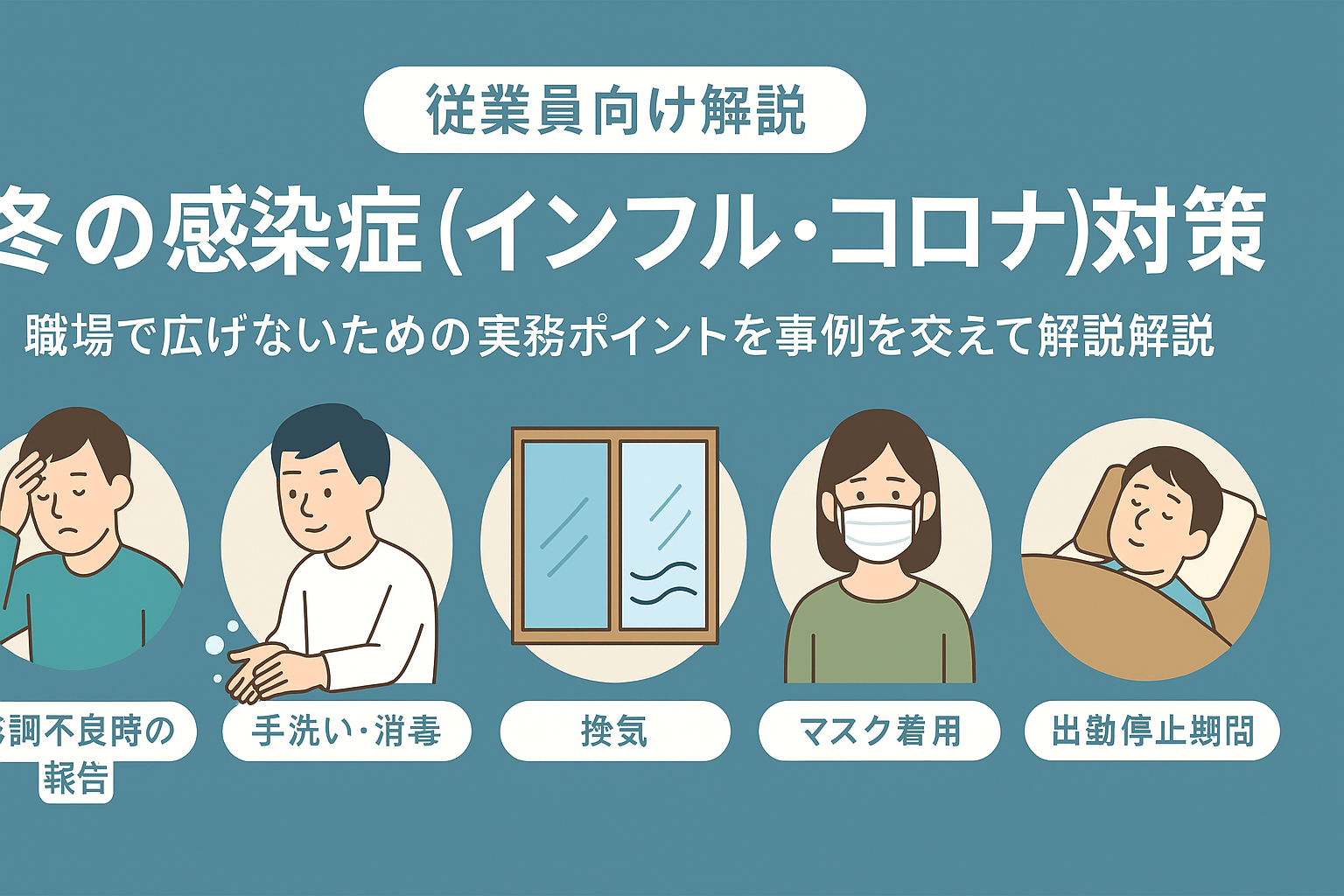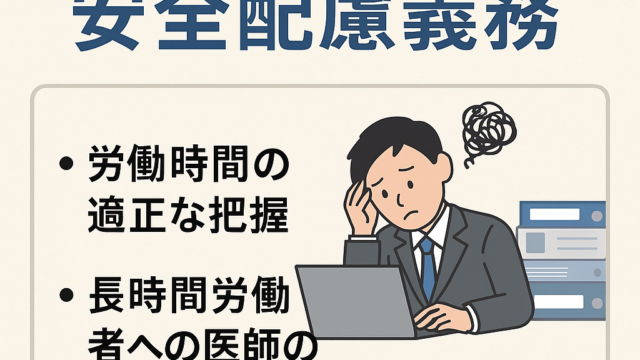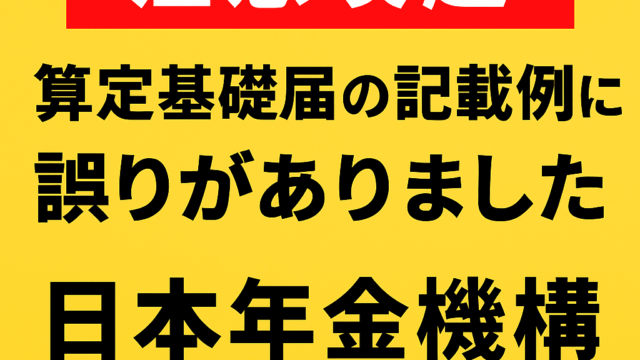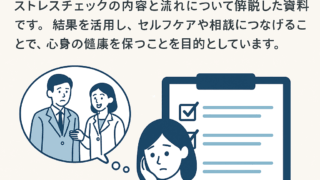家内労働者とは?
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
例えば、衣服の縫製、部品の組み立て、アクセサリーの加工など、家庭内でできる軽作業が典型です。
労働基準法との違い
一方、労働基準法が適用される「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています(労基法第9条)。
つまり、会社や工場に雇われ、使用者の指揮命令のもとで働く人が対象です。
家内労働者は一般的にこの「労働者」には該当せず、労働基準法の保護を受けることはできません。
その代わりに、「家内労働法」という特別な法律が適用されます。
家内労働法の目的
家内労働法は、家内労働者の就業条件や工賃の支払方法を定め、適正な労働環境を守るために制定されています(家内労働法第1条)。
労働基準法と比べると保護範囲は限定的ですが、委託者に対して工賃台帳の作成や明細書の交付を義務づけるなど、最低限のルールが設けられています。
事例紹介
例えば、Aさんは在宅で洋服の縫製を行っており、委託元の会社から布地や糸を受け取り、完成品を納品するごとに出来高払いで工賃を受け取っています。
Aさんは会社に雇われているわけではなく、勤務時間や働き方も自分で決めています。この場合、Aさんは「労働基準法上の労働者」には当たらず、家内労働法の対象者として扱われます。
根拠法令・参考情報
- 家内労働法 第1条(目的)
- 労働基準法 第9条(定義)
👉 労務管理や法令対応で不安がある場合は、専門家にご相談ください。
無料相談・お問い合わせはこちら