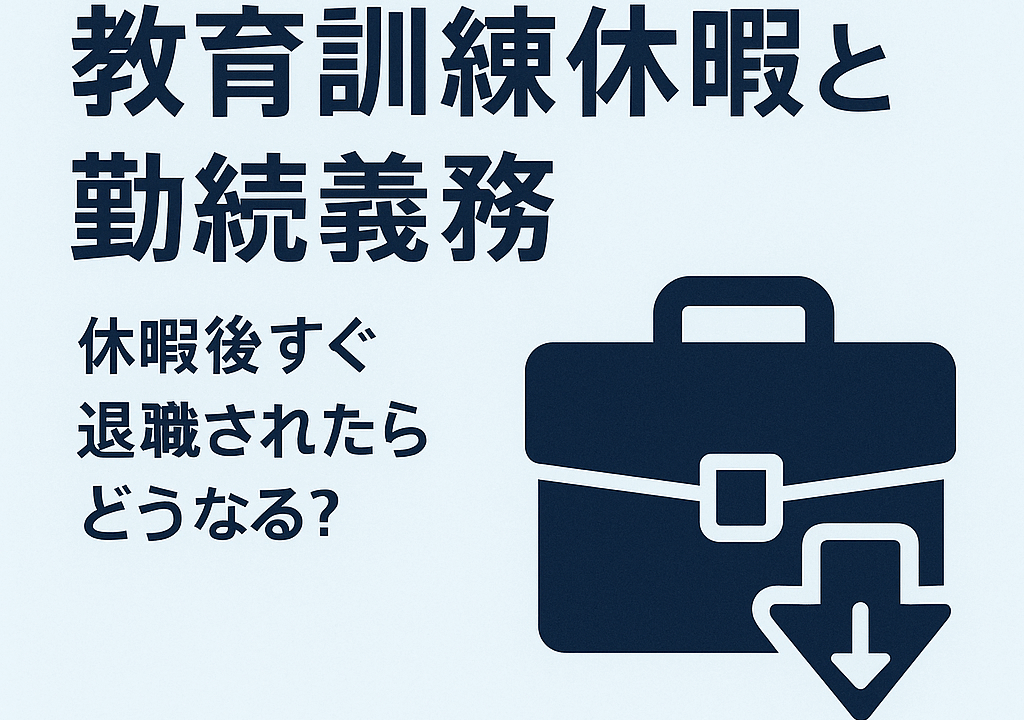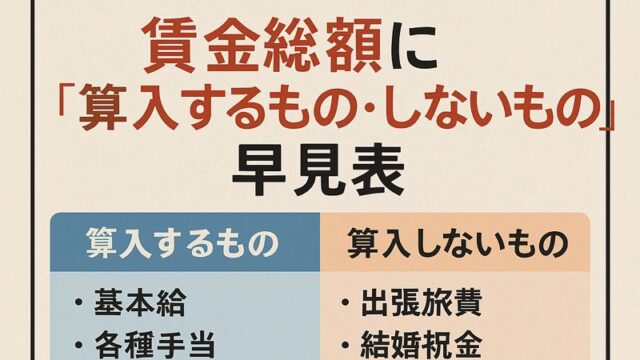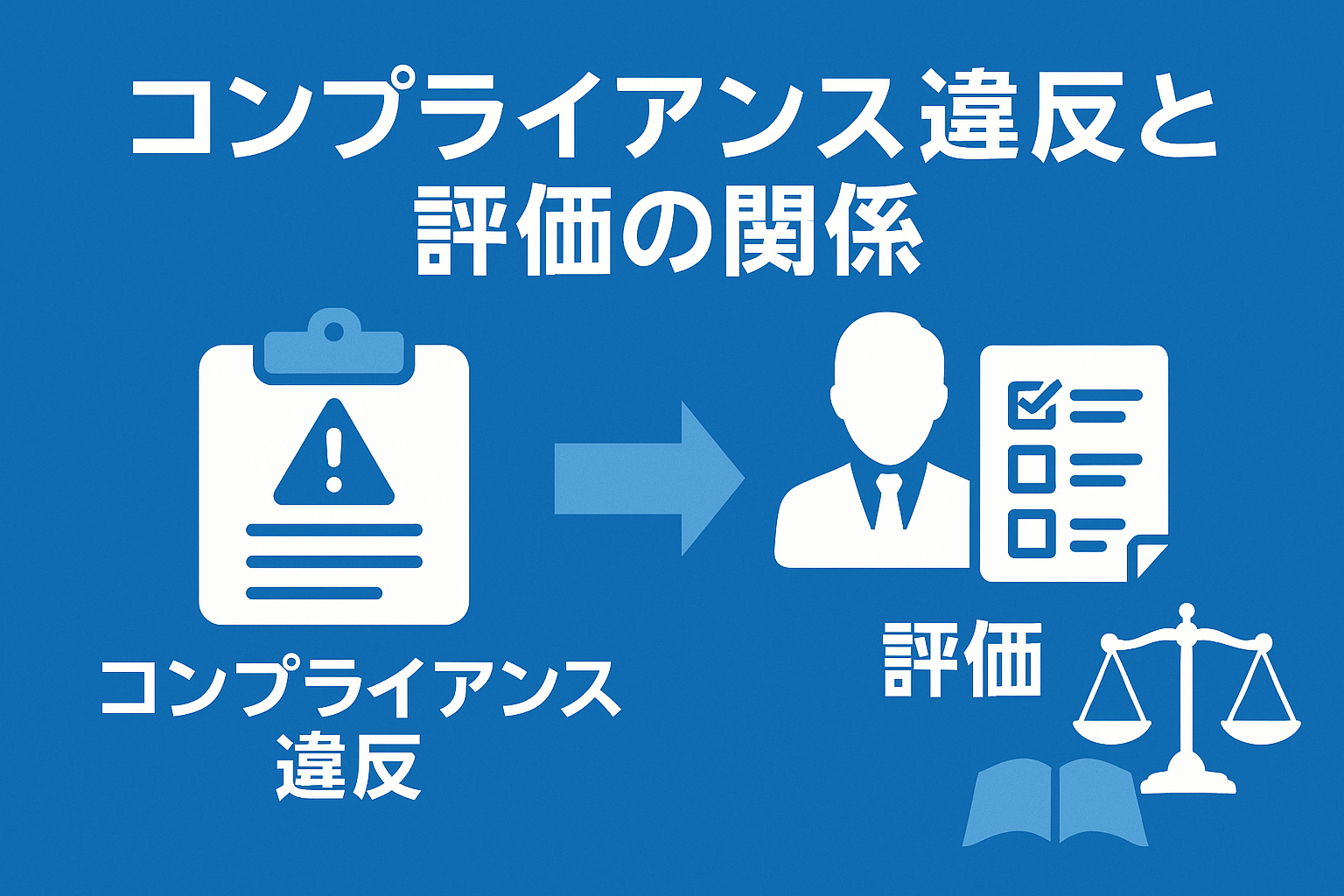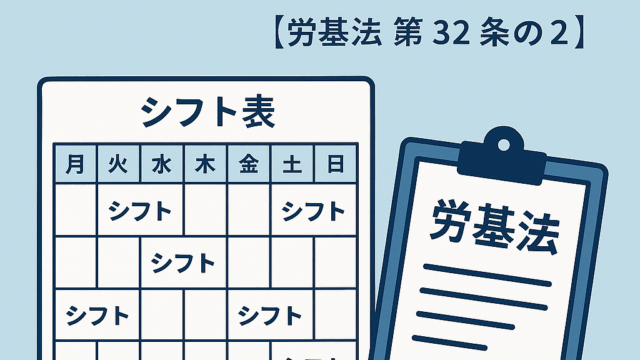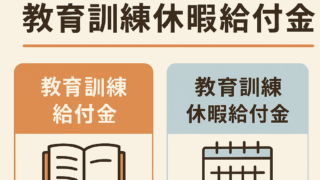企業の人材育成施策の一つとして「教育訓練休暇制度」を導入するケースが増えています。
しかし、教育訓練休暇を取得した従業員が、休暇後にすぐ退職してしまった場合、会社として「一定期間の勤続義務」を課すことはできるのでしょうか。
法的原則:勤続義務は設定できるのか?
結論から言えば、教育訓練休暇を理由とした勤続義務の設定は法的に困難です。
- 憲法第18条:奴隷的拘束の禁止
- 憲法第22条:職業選択の自由の保障
- 民法第627条:期間の定めのない雇用の解約自由
これらの規定により、労働者の退職の自由は強く保護されています。
さらに、憲法上の権利は民法の公序良俗条項(民法第90条)を通じて間接的に適用されるため、過度な勤続義務を課すことは「無効」とされるリスクが高いといえます。
実務上の留意点
教育訓練休暇を理由に退職を制限できない一方で、実務的に注意すべき点があります。
助成金への影響
教育訓練に関連する雇用関係助成金では、受給要件として一定期間の雇用維持が求められる場合があります。
休暇取得後に退職や雇止めを行うと、助成金が不支給または返還となるリスクがあるため注意が必要です。
制度設計における工夫
- 教育訓練休暇の目的・性質の明確化
- 費用負担を伴う研修制度との区別
- 就業規則や制度要項への明文化
これらを整備することで、従業員への誤解やトラブルを防止できます。
補足すべき観点:合理的な制約は可能か?
完全に制約を課すことは困難ですが、以下のような合理的な対応は考えられます。
| 検討項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用負担との関係 | 会社が高額な研修費用を負担した場合、「一定期間内に退職すれば費用の一部を返還する」合意は有効となる可能性あり |
| 労使合意の重要性 | 制度導入時に十分な協議を行い、従業員の理解と合意を得ることが不可欠 |
| 就業規則の整備 | 教育訓練休暇の定義、取得要件、費用負担の有無、効果などを明確に規定 |
事例
事例①:教育訓練休暇後にすぐ退職
従業員が教育訓練休暇を取得し、資格試験に合格。その直後に転職したが、会社は勤続を強制できず、結果的に助成金の一部が不支給となった。
事例②:費用返還合意による対応
会社が外部研修費用を全額負担し、就業規則と個別同意書で「1年以内に退職した場合は費用を返還」と規定。従業員が半年で退職したが、返還合意が合理的と認められ、費用の一部を回収できた。
まとめ
- 教育訓練休暇に勤続義務を直接設定することはできない
- 憲法・民法により労働者の退職の自由は強く保護されている
- 助成金への影響や、費用負担型研修制度との区別に注意が必要
- 高額な費用負担を伴う場合は、合理的範囲での返還合意が有効となる場合がある
制度導入時には、就業規則の整備と従業員への丁寧な説明・合意形成が不可欠です。