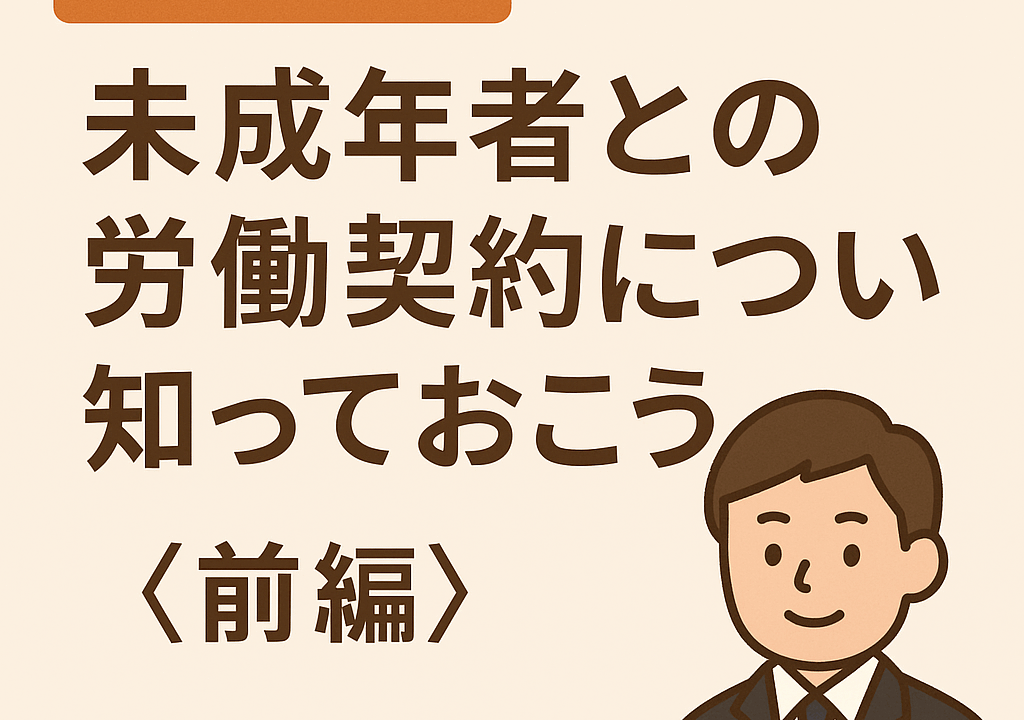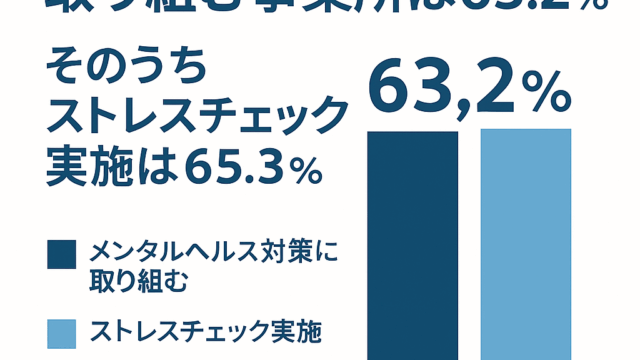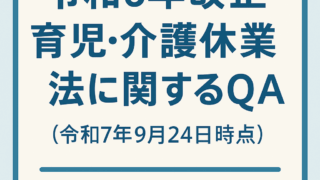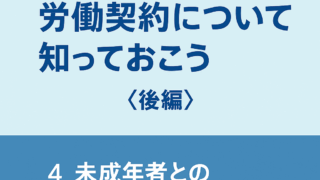(2025/09/21 連載記事)
こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
企業がアルバイトやパートで未成年者を雇用することは珍しくありません。しかし、未成年者は民法上「制限行為能力者」とされており、労働契約の締結には特有のルールが存在します。知らずに契約してしまうと、後から「契約が取り消された」といったトラブルに発展する可能性もあります。今回は 民法と労働基準法の基本的な位置づけ を整理し、実務で押さえておきたいポイントを解説します。
1 未成年者とは
民法4条では「年齢十八歳をもって、成年とする」と規定されています。
したがって、18歳の誕生日を迎える前日までは未成年者とされます。
例:2005年9月20日生まれの人は、2023年9月19日まで未成年者であり、2023年9月20日から成年になります。
2 未成年者の法律行為の原則
未成年者が法律行為(契約など)を行う場合、原則として 法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意 が必要です(民法5条)。
同意がない法律行為は、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます。
- 取り消しが行われると、法律行為は最初から無効に戻る(民法121条)。
- ただし「単に権利を得、又は義務を免れる」行為(例:贈与や債務免除)には同意は不要です。
3 同意の方法
- 明示・黙示どちらでも有効(民法122条)。
- 事前の同意だけでなく、契約後に追認することも可能です。
親権者が父母の場合
婚姻中であれば共同で親権を行使するため、原則として 両親の同意 が必要です(民法818条)。
ただし、父母の一方が反対していたとしても、相手方がその事実を知らなければ同意は有効とされます(民法825条)。
【事例】高校生アルバイトの契約取り消し
ある飲食店が17歳の高校生とアルバイト契約を結びましたが、親が「学業に支障がある」と反対し、後日契約を取り消しました。
結果として契約は初めからなかったことになり、店舗側はシフト調整や人員確保に追われることに…。
👉 このように、未成年者の場合「法定代理人の同意」を確認していないと、後で大きなトラブルにつながることがあります。
実務ポイント(前編まとめ)
- 18歳未満は未成年者として扱うことを確認。
- 契約時に保護者同意書を取得する運用を徹底。
- 同意は事前でも事後でも有効だが、書面で残すことが安心。
📌 後編では、労働基準法に定められた未成年者保護規定(労働時間・深夜労働・危険有害業務など)について解説します。
➡️ 初回相談は無料です。労働契約や就業規則のご相談はお気軽にどうぞ!