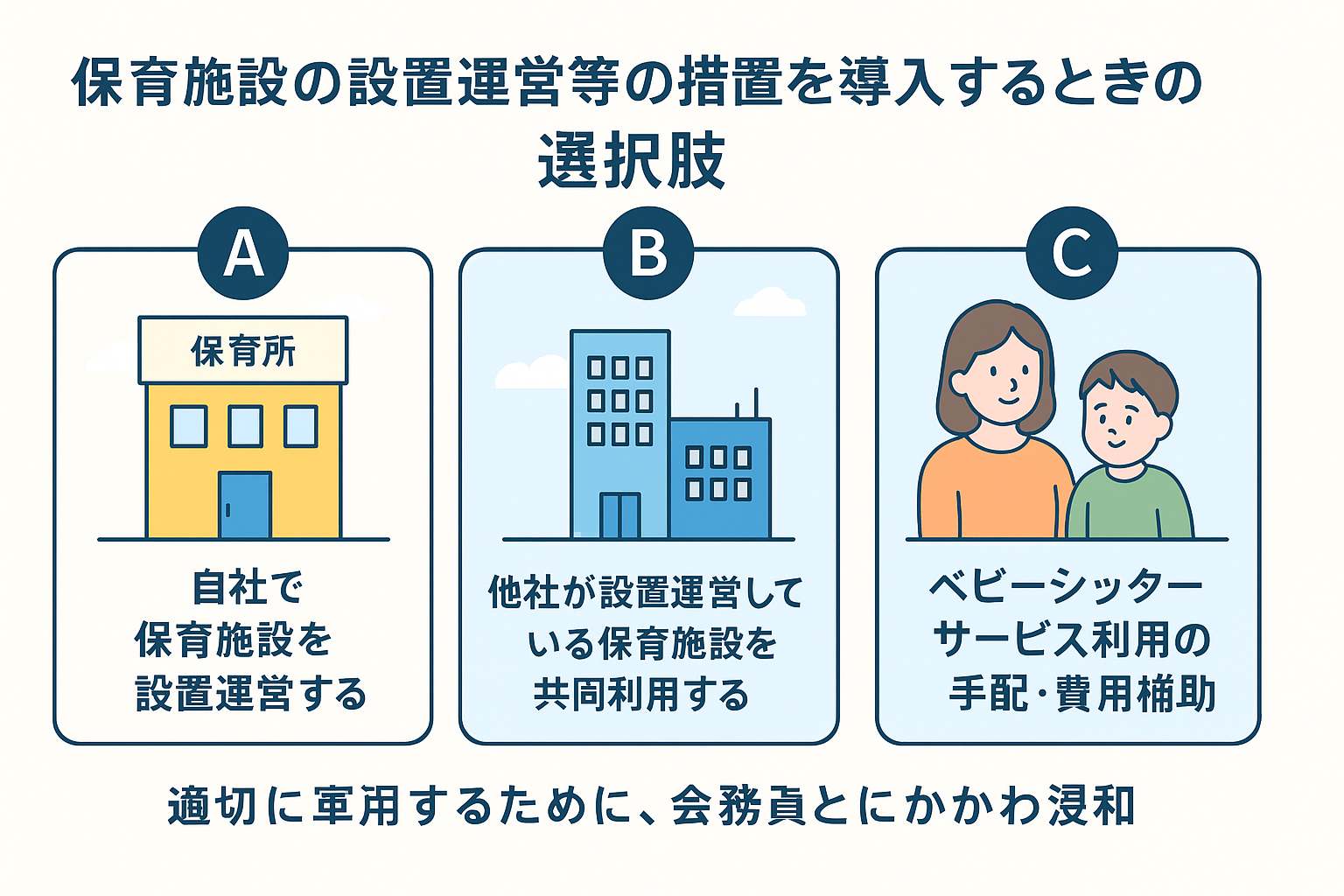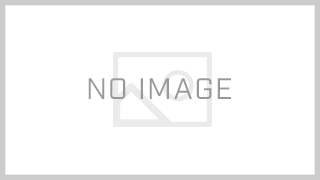~退職時に費用を返還させる仕組みは有効?~
社員のスキルアップや業務に必要な資格取得をサポートするために、会社が受験料や研修費用を補助することは珍しくありません。
しかし、取得後すぐに退職されてしまった場合、「せっかく会社が費用を負担したのに…」という状況も起こり得ます。
そこで多くの企業が取り入れているのが、「一定期間内に退職した場合は資格取得費用を返還してもらう」という合意(返還合意)」です。
今回は、この返還合意が有効とされるポイントや実務上の留意点を整理します。
有効性の判断ポイント
① 合理的な期間設定
返還義務の期間は、一般的に 2~3年程度 が妥当とされています。
資格の性質や取得にかかる時間を考慮し、過度に長い拘束期間は避ける必要があります。
② 金額の妥当性
返還を求められる金額は、実際に会社が負担した費用の範囲内 でなければなりません。
過大な金額を請求することは認められません。
③ 業務との関連性
資格が会社の業務に必要であり、取得によって会社に利益があることも重要な判断材料です。
例えば業務独占資格や業務に直結する資格の場合は、有効と判断されやすくなります。
返還合意のひな型例
(資格取得費用の貸与および返還)
第○条 会社は、業務上必要と認める資格の取得について、従業員の申請に基づき、
受験料、講習料、教材費等の費用を貸与することができる。
2 前項の費用の貸与を受けた従業員が、資格取得後○年以内に自己の都合により
退職した場合は、貸与を受けた費用の全額を会社に返還しなければならない。
ただし、勤続期間に応じて次のとおり減額する。
・勤続○年未満:全額
・勤続○年以上○年未満:○%
・勤続○年以上:返還義務なし
3 前項の返還義務は、懲戒解雇その他従業員の責めに帰すべき事由による
退職の場合も同様とする。
4 会社都合による退職の場合は、返還義務を免除する。
注意事項
労働基準法との関係
- 賃金から直接控除する場合には 労使協定が必要 です。
- 損害の実費を超える返還請求は、労基法16条違反 と判断される可能性があります。
合意書の重要性
- 資格取得前に必ず書面で合意 を取ることが必要です。
- 返還条件を明確に記載することで、トラブルを防止できます。
段階的減額の検討
- 勤続年数に応じた 段階的な減額制度 を設けると合理性が高まります。
- 「一律全額返還」よりも、裁判所で有効と判断されやすくなります。
事例紹介
東京地裁令和5年10月26日判決では、
自動車教習所の指導員資格取得費用について、3年以内に退職した場合は返還を求める合意 が有効とされました。
裁判所は、
- 教習指導員資格は国家資格であり、個人の転職にも有利
- 資格取得後は手当がつき、労働者の利益も大きい
- 返還期間は3年と妥当な長さ
と判断し、労基法16条違反にはあたらないとしました。
まとめ
資格取得費用の返還合意は、
- 合理的な期間(2~3年程度)
- 実費相当額の返還
- 業務に必要な資格であること
といった条件を満たせば有効とされる可能性が高いです。
ただし、すべてのケースで有効とは限らないため、制度設計時には慎重な検討と書面化 が不可欠です。
📌 資格取得支援制度や返還合意の導入に関するご相談は、ぜひお気軽にご相談ください。
👉 無料相談・お問い合わせはこちら