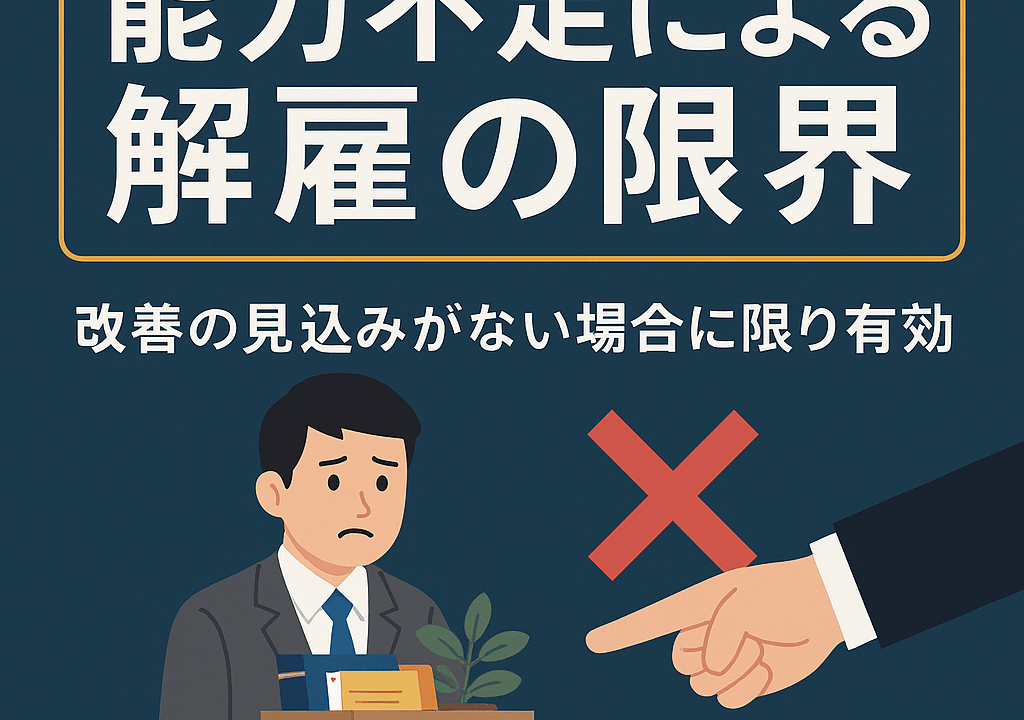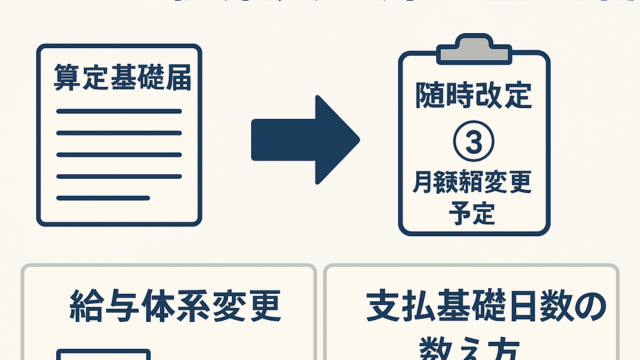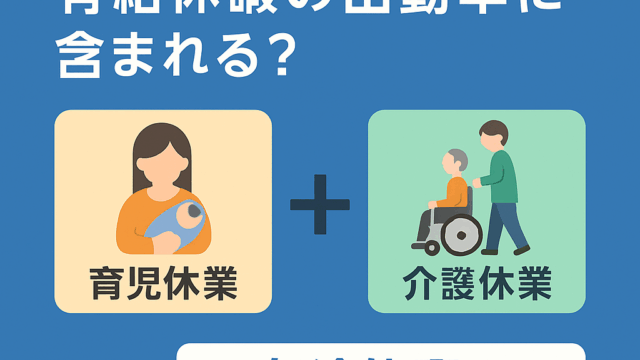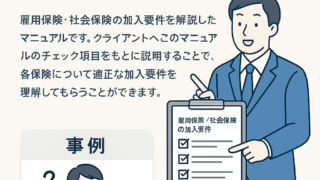はじめに
「能力不足の従業員を解雇できるか?」――
多くの企業が直面する難しいテーマです。
しかし、能力不足を理由とした解雇は、実務上きわめて慎重な対応が求められます。
本記事では、東京地裁が示した代表的な判断例「セガ・エンタープライゼス事件(平11・10・15)」をもとに、
企業として押さえるべき実務上の注意点をわかりやすく解説します。
1.事件の概要(セガ・エンタープライゼス事件)
業務用娯楽機械を製造・販売する会社の従業員(Xさん)は、複数部署を異動したのち、最終的に担当業務のない部署に配置されました。
会社はXさんに退職勧奨を行いましたが、これを拒否。
その後、会社は「人事考課上の順位が下位10%未満である」ことを理由に、
就業規則の「労働能率が劣り、向上の見込みがない」とする規定を根拠に能力不足解雇を行いました。
これに対し、Xさんは「解雇無効」として裁判所に申立てを行いました。
2.裁判所の判断(東京地方裁判所 平成11年10月15日決定)
(1)「労働能率が劣り、向上の見込みがない」とは
裁判所は、就業規則の文言を厳格に解釈し、
単に平均水準より能力が劣るというだけでは不十分であり、
「著しく労働能率が劣り、かつ向上の見込みがない」場合に限り、
能力不足による解雇が認められると判断しました。
✅ 相対的に評価が低い(下位10%など)というだけでは解雇理由にはならない。
✅ 教育・指導などで改善の見込みがある場合は「向上の見込みがない」とはいえない。
(2)人事考課の限界
人事考課は相対評価であり、「平均以下」という結果だけで
「著しく労働能率が劣る」とまではいえないとしました。
また、会社側が十分な教育や指導を行わず、改善の機会を与えなかった点も問題視されました。
(3)結論
裁判所は、会社の解雇を「権利の濫用」として無効と判断しました。
3.実務で押さえるべきポイント
① 「能力不足=即解雇」ではない
労働契約法第16条では、
解雇は「客観的に合理的な理由」を欠き、「社会通念上相当」でなければならない
と定められています。
つまり、平均以下=解雇可能ではなく、
「著しく低い能力で、改善の見込みがない」ことを会社側が具体的に立証しなければなりません。
② 教育・指導の実施が不可欠
判例は、会社が「体系的な教育・指導」を行っていれば改善の可能性があったと指摘しています。
実務上は、次のようなステップを踏むことが重要です。
| ステップ | 内容 | 書面記録の例 |
|---|---|---|
| ① 指導・教育 | 上司による具体的な改善指導 | 面談記録、指導書 |
| ② 評価・フォロー | 成果を一定期間観察し再評価 | 評価シート、フィードバック記録 |
| ③ 最終確認 | なお改善が見られない場合に対応検討 | 就業規則・評価履歴 |
このプロセスを経ずに「解雇」に踏み切ると、裁判で不当解雇と判断されるリスクが極めて高くなります。
③ 相対評価だけに頼らない
セガ事件でも、人事考課の順位(下位10%)が重視されていましたが、
裁判所はこれを相対評価にすぎないと指摘しました。
したがって、評価に基づいて処分を行う場合は、
相対順位ではなく、職務上の具体的なパフォーマンス基準(絶対評価)を明確にしておくことが大切です。
4.実務事例:評価制度と解雇トラブル防止策
【事例】
A社では、営業職の従業員Bさんが3期連続で営業成績が最下位でした。
上司は「結果が出ていないから能力不足」と判断し、退職を勧めましたが、Bさんは拒否。
A社は最終的に解雇しましたが、Bさんは裁判で「不当解雇」と主張しました。
【結果】
裁判所は、A社が教育・改善機会を与えていなかった点、
また評価基準が「相対的な順位」にすぎなかった点を理由に、解雇を無効と判断しました。
5.まとめ:能力不足による解雇は慎重に
- 能力不足解雇には、絶対的な能力欠如と改善不能性が必要
- 相対評価(順位)だけでは不十分
- 改善指導・教育機会を記録として残すことが重要
- 不当解雇と判断されれば、職場復帰や賃金支払命令が出る場合も
【事件情報】
- 事件名:セガ・エンタープライゼス事件
- 裁判所:東京地方裁判所
- 決定日:平成11年10月15日
- 事件番号:平成11年(ヨ)第21055号
- 関連条文:労働契約法 第16条
ひらおか社会保険労務士事務所より
当事務所では、企業の「人事評価制度の設計」「能力不足者対応マニュアル」「退職勧奨の進め方」など、
トラブルを防ぐための仕組みづくりを支援しています。
💬 人事評価・解雇トラブルのご相談は → お問い合わせはこちら