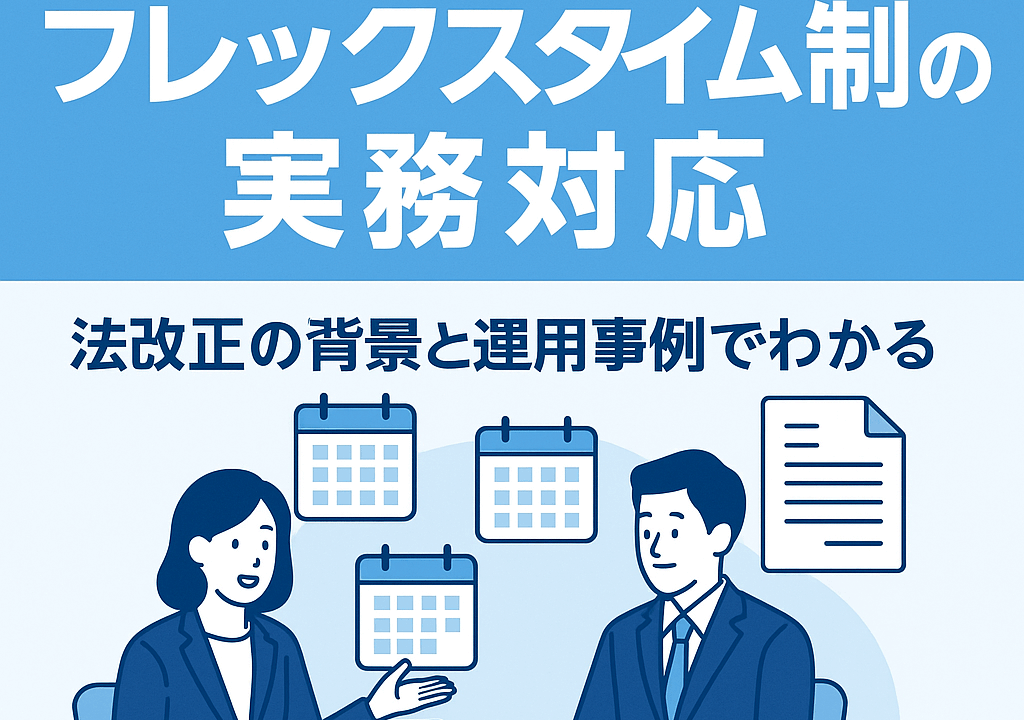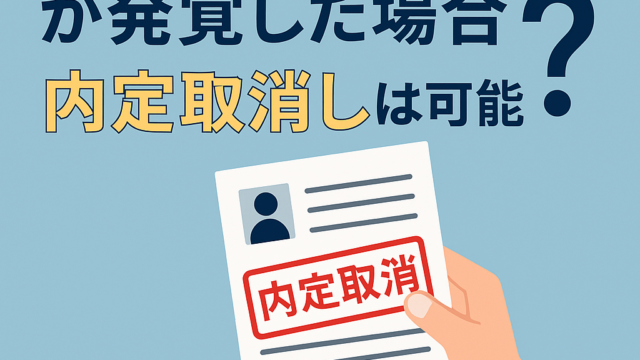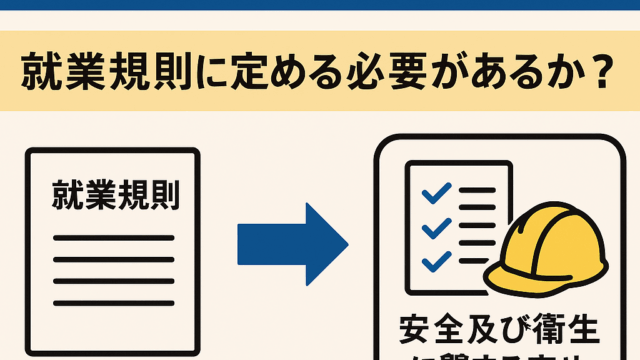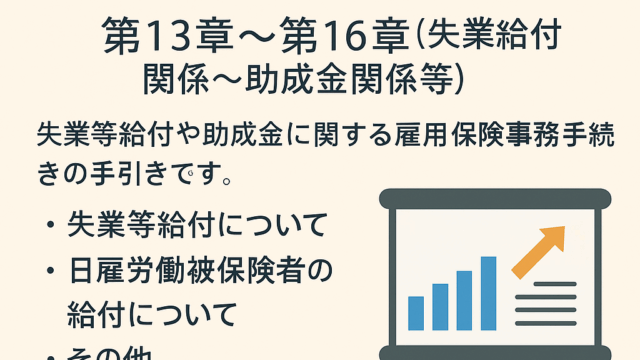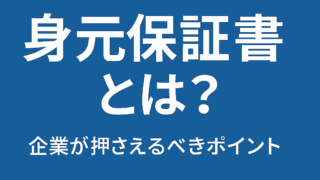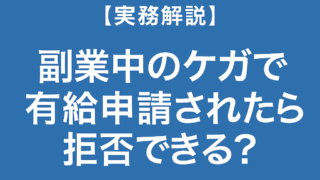~法改正の背景と運用事例でわかる実務対応~
1.複数月フレックスタイム制とは?
通常のフレックスタイム制では、1か月以内の清算期間で労働時間を調整します。
一方、複数月フレックスタイム制は、最長3か月の期間で労働時間を調整できる制度です。
たとえば、繁忙期と閑散期が明確な業種(例:製造業・サービス業・医療機関など)では、
「忙しい月は多く働き、閑散期にその分を減らす」という柔軟な働き方が可能になります。
2.制度導入の法的要件
複数月フレックスタイム制を導入するには、**労使協定(36協定とは別)**の締結が必要です。
この協定には、以下の内容を必ず記載します。
- 清算期間(最長3か月)
- 清算期間中の総労働時間
- 各月の標準労働時間の目安
- 労働時間の管理方法
- 届出先(所轄労働基準監督署)
💡 例
3か月清算期間の場合:
年間労働時間2,080時間 ÷ 12 × 3 ≒ 520時間を上限として設定。
3.制度導入のメリット・デメリット
✅ メリット
- 繁忙期・閑散期に応じて柔軟にシフトを調整できる
- 残業代の発生を抑え、コストを平準化できる
- 従業員にとっても「自由な働き方」がしやすくなる
⚠️ デメリット(注意点)
- 労働時間管理が煩雑になる
- 清算期間の中途退職・休職時に調整が難しい
- 期中の超過労働(いわゆる“オーバーワーク”)を見落とすと未払い残業のリスク
4.実務での運用ポイント
(1)労働時間の把握・管理
清算期間全体での労働時間を把握するため、
勤怠システム(クラウド・Excelでも可)で期間集計できる設定が必要です。
💡 ポイント:
月ごとの勤務時間を見ながら、清算期間の総時間が法定内に収まるようにチェックする。
(2)中途退職・休職時の取扱い
従業員が清算期間中に退職する場合、
実際の労働時間と予定労働時間との差を計算し、残業代や控除を精算する必要があります。
💡 事例
3か月清算期間中に2か月で退職した場合、
予定より多く働いていれば「追加の残業代を支払い」、
少なければ「賃金控除」は原則不可(労働基準法24条の賃金全額払い原則)。
(3)時間外・休日労働の判断
清算期間内で総時間が法定労働時間(週40時間)を超えた場合に時間外労働となります。
ただし、1日8時間超または1週40時間超での労働には、
「健康確保」の観点から残業代を支払うことが望ましいとされています。
(4)就業規則への明記
導入にあたっては、就業規則にも必ず次の内容を盛り込みましょう。
- 清算期間の設定
- 労働時間の決定方法
- 標準労働時間と始業終業の変更の仕組み
- 清算期間中の労働時間管理方法
5.【事例紹介】製造業A社の運用例
業種:製造業(従業員45名)
導入目的:繁忙期の残業削減と閑散期の有効活用
A社では、繁忙期(4~6月)は月180時間、閑散期(7~9月)は月140時間に設定。
清算期間を3か月とし、総労働時間を480時間に統一しました。
結果として、
- 残業代が前年より15%削減
- 有給取得率も改善(閑散期に取得を促進)
といった効果が見られました。
6.導入時の注意点まとめ
| チェック項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 労使協定の締結 | 清算期間・総労働時間・管理方法を明記 |
| 就業規則の改定 | フレックスタイム制を導入条項として追加 |
| 勤怠管理方法 | 清算期間ごとに労働時間を自動集計できる仕組み |
| 中途退職者対応 | 精算時の取扱いを明文化しておく |
| 過重労働防止 | 長時間労働のモニタリング体制を整備 |
7.まとめ:柔軟な働き方を実現するために
複数月フレックスタイム制は、繁閑差のある職場にとって有効な制度です。
一方で、勤怠管理や賃金精算など運用面の整備が不可欠。
導入前に「労使協定」「就業規則」「勤怠システム」の3点をしっかり整えることが成功のカギです。
【無料相談はこちら】
複数月フレックスタイム制の導入・労使協定作成・就業規則改定など、
実務対応に強い社会保険労務士がサポートします。お気軽にご相談ください。