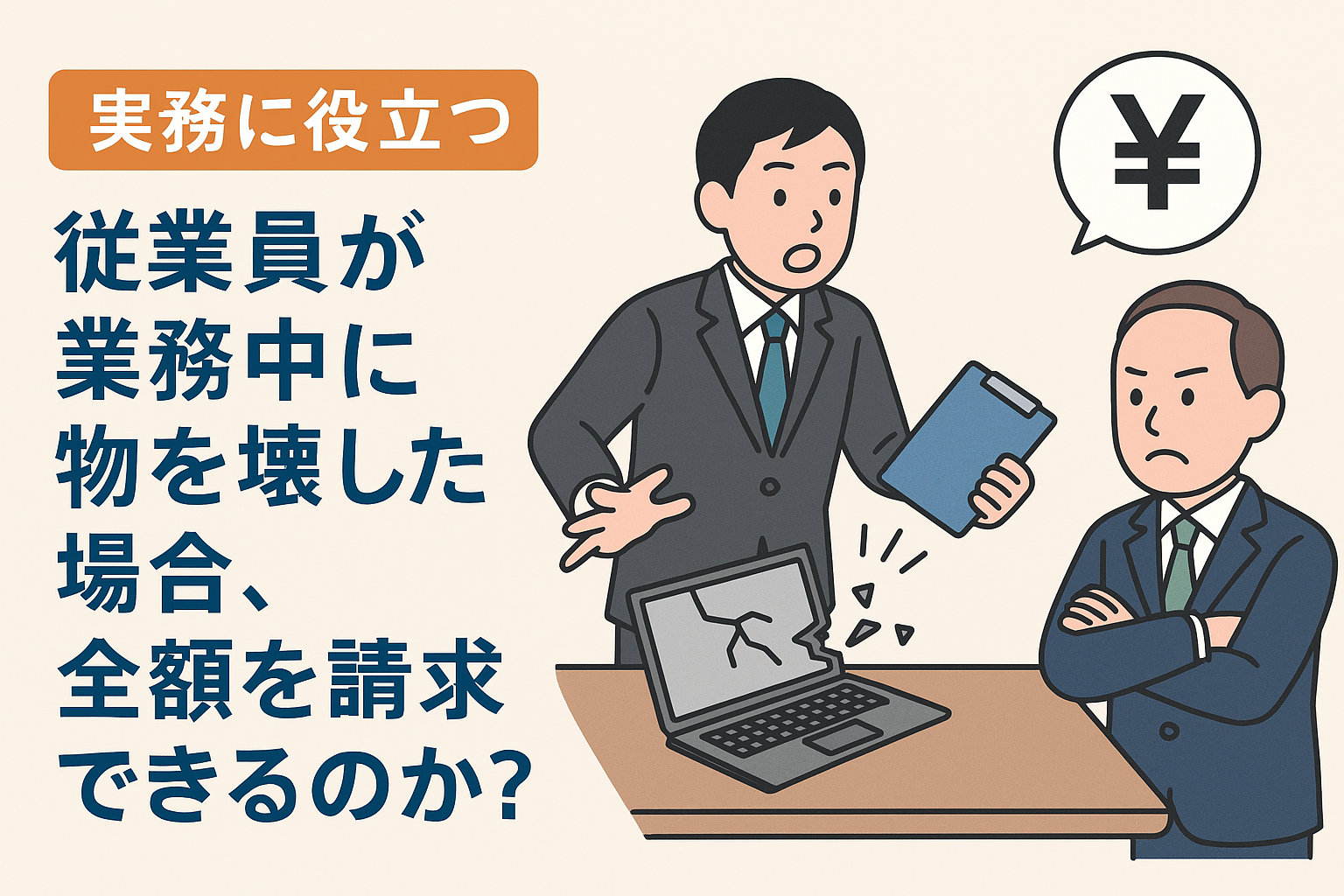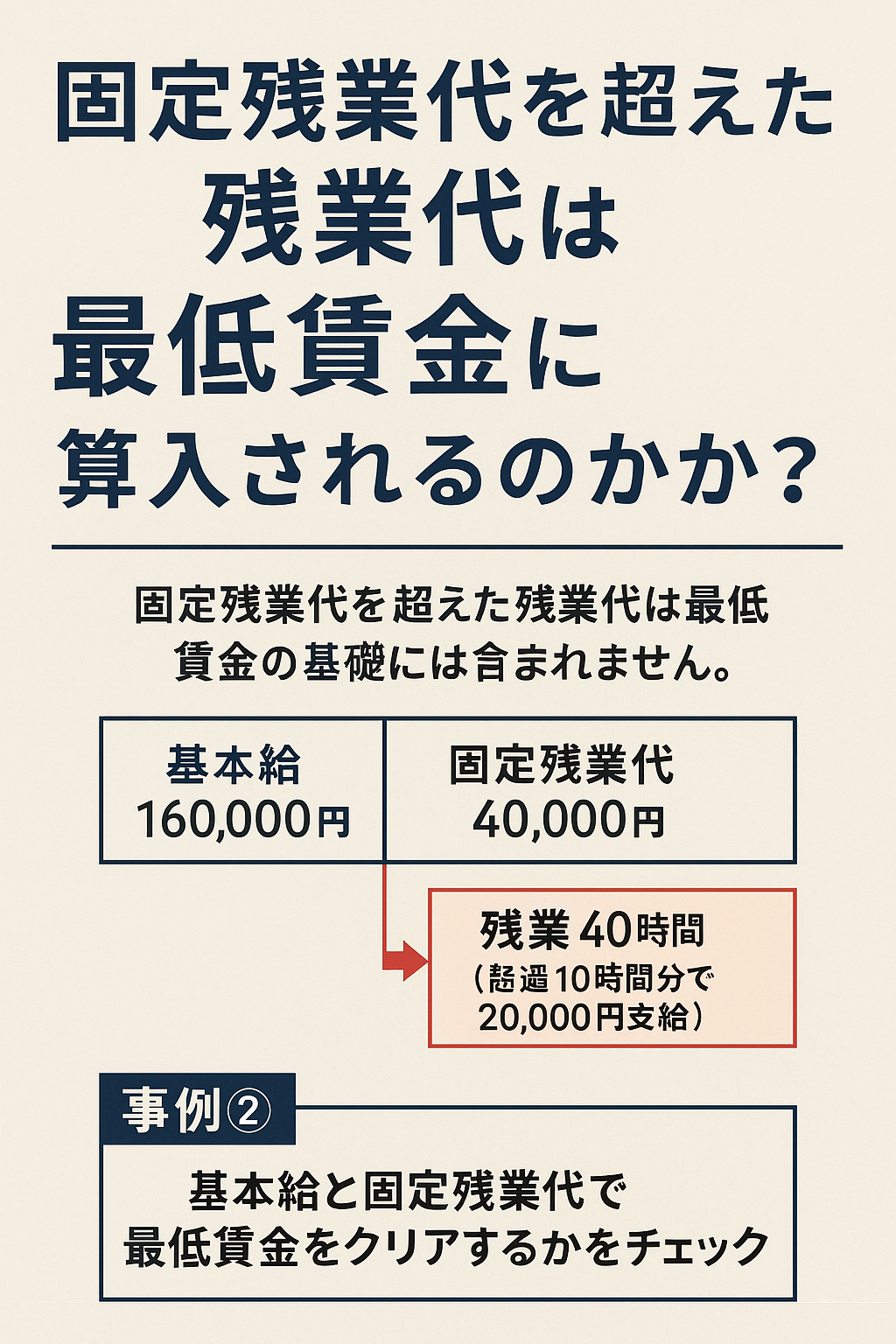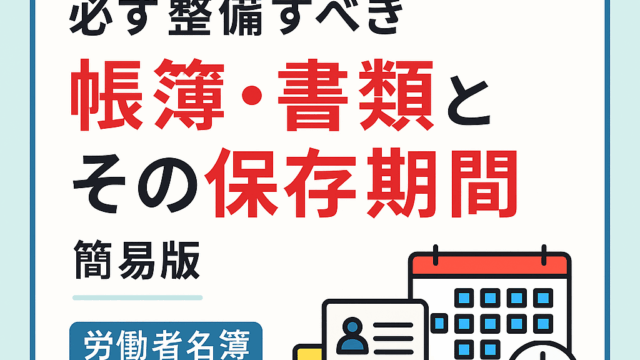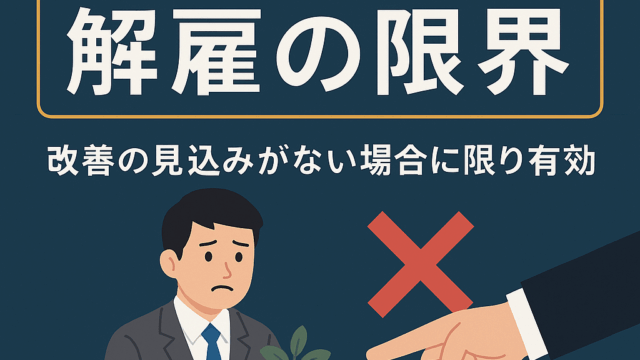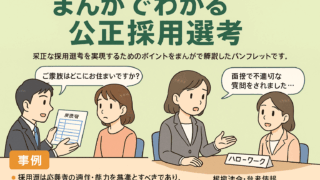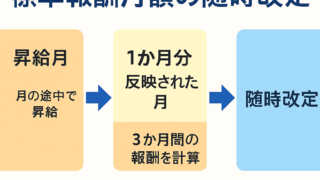こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
日常業務の中で、従業員が不注意により取引先の所有物を破損してしまうケースは少なくありません。
「この損害を全額、従業員に請求できるのか?」というご質問をいただくことがあります。
今回は、このテーマについて実務で役立つ法的ポイントを整理します。
使用者責任と求償権
民法第715条では「使用者責任」が定められており、従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合、原則として事業者が損害賠償責任を負うことになります。
そして、事業者が取引先へ損害賠償を行った場合、従業員に対して求償権を行使すること自体は可能です。
ただし「全額請求」はできない
最高裁判例(茨城石炭商事事件・昭和51年7月8日)では、
「損害の公平な分担」という見地から、従業員への求償は 信義則上相当な限度 に制限されると示されました。
判断基準として考慮されるのは以下の点です。
- 事業の性格・規模・施設の状況
- 従業員の業務内容や労働条件、勤務態度
- 加害行為の態様(不注意か、重大な過失かなど)
- 使用者側の予防策や保険加入の有無
- その他の事情(勤務年数、給与水準など)
同事件では、従業員が起こした事故に対して、損害額の4分の1までしか請求できないと判断されました。
実務での対応事例
ある運送会社で、従業員が業務中に取引先の機材を誤って破損しました。
修理費用は約200万円にのぼりましたが、会社は保険でカバーしきれない部分について従業員に請求しようと考えました。
しかし顧問弁護士と相談した結果、
- 業務上の過失であること
- 日常的にリスクが想定される業務であったこと
- 会社側の安全管理指導にも不十分な点があったこと
といった事情を踏まえ、最終的には従業員に対して20万円のみ負担を求める形で解決しました。
実務対応のポイント
- 全額請求はできない前提で考える
- 保険加入(賠償責任保険など)でリスクを分散する
- 就業規則や雇用契約において、損害賠償に関するルールを明確にしておく
- 過失の態様や従業員の状況を総合的に考慮して、請求範囲を決める
まとめ
従業員が業務中に起こした事故や破損については、原則として事業者が損害賠償責任を負います。
ただし、従業員に対して求償できる範囲は「信義則上相当な限度」であり、全額請求はできない点に注意が必要です。
リスク管理のためには、保険・就業規則・日常的な安全教育の三点セットが重要です。
✅ 自社の「損害賠償ルール」の見直しや就業規則の整備についてお悩みがあれば、ぜひご相談ください。