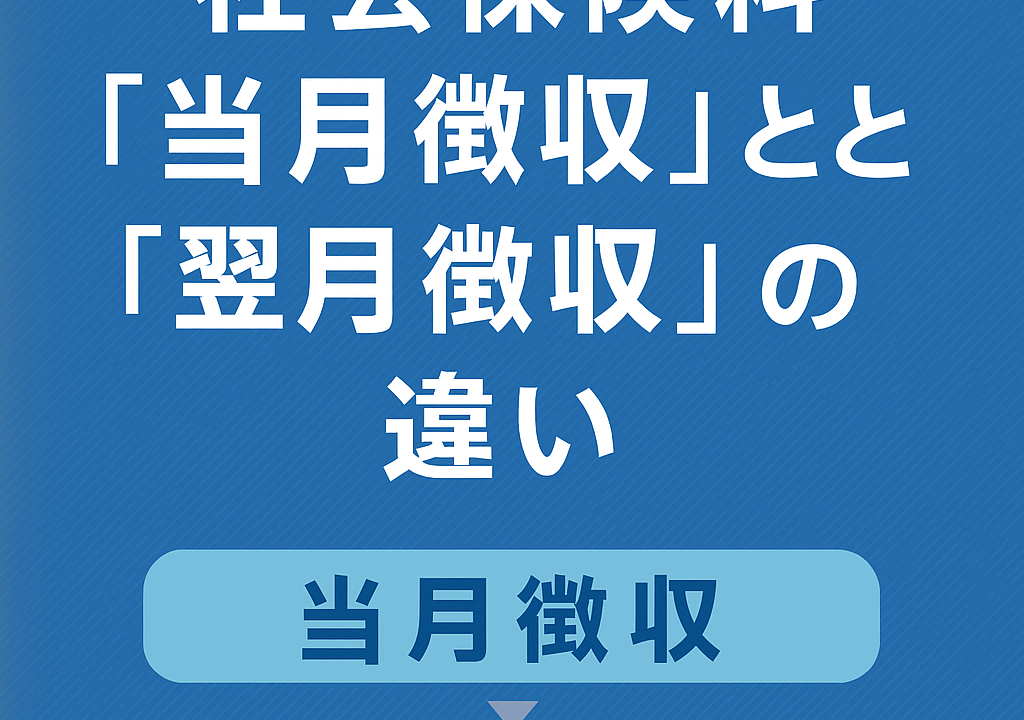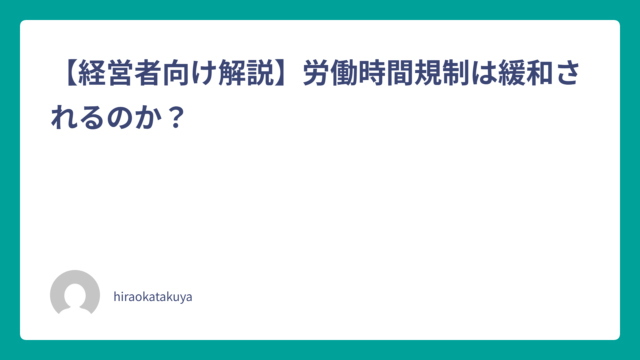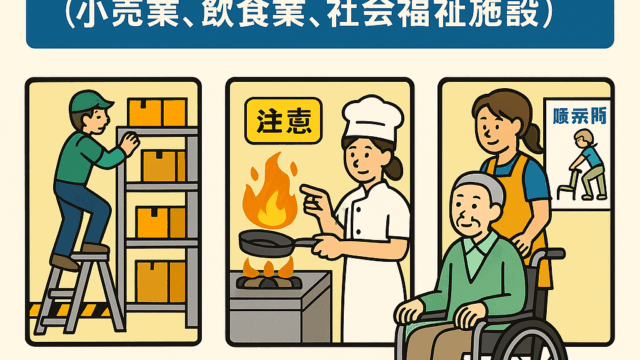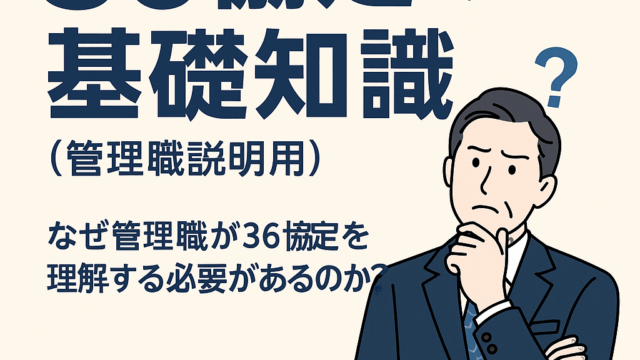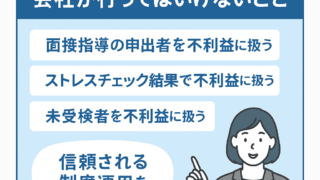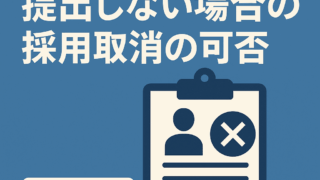こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
今回は、「社会保険料の徴収タイミング」をテーマに、月末締め翌15日支払の会社で「当月徴収」は可能なのか、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
1. 社会保険料の基本ルール
社会保険料は、労使折半で負担し、会社が給与から控除(天引き)して納付します。
その徴収タイミングには、次の2種類があります。
| 区分 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 翌月徴収 | 前月分の保険料を翌月給与で控除 | 最も一般的な方法 |
| 当月徴収 | 当月分の保険料を当月給与で控除 | 可能だが運用に注意が必要 |
多くの企業では「翌月徴収」を採用していますが、「当月徴収」も法律上は禁止されていません。
しかし、給与支払日や入社月の扱いによって、トラブルや誤徴収が起きやすくなります。
2. 月末締め翌月15日払いの場合の考え方
✅ 仕組みの整理
このスケジュールの会社では、
「○月分の給与」が翌月15日に支払われます。
| 対象月 | 支払日 | 社会保険料徴収例 |
|---|---|---|
| 1月分給与 | 2月15日 | 翌月徴収の場合:1月分保険料 当月徴収の場合:2月分保険料 |
このため、当月徴収に切り替えると、給与支給より先に保険料負担が発生することになります。
3. 入社月の注意点(ここが落とし穴)
たとえば、4月1日入社で、給与が「4月末締め→5月15日支払い」の場合を考えてみましょう。
▼ 当月徴収とした場合
- 入社月(4月分)の給与はまだ支給されていません。
- したがって、4月の給与から4月分の保険料を控除することができません。
- そのため、翌月(5月15日支払の給与)で、
4月分+5月分=2か月分の保険料をまとめて徴収する必要があります。
これを失念すると、納付漏れや二重控除の原因になります。
4. 実務上のリスクとおすすめの方法
| 観点 | 当月徴収 | 翌月徴収 |
|---|---|---|
| 入社月の取扱い | 複雑(2か月分徴収が発生) | シンプルで管理しやすい |
| 経理処理 | 月次調整が難しい | 決算処理も安定 |
| 従業員説明 | 混乱しやすい | 分かりやすい |
結論として、月末締め翌月15日支払の会社では「翌月徴収」が実務的におすすめです。
当月徴収を採用する場合は、
- 入社時の保険料徴収ルールを明文化する
- システムや給与計算ソフトの設定を確認する
- 従業員にも「2か月分控除になる可能性」を説明する
といった対策が必要です。
5. 【事例】入社時に保険料控除を忘れたケース
事例:4月1日入社・4月末締め・5月15日支給の会社
担当者が当月徴収を採用していたにもかかわらず、入社月(4月分)の保険料を5月給与で控除し忘れたため、
6月に2か月分を一度に控除することになり、従業員から「控除額が多い」と問い合わせがありました。
このように、入社月の処理漏れが最も多いトラブルです。
後から徴収しようとすると給与天引きの同意が必要になる場合もあり、慎重な対応が求められます。
6. 根拠法令
- 健康保険法 第167条(保険料の源泉控除)
事業主は、被保険者の負担すべき保険料を賃金から控除して納付しなければならない。 - 厚生年金保険法 第84条(保険料の源泉控除)
同様に、厚生年金保険料も給与からの控除が認められています。
ただし、控除のタイミング(当月か翌月か)は会社が決めてよいため、
実務上は「翌月徴収」が最も混乱を防ぐ運用といえます。
7. まとめ
| まとめポイント | 内容 |
|---|---|
| 当月徴収は可能 | 法的には問題なし |
| 入社月は注意 | 給与がないため2か月分徴収が必要 |
| 翌月徴収がおすすめ | 管理が簡単でトラブル防止になる |
📞 ご相談はこちら
社会保険料の徴収ルールや入社・退職月の控除処理など、
給与計算・社会保険実務に関するご相談も承っております。