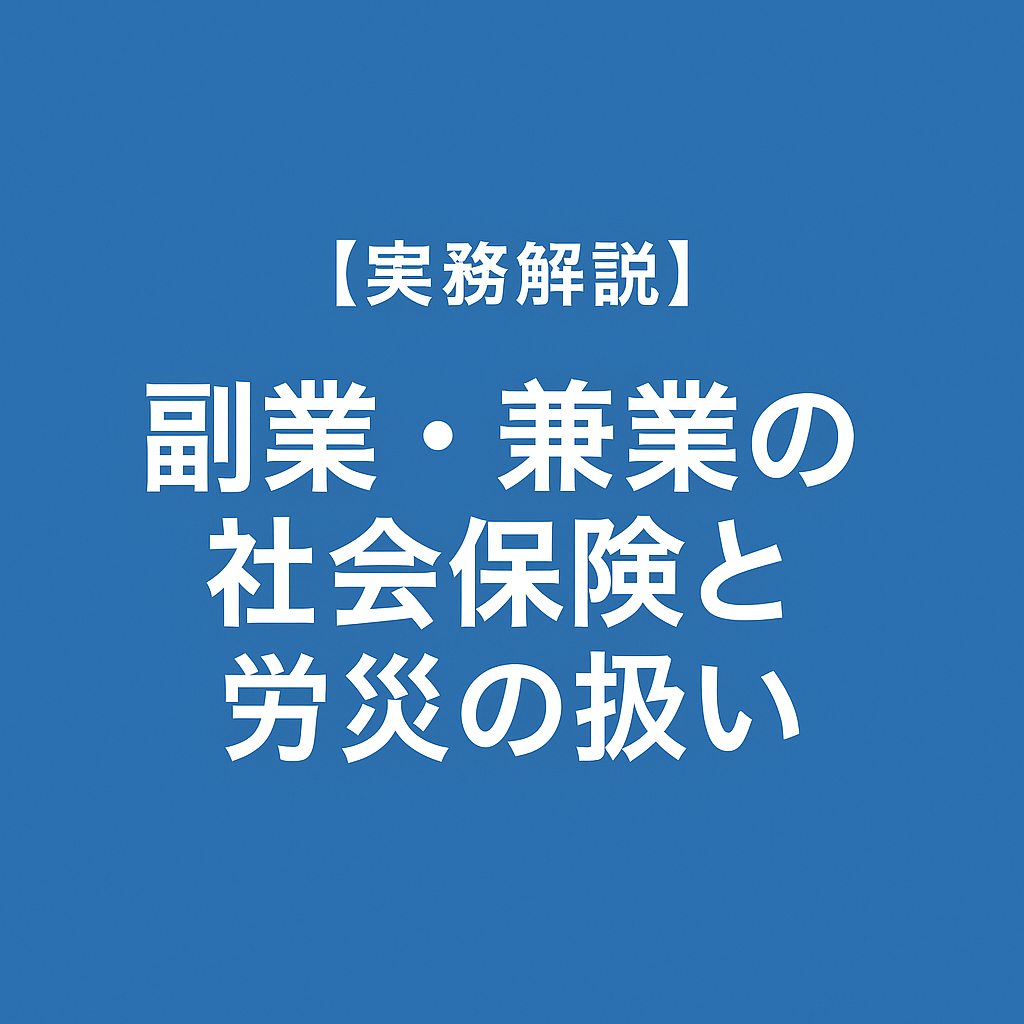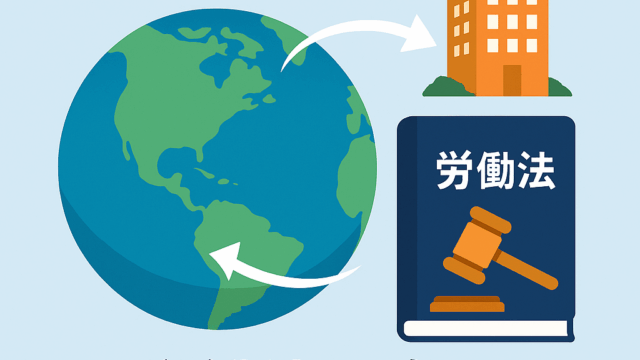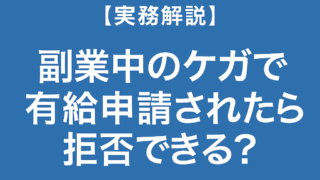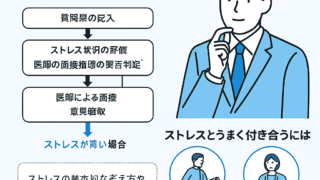近年、副業や兼業を認める企業が増加しています。働き方の多様化が進む中で、「副業している社員の社会保険・労災保険はどうなるのか?」という相談も増えています。
今回は、社会保険・雇用保険・労災保険それぞれの取扱いについて、実務に役立つ形で整理します。
1.社会保険(健康保険・厚生年金)の扱い
(1)基本の考え方
社会保険は、事業所ごとに加入要件を満たしているか で判断します。
複数の勤務先がある場合でも、「どこで何時間働いているか」により個別に判定します。
加入の主な要件
- 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上
- 雇用期間の見込みが2か月以上
- (短時間労働者の特例あり:週20時間以上、月額8.8万円以上など)
(2)複数勤務先での取り扱い
副業・兼業で複数の勤務先があり、それぞれの勤務先で加入要件を満たす場合は、2020年の法改正により「二以上事業所勤務者制度」が導入されています。
本人の選択により、いずれかの事業所を「主たる事業所」として指定し、報酬を合算して保険料を計算することができます。
💡 ポイント
「複数の勤務を合算して基準を満たす」ではなく、「それぞれの勤務先が要件を満たす」場合にのみ適用されます。
2.雇用保険の扱い
雇用保険は「主たる賃金を得ている雇用関係」において被保険者となります。
副業先でも雇用保険に加入するのは、原則として「主たる勤務先」だけです。
ただし、令和4年1月からは65歳以上の労働者を対象に、複数勤務先の労働時間を合算して加入要件を満たす場合、雇用保険の適用対象となる仕組みが導入されました。
高年齢者の多様な働き方に対応する制度です。
3.労災保険(複数事業労働者制度)
労災保険は、「労働者が勤務中に被った災害」を補償する制度です。
副業・兼業の場合でも、それぞれの勤務先で雇用契約を結んでいる限り、労災の対象となります。
(1)複数事業労働者制度とは
令和2年9月から導入された制度で、
複数の勤務先で働く人が労災に遭った場合、すべての勤務先の賃金を合算して給付額を算定できるようになりました。
(2)業務災害・通勤災害の取扱い
- 本業での勤務中にケガをした場合:本業の労災
- 副業中にケガをした場合:副業先の労災
- どちらも原因に関係する場合(過重労働等):複数業務要因災害として合算評価
💡 注意点
以前は「副業先でのけがは対象外」と誤解されることもありましたが、現在は勤務先ごとに補償され、必要に応じて賃金合算が行われます。
4.【事例】副業中にケガをしたケース
<事例>
本業A社(週4勤務)+ 副業B社(週2勤務)で働く従業員が、副業中に転倒して骨折しました。
本人はB社での勤務中でしたが、A社でも勤務を続けていたため、労災手続きに混乱が生じました。
<ポイント>
- ケガをした場所がB社の業務中であれば、B社の労災保険が適用されます。
- 給付額の算定にあたっては、A社とB社双方の賃金を合算して算定可能。
- 両社に対して「賃金証明書」の提出を依頼する必要があります。
5.実務対応のポイント
企業側の留意点
- 副業・兼業を認める場合は、就業規則や副業規程で条件・報告義務を明記する
- 労働時間の通算管理(過重労働防止・健康管理措置)を検討する
- 労災発生時には、複数勤務先の情報共有や証明書類の準備が必要
従業員側の留意点
- 副業を始める前に、所属会社の就業規則で副業可否を確認
- 労働時間・賃金・通勤経路を自己管理する(労災・安全配慮の観点からも重要)
- 副業・兼業先で事故が発生した場合、勤務状況や賃金情報を正確に報告すること
6.まとめ
副業・兼業が一般化する中で、社会保険・労災保険の取扱いも変化しています。
複数の勤務先での働き方に合わせた新しい制度が整備されつつあるため、「どの勤務先で加入しているか」「どの保険が適用されるか」を正しく理解しておくことが重要です。
💬 企業担当者の方へ
副業・兼業を導入する際には、就業規則・副業規程の整備と安全配慮の仕組みづくりが欠かせません。
制度設計や規程整備のサポートが必要な場合は、ぜひご相談ください。