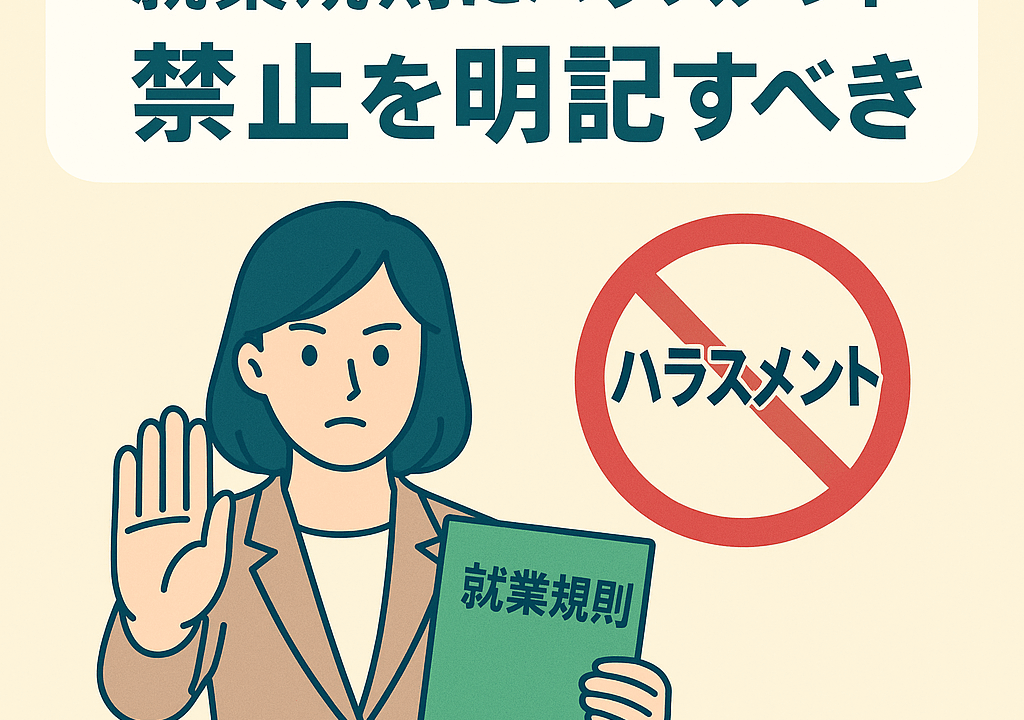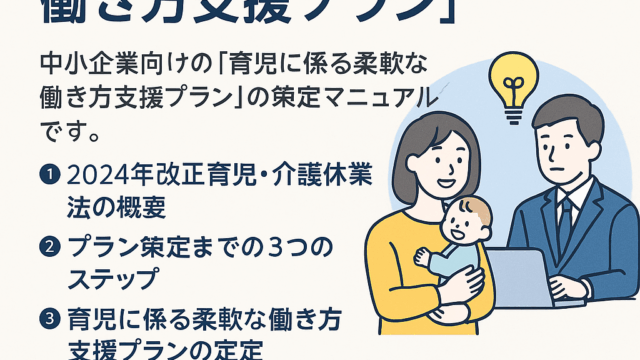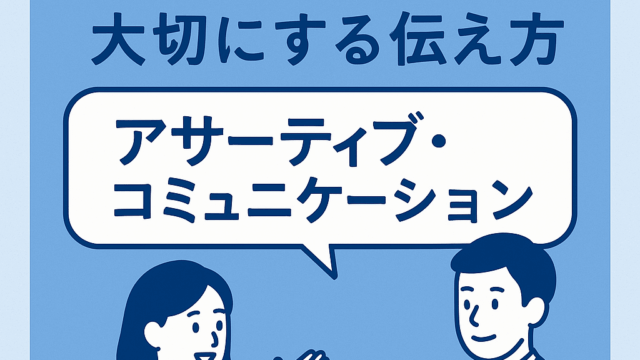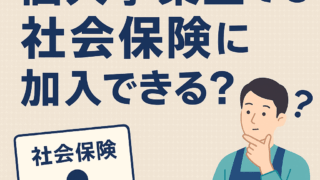職場でのパワハラ・セクハラなど、ハラスメント防止は企業にとって最も重要なコンプライアンス課題の一つです。
ところが、意外にも「就業規則にハラスメント禁止の記載がない」という企業が少なくありません。
実はこれ、法令上の問題につながる可能性があります。
本記事では、社会保険労務士の立場から「ハラスメント禁止の明記がなぜ必要か」「未記載のままだとどうなるのか」をわかりやすく解説します。
◆ ハラスメント禁止を明記しなければならない理由
令和2年に施行された「労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)」では、企業に対し次の対応が義務付けられています。
- ハラスメント防止の方針を明確にし、労働者に周知・啓発すること
- 相談体制(相談窓口)の整備
- 発生時の迅速かつ適切な対応
- 再発防止の措置
また、厚生労働省の指針(令和2年厚生労働省告示第5号・第6号など)では、
「就業規則その他服務規律において、ハラスメントを行ってはならない旨を定めること」
が求められています。
したがって、就業規則にハラスメント禁止の明記がない場合、法令遵守体制が不十分と判断されるおそれがあります。
◆ 懲戒処分との関係にも注意
懲戒処分は、「懲戒事由」と「懲戒の種類」を就業規則に定めていなければ行うことができません。
つまり、ハラスメント行為を懲戒処分の対象とするには、就業規則にその旨を明記しておく必要があります。
たとえば「パワーハラスメントその他の職場におけるハラスメント行為を行った場合は、懲戒処分の対象とする」と規定しておくことで、
処分の根拠が明確になり、トラブル防止につながります。
◆ 【実務事例】A社(製造業)のケース
ある製造業A社では、上司による叱責が常態化しており、部下から「パワハラではないか」との相談が寄せられました。
ところが、A社の就業規則には「ハラスメント禁止」も「懲戒事由としてのハラスメント」も記載がなく、
会社として処分の判断に迷う事態となりました。
最終的に、社外の社会保険労務士に相談し、
就業規則を改定して以下の条項を新設しました。
第◯条(ハラスメントの禁止)
労働者は、職務の遂行にあたり、他の労働者に対し、職務上必要かつ相当な範囲を超える言動を行ってはならない。第◯条(懲戒の事由)
労働者がハラスメント行為を行った場合、情状に応じて懲戒処分とすることがある。
改定後は、社内研修も実施し、相談対応マニュアルを整備。
現在では、早期相談・早期解決が可能な職場環境が整いました。
◆ まとめ:就業規則の整備は「予防策」
ハラスメント対策は「発生してからの対応」よりも、「発生を防ぐ仕組みづくり」が重要です。
そのためには、就業規則や服務規律にハラスメント禁止の明記を行い、懲戒との関係も整理しておくことが不可欠です。
✅ ハラスメント防止方針の周知
✅ 就業規則での禁止・懲戒規定の明確化
✅ 社内研修・相談窓口の整備
これらを整えることで、従業員が安心して働ける職場環境を実現できます。
根拠法令・参考情報
- 令和2年厚生労働省告示第6号(職場におけるパワーハラスメント防止指針)
- 令和2年厚生労働省告示第5号(セクシュアルハラスメント防止指針)
- 平成28年厚生労働省告示第312号(妊娠・出産等に関するハラスメント防止指針)
👇 無料相談・お問い合わせはこちら
ハラスメント防止規程の整備や、就業規則の改定支援については、専門の社会保険労務士がサポートいたします。
お気軽にご相談ください。