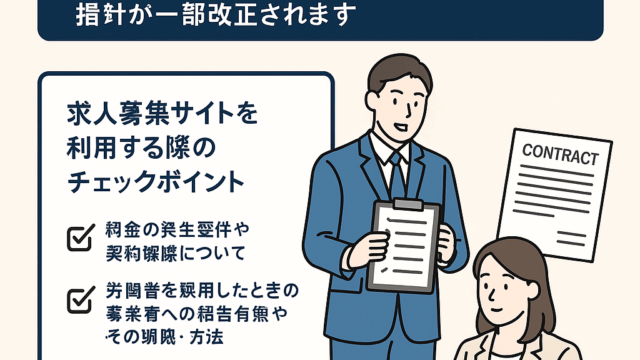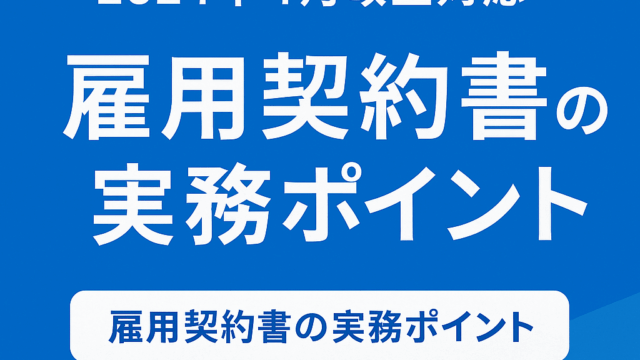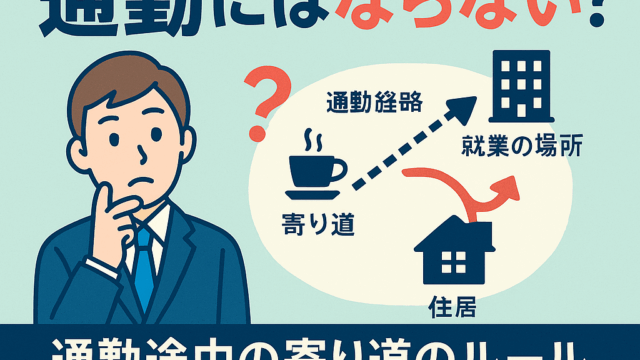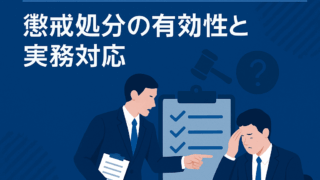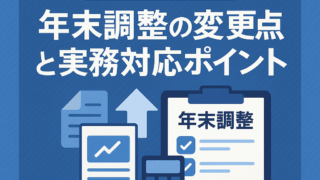「従業員が顧客リストを外に持ち出した」「取引先に機密資料を送っていた」「社員がSNSで社内の情報を書いてしまった」——
こういった相談は実際によくあります。
秘密情報の持ち出し・漏えいは、
- 会社の信用
- 金銭的な損害
- 取引先との関係
- そして代表者個人の責任問題
に直結します。
一方で、すぐに懲戒解雇すればいいという話でもありません。
逆に会社側がやりすぎると「不当な処分だ」と争われ、負けてしまうこともあります。
このページでは、会社がまず押さえるべき5つのポイントをわかりやすく整理します。
① まず押さえるべき全体フロー
従業員による情報持ち出し・漏えいが疑われたら、会社は次の順で考えます。
- それは「何の情報」か?(秘密情報なのか、個人情報なのか、内部告発なのか)
- どういう形で持ち出し/漏えいされたのか?
- 会社としてどの対応が可能か?
- 懲戒処分
- 損害賠償請求
- 差止請求(使うな・返せ)など
- 立証できる証拠はあるか?
- そもそも再発を防げる体制になっていたか?
この順番を外すと、感情的な対応になってしまい、後で会社側が不利になります。
② 「秘密情報」とは何か(用語の整理)
一口に「社外秘」といっても、実は性質の異なる情報が複数あります。ここを間違えると、正しい手段が取れません。
1. 会社の秘密情報(広い意味)
本ガイドでは「会社が外に出ることを想定していない情報」を広く“秘密情報”と呼びます。
例:
- 顧客リスト・単価・仕入先条件
- 事業計画・販売戦略
- 技術資料・ノウハウ
- 社内の人事評価・給与情報
- ハラスメントの相談内容
- 不正経理(粉飾など)に関する内部情報 など
ポイント:
就業規則に書いていなくても、従業員は在職中「会社の秘密を勝手に外に出さない義務」を負うと考えられています(信義則上の守秘義務)。
2.「営業秘密」(不正競争防止法)
不正競争防止法では「営業秘密」という特別なカテゴリーがあります。
営業秘密に当たると、損害賠償だけでなく“差止”や“刑事罰”まで視野に入ります。
営業秘密と認められるには、次の3つが必要です。
- 秘密として管理されている(アクセス制限・秘マーク等がある)
- 事業に有用(売上・生産・ノウハウなどに役立つ)
- 公然と知られていない(社外に出回っていない)
例:
- 製造工程の詳細マニュアル
- 新商品ラインナップと価格戦略
- 3年計画の生産・販売シミュレーション など
※この「営業秘密」に当たるかどうかで、会社が取り得る手段は大きく変わります。
3.「個人情報」
個人情報保護法上の「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報のことです(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、社員の人事情報、顧客データなど)。
注意点:
- 漏えいすると、会社は “従業員本人・顧客本人” から損害賠償を請求される恐れがあります。
- 個人情報保護委員会への報告、本人への通知、社外公表(プレス対応)が必要になる場合があります。
- 場合によっては会社の信用問題=取引停止リスクに直結します。
「顧客リストを勝手に持ち出した」ケースは、ここに該当することが多いです。
4.「通報対象事実」(公益通報)
会社の法令違反(労働基準法違反、個人情報保護法違反、粉飾決算など)を内部告発・通報するために情報を外に持ち出すことがあります。
これは公益通報者保護法の領域になります。
一定の条件を満たす通報は“保護”され、それを理由にした解雇・降格・減給などは無効とされる可能性があります。
つまり、
- 「会社の違法な残業隠しを労基署に通報した」
- 「ハラスメントの現場記録を行政に相談した」
といった行為は、安易に“情報漏えい=懲戒解雇”としてはいけません。
ここを誤ると会社が逆に違法な不利益取扱いをした扱いになります。
③ どういう行為が「持ち出し・漏えい」にあたるのか?
典型パターンは次の3つです。
- 【持ち出し+漏えい】
例:売上計画資料をUSBにコピーして自宅に持ち帰り、第三者企業に渡した - 【持ち出しなし+漏えい】
例:会社PCから顧客リストを他社にメール送信した/SNSに社内の内部資料を掲載した
(データ自体は会社のPC内にあったが、社外へ送った) - 【持ち出しのみ(漏えいは未遂)】
例:退職前に設計データ一式を個人用ストレージに保存して持ち帰ったが、外部利用は未確認
さらに、
- 故意(売るつもりでコピーした)
- 過失(カバンごと紛失、誤送信)
も評価で変わります。
悪質性・目的・会社への実害が、懲戒の重さを左右します。
④ 会社が取り得る主な対応
1. 懲戒処分(注意・減給・出勤停止・懲戒解雇など)
懲戒処分が有効と判断されるには、次の観点が見られます。
- 情報の重要性・機密性
- 漏えいの目的(背信的か、自己防衛的か)
- 会社に発生した損害やリスクの大きさ
- 同じことを繰り返しているか
- 就業規則に「秘密保持義務違反は懲戒対象」と明記してあるか
懲戒処分が有効とされた事例
ケースA:3か年の極秘経営計画を持ち出し・漏えいした例
経営再建のための極秘計画(生産機種や販売見込み、人員制度の見直しなど)を外部に持ち出し、組合活動の材料として流出させた従業員に対し、懲戒解雇を有効とした裁判例があります(東京高裁 昭和55年2月18日)。
→ 会社の中枢戦略レベルの情報であり、背信性が極めて高いと評価されました。
ケースB:退職直前に技術資料を大量に持ち出した例
退職前に設計資料・フロッピーディスク等を大量に持ち出した従業員について、懲戒解雇を有効とした裁判例があります(大阪地裁 平成13年3月23日)。
→ 「会社に損害を与える、または自分や第三者の利益のために使う」という背信的意図があると判断されました。
懲戒処分が無効とされた事例
ケースC:弁護士への相談のための持ち出し
自分が受けているいじめ・差別的扱いについて相談する目的で、従業員が人事資料などを弁護士に渡したケースでは、懲戒解雇は無効とされました(東京地裁 平成15年9月17日)。
→ 自己の権利救済のために、守秘義務のある弁護士にだけ見せた行為は、一律に「重大な漏えい」とまでは言えない、と判断されています。
ケースD:顧客リストを他社に送信したが実害なし
顧客リストを提携先にメールで送った従業員に懲戒解雇を出したが、裁判所は「売上拡大の意図はあった」「実害が出ていない」などを重視し、懲戒解雇は重すぎる=無効と判断しました(東京地裁 平成24年8月28日)。
→「いきなり解雇」は、かなりハードルが高いということです。
重要ポイント
懲戒解雇は「最後のカード」です。
いきなり最重処分にいくと、裁判で負ける可能性が高くなります。
2. 損害賠償請求・差止請求
- 従業員に対して
秘密保持義務違反(在職中の信義則上の義務違反)として、損害賠償請求が可能と考えられます。
また、営業秘密であれば「その情報を使うな・返還しろ・破棄しろ」という差止請求も視野に入ります。 - 情報を受け取った第三者に対して
営業秘密であれば、その第三者に対しても「使うな・返せ」と主張できますし、刑事責任の追及も可能な場面があります。
ただし、実務では「損害額の証明」がハードルです。
どれだけの損害が出たのか、売上はいくら失われたのかを数字で示す必要があり、裁判でもそこが争点になります。
※営業秘密の場合は「持ち出した人が得た利益=会社の損害」と推定される仕組みがあり、証明がしやすくなります。これは大きな武器です。
3. 人事上の一時的措置
- アクセス権の遮断(システム権限の停止)
- 一時的な自宅待機命令
- 配置転換・職務変更 など
漏えいリスクの拡大を止めるための一時対応は、すぐに検討して構いません。
ただし、不利益取り扱いと評価されないよう、理由と必要性は記録に残しておきましょう。
⑤ どんな証拠を集めるべきか(後で必ず役に立ちます)
会社が「正当な対応だった」と説明するためには、証拠がすべてです。
裁判所は“事実”ではなく“事実を示す証拠”を見ます。
最低限おさえたい証拠は次のとおりです。
- いつ・誰が・どの情報にアクセスしたか(アクセスログ)
- どのファイルをコピーしたか/どのメールを送ったか(送信履歴)
- 外部デバイス(USB等)への持ち出し記録
- カードキー履歴・監視カメラ記録・タイムカードの動き
- 本人へのヒアリングメモ(日時・誰が同席・本人の説明)
- 再発防止の指示、注意喚起を行った事実(書面や議事録)
「言いました/聞いてません」にならないよう、記録を残しておくことが重要です。
⑥ よくある相談パターン(事例)
事例1:営業スタッフが顧客リストを持って辞めた
退職前の社員が、顧客リストと単価表をUSBにコピーし、そのまま競合に転職したケース。
会社が取るべきだった対応は:
- リストが「営業秘密」として管理されていたことを示す(アクセス制限、社外秘マーク等)
- 持ち出しの事実を記録(ログ・監視カメラなど)
- 退職時点でアカウント停止・PC回収
- 競合先へ「その情報を使わない・返還する」旨の警告文書送付
- 本人には懲戒処分や損害賠償請求も視野
→ ポイント:就業規則・誓約書で「営業秘密の持出禁止」「退職後も秘密保持義務あり」をきちんと明文化しておくこと。
事例2:ミスで個人情報を外部にメール送信
事務担当者が取引先に請求データを送るつもりで、別の添付ファイル(従業員のマイナンバーを含むファイル)を誤送信してしまった。
会社が必要になる対応は:
- 直ちに相手先へ削除要請・回収要請
- 送付先がさらに転送していないかの確認
- 漏えい対象者(従業員等)への説明体制の準備
- 個人情報保護委員会への報告や公表が必要かの検討
- 再発防止策(送信前チェックの複数確認ルール等)の明文化
→ ポイント:過失でも会社の法的・信用上のリスクは大きい。
「うっかりでした」で済ませない。
事例3:ハラスメントの証拠を外部の弁護士に持ち出して相談
従業員が、上司からのパワハラの記録や人事評価メモをコピーし、弁護士に相談した。会社は「情報持ち出しだ」として懲戒解雇。
このケースでは、裁判所が懲戒解雇を無効にした例があります。
理由は、目的が“自分の権利の救済”であり、弁護士には守秘義務があるからです。
→ ポイント:公益性・防衛目的の持ち出し(内部告発含む)は、一律に「悪質な漏えい」とは扱えません。慎重に。
⑦ 会社が今すぐやっておくべき予防策(超重要)
- 就業規則・雇用契約書・誓約書に
「秘密情報の定義」「持出禁止」「在職中・退職後の守秘義務」「違反時の懲戒」を明記する - 営業秘密にしたい情報は、ちゃんと“営業秘密扱い”にする
(アクセス権限を限定、ファイルに「社外秘」フッター、保管ルールを明文化) - 退職予定者のアカウントや媒体持ち出しを事前にチェックする
- 個人情報の送信・持ち出しルール(USB禁止・外部メール禁止・二重チェック)を作る
- 万一のときの初動フローを決めておく
(誰が調査する?誰がプレス・取引先対応をする?)
これらはすべて「事が起きてから作る」のでは遅い内容です。
まとめ
- 秘密情報の持ち出し・漏えいは、会社の経営そのものに直結する重大リスクです。
- ただし“すぐ懲戒解雇”は危険で、逆に会社が不利になることもあります。
- まずは「どんな情報か」「どんな目的で外に出たか」「会社にどんな影響があるか」を丁寧に整理・記録してください。
- そして、就業規則と情報管理ルールの整備は“事前対策”として必須です。
「うちの会社のルールはこのままで大丈夫?」
「就業規則に何を入れておくべき?」
「今回のケース、懲戒まで踏み込んでいい?」
といったご相談は、個別の状況(業種・社内体制・過去の運用)によって結論が変わります。
下記よりお気軽にお問い合わせください。(初回相談無料です)