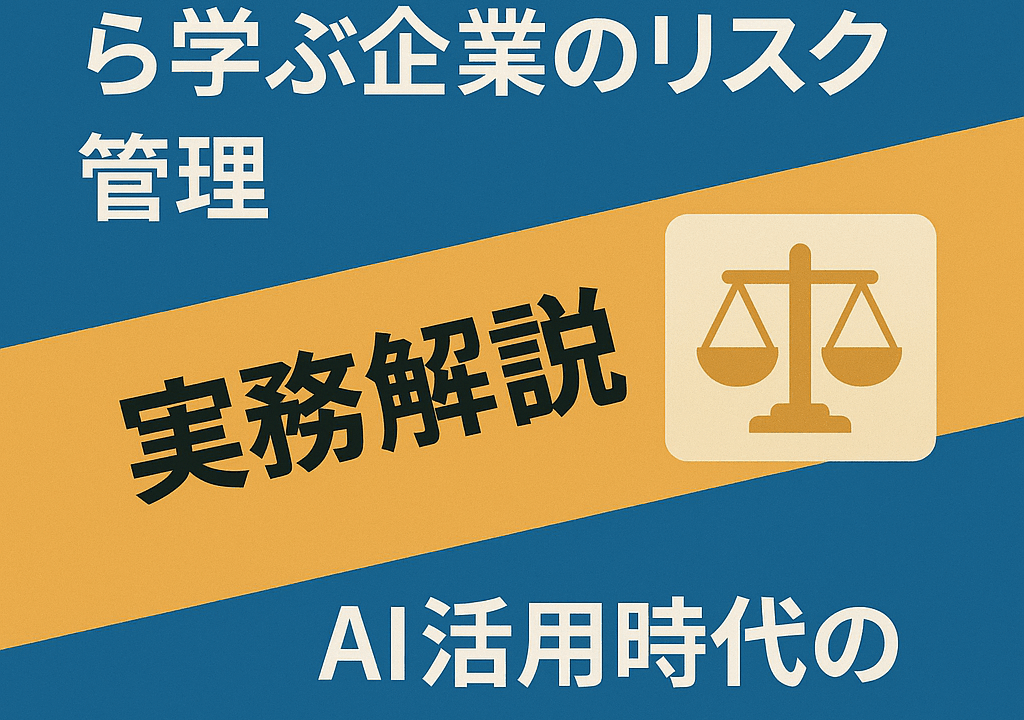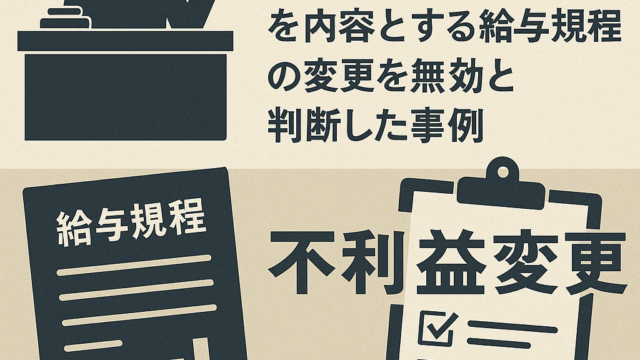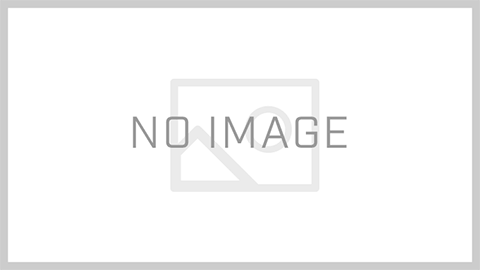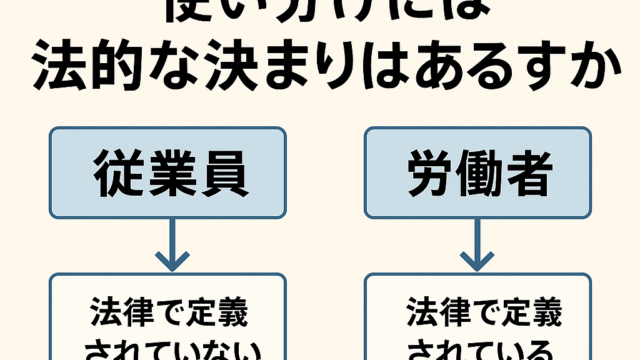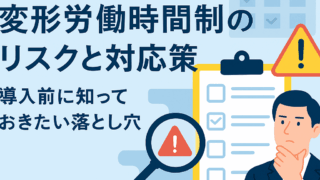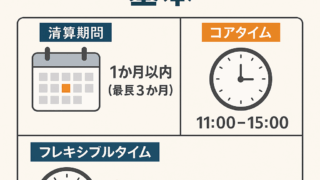こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
賃金をめぐるトラブルは、労務管理の中でも特に訴訟リスクが高い分野です。
近年はAIによる業務効率化が進み、成果や評価の仕組みが複雑になる中で、賃金ルールの不備が直ちに法的リスクに直結します。
今回は、判例を通じて「賃金に関するリスク」と「実務で押さえるべきポイント」を解説します。
1. 判例から見る賃金トラブルの典型例
事例①:残業代請求が認められたケース
ある企業では「管理職だから残業代は支払わない」としていました。
しかし実態としては人事権や経営上の裁量がなく、通常の社員と同様の勤務状況だったため、裁判所は「管理監督者に該当しない」と判断し、残業代の支払いを命じました。
👉 実務ポイント:役職名だけで「管理監督者」と扱うのは危険。実態に即した判断が必要。
事例②:固定残業代が無効とされたケース
営業職に対して「固定残業代」を支給していた企業がありました。
しかし、就業規則や契約書に「基本給と残業代の内訳」が明確に記載されていなかったため、固定残業代部分が無効とされ、追加で残業代を支払うことになりました。
👉 実務ポイント:固定残業代制度を導入する際は、「内訳の明示」「残業時間との整合性」が必須。
事例③:賞与の不支給をめぐる争い
ある企業では、業績不振を理由に一方的に賞与を不支給としました。
裁判所は「就業規則や賃金規程に賞与支給の基準が明確に定められていない」として、不支給は無効と判断。結果的に、労働者側の請求が認められました。
👉 実務ポイント:賞与や手当は「会社の裁量」としても、支給基準や算定方法を明記することが必要。
2. 実務担当者のチェックリスト
- 管理職の労働実態は「管理監督者」の定義に合致しているか?
- 固定残業代を導入している場合、契約書や規程で明確に内訳を示しているか?
- 賞与・手当の支給条件や不支給の要件を明確にしているか?
- AIやシステムで算定している給与データに誤りがないか、定期的に検証しているか?
3. まとめ
賃金に関する判例は、いずれも「制度のあいまいさ」がトラブルの原因となっています。
特にAI活用が進む現在は、制度の透明性と説明可能性が一層重要です。
企業としては、就業規則や賃金規程を整備するだけでなく、従業員への説明責任を果たすことが、労務トラブルを防ぐ最大のポイントです。
📌 無料相談受付中
「固定残業代制度を導入しているがリスクが不安」
「賞与や手当の規程を見直したい」
といった具体的なご相談は、ぜひ当事務所へお気軽にご連絡ください。