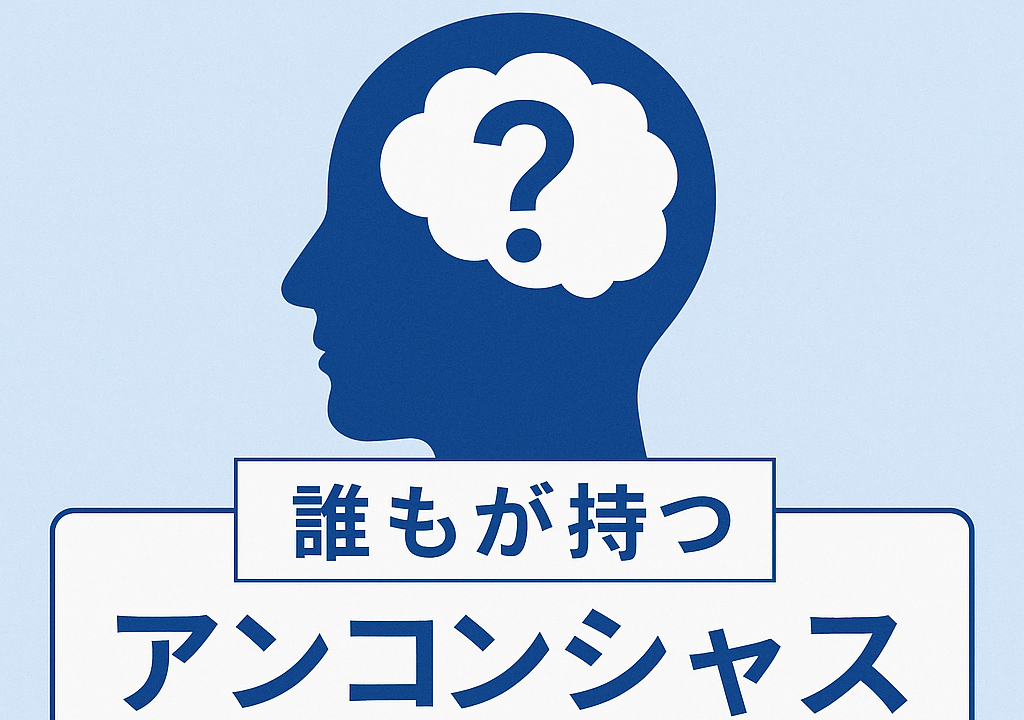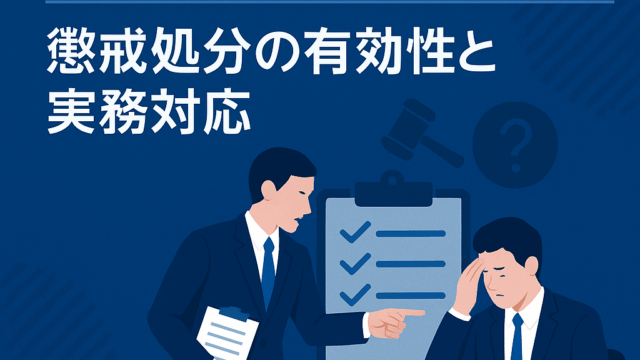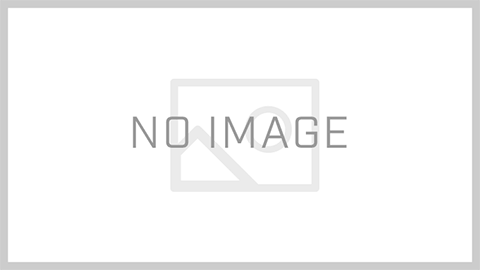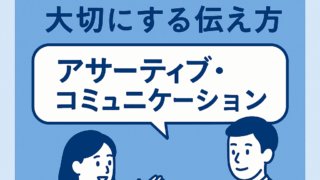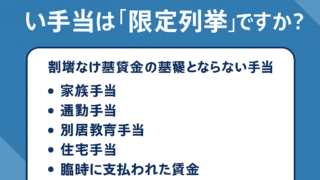〜誰もが持つアンコンシャス・バイアスを知ろう〜
1.アンコンシャス・バイアスとは?
「アンコンシャス・バイアス(Unconscious Bias)」とは、
これまでの経験や環境によって形成される、無意識の思い込みや先入観のことです。
たとえば、
- 「男性は力仕事が得意」
- 「若い人はデジタルに強い」
- 「子育ては女性が中心に行うべき」
こうした言葉を何気なく口にしたことはありませんか?
これらは悪意がなくても、「無意識の思い込み」によって他者を枠にはめてしまう発言です。
💡アンコンシャス・バイアスは誰にでもあります。
大切なのは、気づかないうちに人を傷つけたり、判断を誤ったりしないように「自覚すること」です。
2.チェックしてみよう!こんな思い込み、ありませんか?
次のうち、いくつ当てはまりますか?
(当てはまること自体が悪いのではなく、「そう感じることがある」と気づくことが第一歩です。)
- 共働きでも、男性は仕事を優先すべきだと思う
- PTAや地域活動は女性の方が向いている
- 男の子は青、女の子はピンクが好きだと思う
- 若手社員に「最近の若者は…」と言ってしまう
- 会議で発言しない人は、やる気がないと感じる
- 新しいメンバーを選ぶとき、つい「自分と似たタイプ」を選んでしまう
このような思い込みは、「差別」ではなく、誰もが持つ自然な心理反応です。
ただし、そのまま放置すると、ハラスメントや不公平な評価、チーム内の分断につながることもあります。
3.代表的なアンコンシャス・バイアスと事例
| 種類 | 内容 | 職場での具体例 |
|---|---|---|
| ステレオタイプ | 年齢・性別・国籍などの属性で相手を判断してしまう | 「若手だからSNSは得意でしょ」 「女性は感情的だから管理職は難しい」 |
| 確証バイアス | 自分の考えを裏付ける情報だけを集め、反対の情報を無視する | 「あの人はミスが多い」と思い込むと、その印象ばかり探してしまう |
| ハロー効果 | 一つの特徴が全体評価に影響してしまう | 「東大卒だから仕事も完璧だろう」と過度に期待する |
| 集団同調性バイアス | 周囲の意見に合わせてしまう心理 | 「みんな賛成しているから、自分も賛成しておこう」 |
4.【事例①】善意から生まれた“思い込み”
ある上司が、育児中の女性社員にこう声をかけました。
「子育てが大変だろうから、無理しないでいいよ。」
一見、思いやりのある言葉ですが、
本人は「仕事を任せてもらえない」「キャリアを止められた」と感じていました。
💡ポイント:
「相手の立場に立って考える」ことと「相手の意見を聞かずに決めつける」ことは違います。
“配慮のつもり”が“制限”にならないように注意しましょう。
5.【事例②】会議で発言しない部下への誤解
チーム会議で発言が少ない部下に対して、上司が「やる気がない」と判断。
しかし実際には、「上司の意見を尊重して黙っていた」だけでした。
💡ポイント:
発言量=意欲とは限りません。
背景や性格、文化的要素も考慮する必要があります。
6.アンコンシャス・バイアスに気づく3つのアクション
① 「自分にもある」と気づく
「私は偏見なんてない」と思うほど、無意識の思い込みに気づきにくくなります。
まずは、自分も例外ではないと認識しましょう。
② 多様な視点に触れる
職場内外で、年齢・性別・国籍・働き方などが異なる人と意見交換をしてみましょう。
異なる価値観に触れることで、自分の「思考のクセ」に気づけます。
③ 判断基準を明確にする
人事評価・面接・役割分担などを行うときは、感覚や印象に頼らず、「事前に定めた基準」をもとに判断することが重要です。
7.まとめ:無意識を「意識」に変えることから始めよう
アンコンシャス・バイアスを完全に無くすことはできません。
しかし、「自分の思考にバイアスがあるかもしれない」と一度立ち止まることで、
職場のコミュニケーションは大きく変わります。
💡意識することが、思いやりの第一歩です。
📞 組織風土改善・ハラスメント防止研修のご相談はこちら
ひらおか社会保険労務士事務所では、
アンコンシャス・バイアスやハラスメント防止をテーマにした従業員研修・管理職研修を実施しています。
多様な人が活躍できる職場づくりをサポートします。