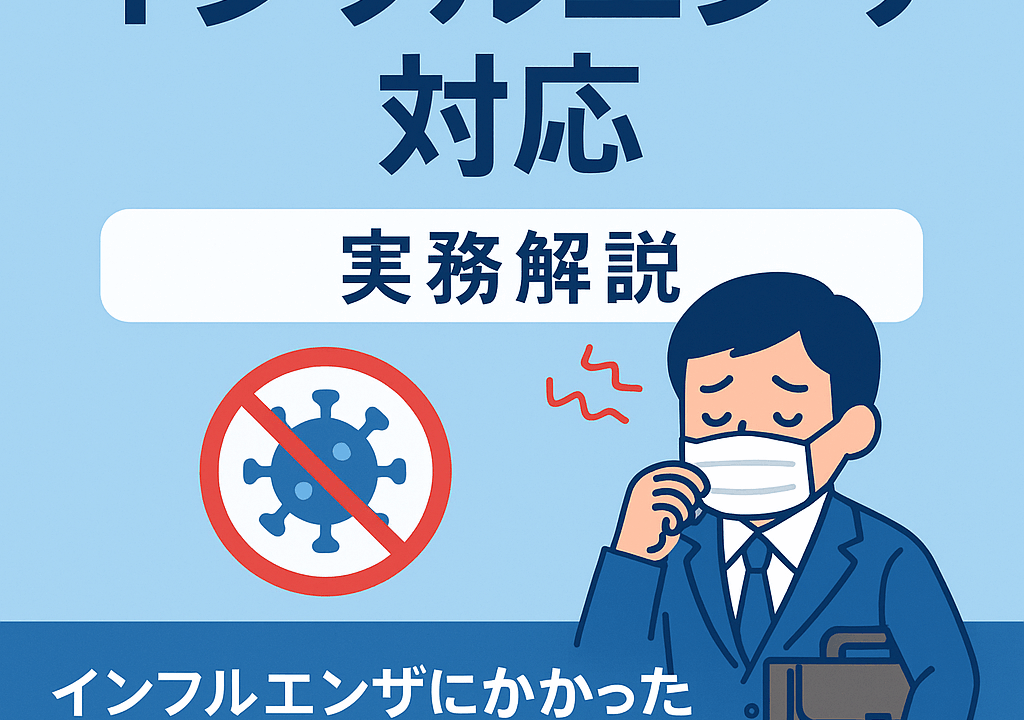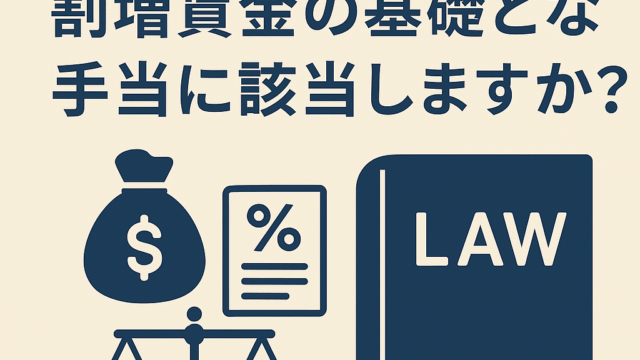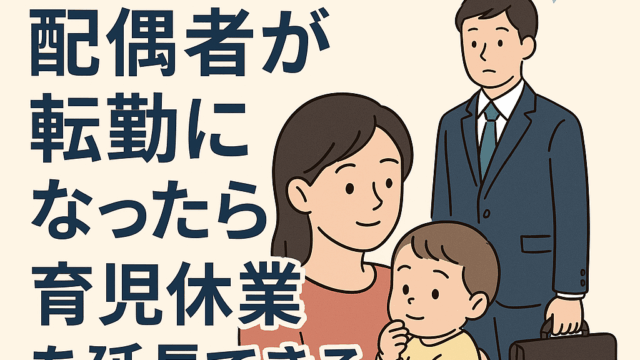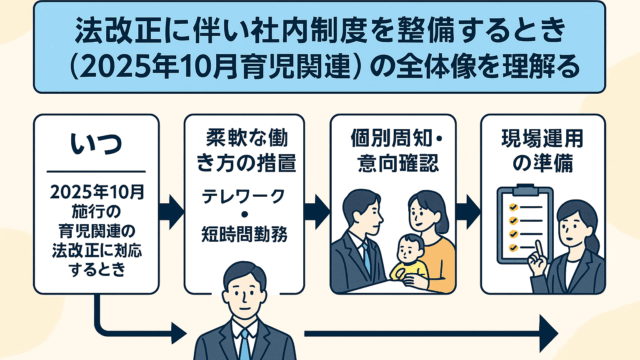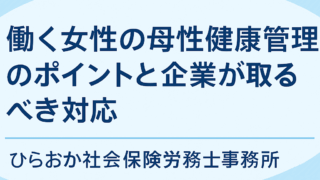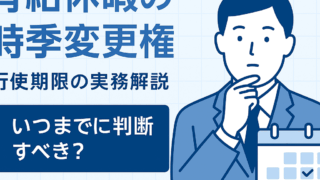冬の時期になると、インフルエンザによる欠勤や感染拡大への対応が課題になります。
「本人は元気だから出社したいと言っているが、周りへの感染が心配…」
このような場合、会社は出社を拒むことができるのでしょうか?
本記事では、法的な根拠と実務上の判断ポイントをわかりやすく解説します。
1.会社は出社を拒むことができるのか?
結論から言うと、インフルエンザにかかった従業員が出社を希望しても、会社は出社を拒むことができます。
従業員には「会社が求めるときに労務を提供する義務」がありますが、
会社が求めていない場合に「働かせてほしい」と主張する就労請求権は法律上認められていません。
したがって、会社が合理的な理由をもって休業を命じた場合、従業員はその命令に従う必要があります。
2.法的な根拠
労働契約法第5条(安全配慮義務)
使用者は、労働者が安全かつ健康に就業できるように配慮しなければならない。
インフルエンザは感染力が強く、職場内でのクラスター発生のリスクがあります。
そのため、他の従業員の安全を確保するための出社制限は「合理的な命令」と評価される可能性が高いです。
民法第623条(雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に労務を提供し、相手方がこれに対して報酬を支払う契約である。
つまり、会社が受け入れない以上、労務提供の義務は発生しません。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。
会社の判断で休ませる場合、その理由が「会社都合」であれば、休業手当の支払いが必要となります。
3.法律上の「就業禁止」との違い
学校保健安全法では、インフルエンザに感染した児童・生徒等について登校停止が定められていますが、
労働者に対する法的な「就業禁止」の規定はありません。
しかし、感染拡大を防止するため、会社が独自に「一定期間の自宅待機命令」を出すことは可能です。
この場合、命令の合理性(感染リスクや職場環境の状況など)が重要になります。
4.実務での判断ポイント
✅ 出社を拒むことができる場合
- 医師により「インフルエンザ」と診断された
- 発熱や咳など、他者に感染するおそれがある
- 社内で感染拡大のリスクが高い(同部署に高齢者や妊婦がいる等)
これらの状況では、安全配慮義務に基づき休業命令を出すことが妥当です。
✅ 出社を拒めない可能性がある場合
- 医師から「回復し、出社可能」と診断されている
- PCR検査等で陰性が確認されている
- 会社側の都合(風評リスクなど)による過剰な対応
このような場合、過剰な制限は違法な休業命令と判断されるおそれがあります。
5.【事例】実際にあったケース
事例①:感染防止のため自宅待機命令を出したケース
従業員がインフルエンザA型に感染。本人は「熱も下がったので出社したい」と申し出ましたが、
会社は「他社員への感染リスク」を理由に自宅待機を3日間命じた。
→ この命令は安全配慮義務に基づく合理的な措置とされ、問題なし。
ただし、会社都合の休業と判断され、休業手当(平均賃金の60%)を支給しました。
事例②:無理に出社させた結果、クラスター発生
繁忙期のため出社を認めたところ、職場内で複数名が感染。
他の従業員から「感染防止措置を怠った」との指摘があり、会社は安全配慮義務違反を問われた。
→ 後日、労働基準監督署から注意喚起を受け、感染症対応マニュアルを整備することになりました。
6.実務対応のポイントまとめ
| チェック項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 医師の診断書の確認 | 「出社可否」や「安静期間」の指示を必ず確認 |
| 自宅待機命令の文書化 | メールや書面で命令内容を明確化しておく |
| 休業手当の検討 | 会社都合による場合は支払いが必要 |
| 感染防止策 | テレワーク活用、マスク・換気・アルコール消毒の徹底 |
| 復帰判断の基準 | 「解熱後2日」「症状軽快から48時間」などを社内ルール化 |
7.まとめ|感染拡大防止と従業員の権利のバランスを
インフルエンザ感染時の出社制限は、職場の安全と健康を守るための正当な対応です。
一方で、過剰な出社制限や手当未支給はトラブルの原因にもなります。
会社としては、医師の診断内容・感染状況・労働基準法のバランスを踏まえたうえで判断し、
「感染症時の対応ルール」を就業規則や社内マニュアルに明記しておくことが望まれます。
📚根拠法令・参考情報
- 労働基準法 第26条(休業手当)
- 民法 第623条(雇用)
- 労働契約法 第5条(安全配慮義務)
👉 初回相談無料|感染症対応・休業ルール整備のご相談はこちら