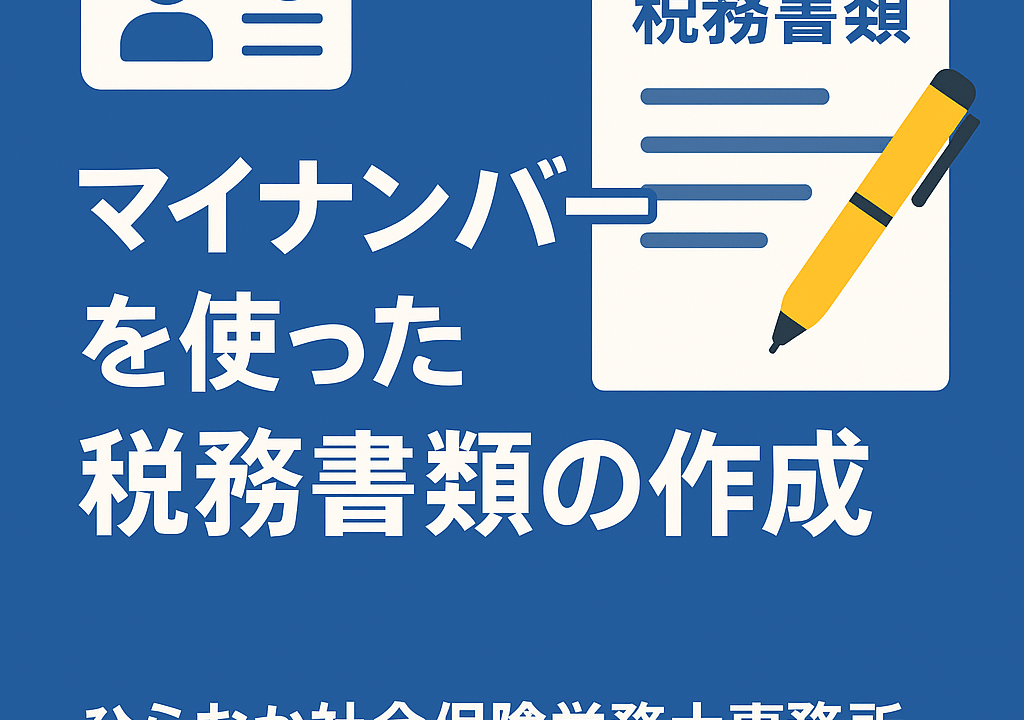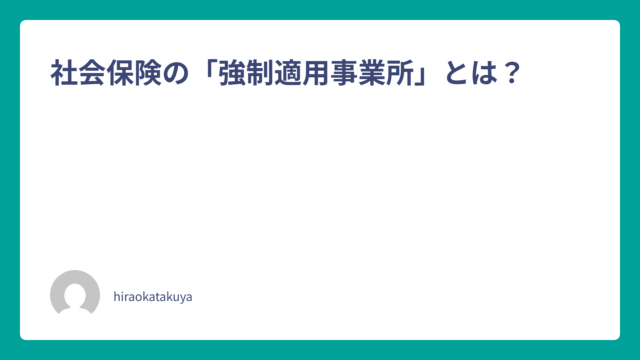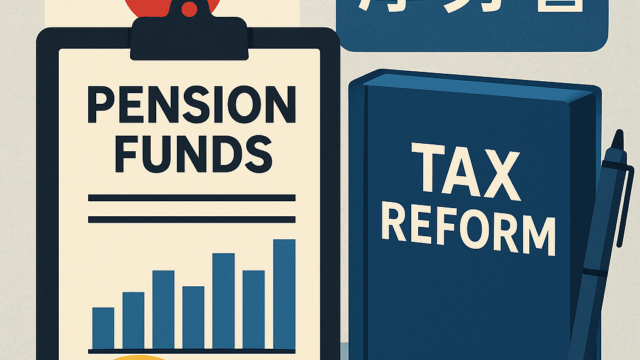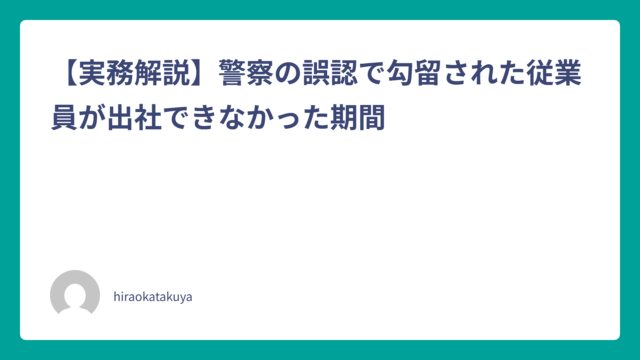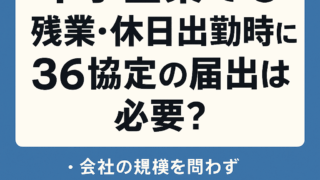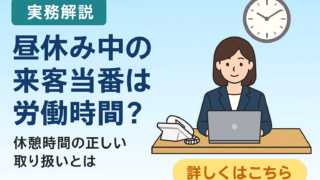近年、マイナンバー制度が定着し、企業でも
- 源泉徴収票
- 法定調書
- 社会保険・雇用保険手続き
などでの使用が日常的になってきました。
そこでよく質問を受けるのが、
「給与計算や労務担当者が、マイナンバーを使って源泉徴収票を作成・提出しても違法ではないか?」
という点です。
この記事では、税理士法の制限と実務でできることを、事例を交えてわかりやすく解説します。
■結論:他人の税務書類を作成して提出するのは“原則、税理士だけ”
税理士法52条では、次の行為は税理士業務とされ、
税理士または税理士法人でなければ行ってはならないと規定されています。
✔ 税務代理
(税金に関する申告・陳述・申請を代わりに行うこと)
✔ 税務書類の作成
(源泉徴収票、法定調書、確定申告書等の作成)
✔ 税務相談
(税金計算・節税方法等についての助言)
したがって、
社労士や行政書士、アウトソーシング会社など、税理士以外の者が “他人の税務書類” を作成・提出することはできません。
違反すると、
2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(税理士法59条)
が科される可能性があります。
■では「企業の給与担当者」が源泉徴収票を作成するのは違法?
→ 結論:違法ではありません。
税理士法が禁止しているのは
“他人の依頼を受け、報酬を得て税務書類を作成する行為”
です。
給与担当者は「自社の税務書類」を作成しているだけなので、
税務書類作成には該当せず合法です。
■企業が自社の税務書類を作成するのは合法
ここが一番重要なポイントです。
✔ 自社の源泉徴収票
✔ 自社の法定調書
✔ 自社の給与支払報告書
これらは、
“提出義務者である事業者自身が、自己判断で作成する業務”
に該当するため、
税理士法の「税務書類作成」とはみなされません。
したがって、
経理担当者・総務担当者・給与担当者が作成しても問題ありません。
■外部の社労士・代行業者はどこまで可能?
社労士やアウトソーシング会社は、
- 給与計算の代行
-マイナンバー収集・管理 - 給与明細作成
- 給与計算結果の納品
などは可能ですが、
❌ 源泉徴収票の作成(代行)
❌ 法定調書の作成(代行)
❌ 税務署への提出(代行)
これらは税理士以外が行うと「税理士法違反」と評価されます。
ただし、
“事業者自身が作成するための準備資料” を作成することは可能
とされており、実務では「たたき台」「集計表」を社労士が作るケースは多くあります。
■【事例】違法になったケースとセーフなケース
▼事例①:違法と判断されたケース
B社(従業員20名)が給与アウトソーシング会社へ依頼
アウトソーシング会社が
- 源泉徴収票を作成
- 税務署へ電子提出
- 給与支払報告書も代行提出
を行っていた。
▼結果
税務署から指摘が入り、税理士法違反の可能性を指摘。
元請会社は業務見直しを余儀なくされた。
▼問題点
- 提出義務者は本来B社なのに、
外部業者が「税務書類の作成」+「提出」を代行していた - 報酬を得て書類を作成しており、税理士法違反に該当
▼事例②:適法とされたケース
社労士事務所が給与計算を受託しているA社
社労士は…
- 給与計算(税額控除の計算含む)
- 源泉徴収票の「下書き(ドラフト)」作成
- 法定調書の集計表作成
- マイナンバーの管理
- 本番の提出作業はA社自身が実施
(電子申告IDもA社のものを使用)
▼結果
すべて適法。
社労士法・税理士法のいずれにも抵触しない。
▼理由
- 税務書類の「最終作成」「提出」はあくまでA社
- 社労士はあくまで“資料作成”の範囲にとどまった
- 税務相談や税務代理も行っていない
■まとめ:税務書類を作成・提出できるのは税理士だけ(ただし自社分は例外)
企業実務のポイントは以下のとおりです。
▼税理士しかできない
- 源泉徴収票の作成代行
- 法定調書の作成代行
- 税務署への提出代行
- 税務相談(税額の判断含む)
- 税務代理
▼企業自身ならできる
- 自社の源泉徴収票作成
- 自社の法定調書作成
- 自社の税務書類提出
▼社労士・代行会社ができる
- 給与計算(税額計算含む)
- マイナンバー収集・管理
- 税務書類の下書き・集計資料作成
- 電子申告の操作補助(IDは企業本人)
企業が安心して業務を行うためには、
税理士業務に該当しない範囲で運用することが重要です。
税務書類の作成範囲や給与計算の外部委託でお悩みの企業様へ
ひらおか社会保険労務士事務所では、
- 給与計算体制の点検
- 税務書類の適法な作成方法のアドバイス
- 電子申告の運用サポート
- 税理士との役割分担の整理
- マイナンバー管理の運用整備
など、法令遵守しながら業務効率化を支援しています。
以下のボタンからお気軽にご相談ください。