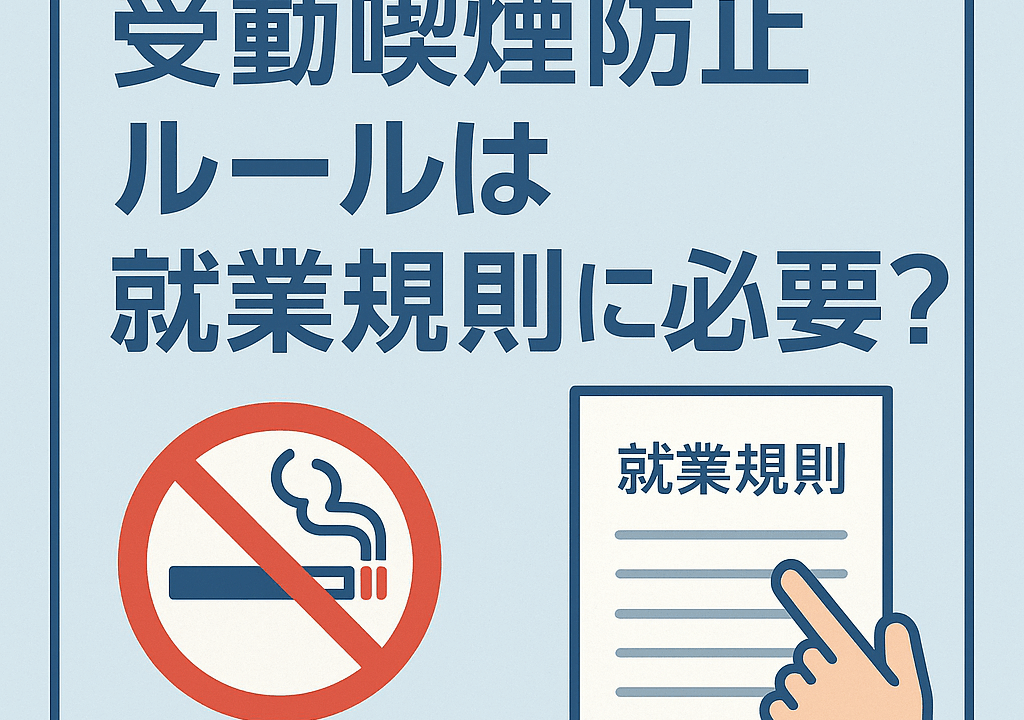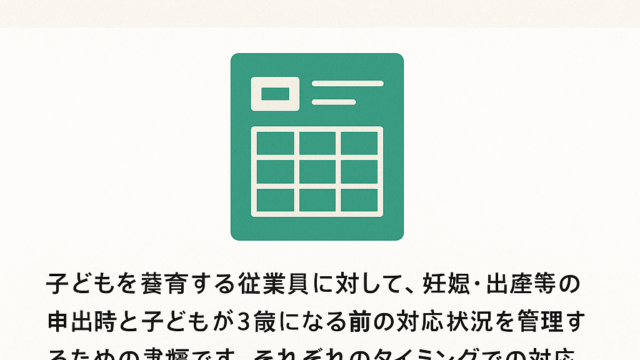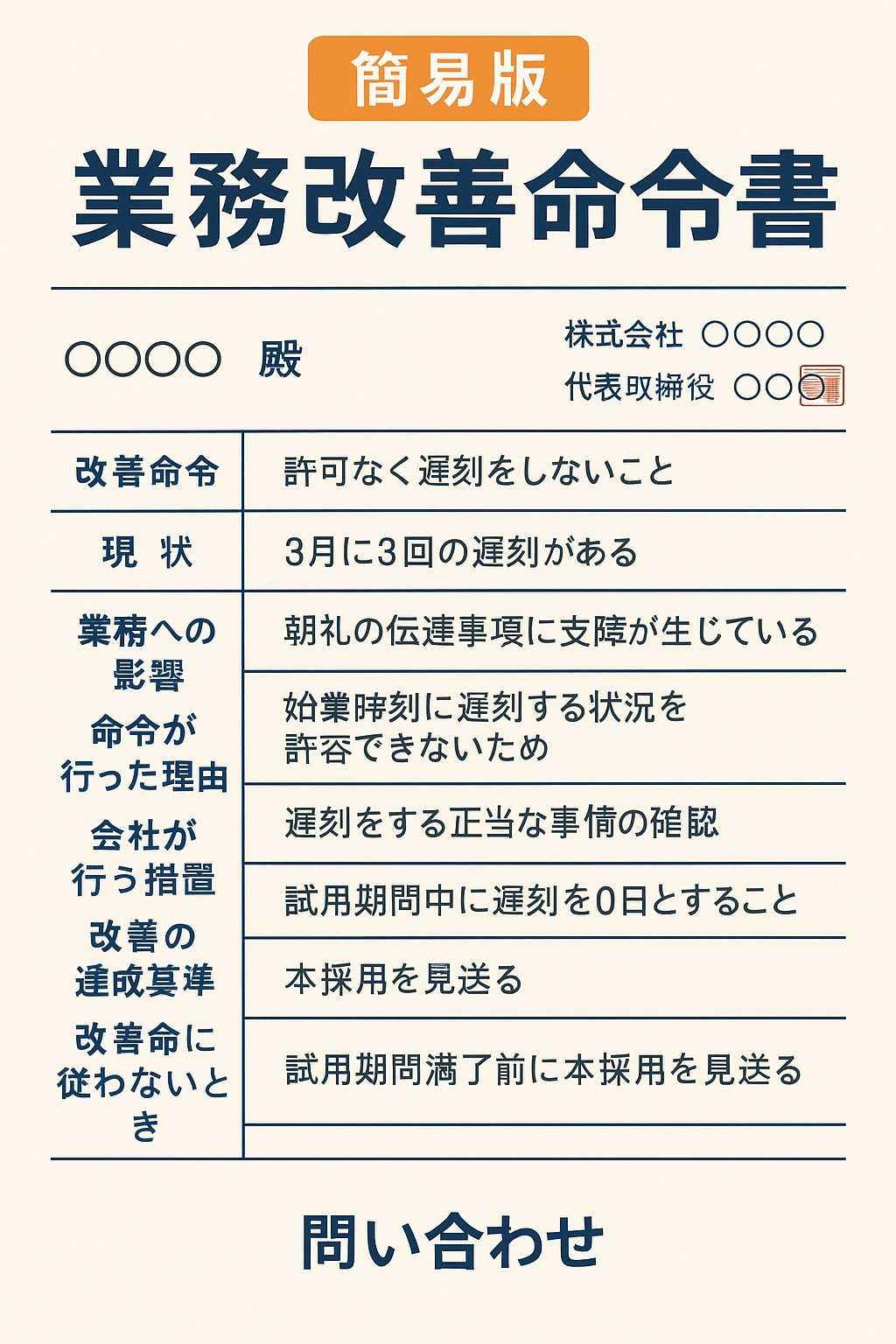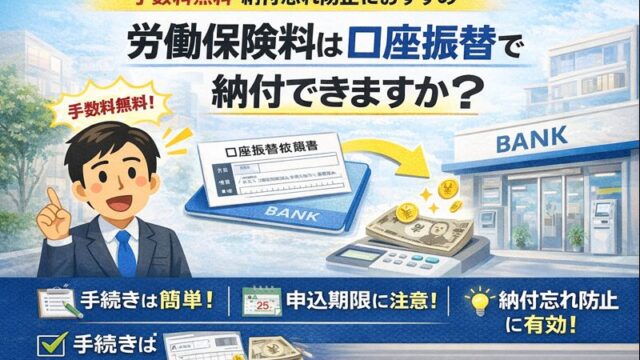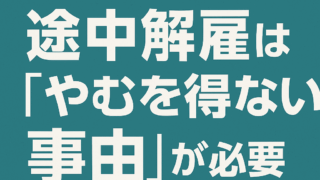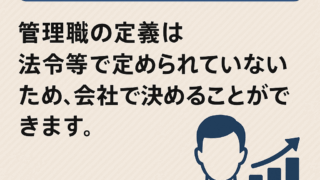〜義務ではないが「定めるメリット」が大きい理由〜
❖ 結論:法的義務はないが、就業規則に定めることをおすすめします
受動喫煙防止に関して、就業規則に明記する法的義務はありません。
しかし、職場トラブルの防止やコンプライアンス対応として定めておくことが望ましいとされています。
労働安全衛生法では、事業者に対して次のような努力義務を課しています。
労働安全衛生法 第68条の2
事業者は、室内またはこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するために、
適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
つまり、法律上は「努力義務」ですが、実際には多くの企業が就業規則などの社内ルールで受動喫煙防止策を明文化しています。
❖ 受動喫煙防止対策を就業規則に入れるメリット
① トラブルの未然防止
喫煙者と非喫煙者の間でのトラブル(臭い・休憩時間・喫煙場所など)は、意外と多い問題です。
就業規則に「喫煙に関するルール」を定めることで、公平な職場環境を整えることができます。
② 組織的な管理の一環として有効
厚生労働省の通達(平成27年5月15日 基安発0515第1号)では、
受動喫煙防止対策を効果的に進めるには、組織的・計画的な実施が重要とされています。
就業規則で定めることで、企業としての方針を明確化できます。
③ 健康経営・イメージ向上
健康経営を推進する企業にとって、受動喫煙防止は欠かせない要素です。
特に医療・介護・教育業界では、非喫煙環境の整備が信頼性向上にもつながります。
❖ 【実務事例】就業規則に定めたことでトラブルを防げたケース
事例:オフィス内での喫煙をめぐる苦情
ある事務所では、屋外に喫煙スペースを設けていましたが、
一部の社員が「雨の日は屋内の出入口付近で吸っていた」ことから、
非喫煙者から苦情が相次ぎました。
そこで会社は、就業規則に次のような条文を追加しました。
<就業規則例文>
(受動喫煙の防止)
第○条 会社は、従業員の健康保持及び快適な職場環境の形成を目的として、受動喫煙防止対策を実施する。
2 就業時間中の喫煙は、会社が指定する喫煙場所において行わなければならない。
3 敷地内禁煙の場合は、会社の定めに従い、喫煙を控えるものとする。
このように明文化したことで、
喫煙者・非喫煙者の双方がルールを共有でき、再発防止と職場の信頼関係向上につながりました。
❖ 実務での対応ポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ✅ 現状の喫煙環境を確認 | 喫煙室・屋外スペースの有無を把握する |
| ✅ 従業員への周知 | 禁煙・分煙ルールを掲示・説明する |
| ✅ 就業規則で明文化 | トラブル防止・健康経営の一環として記載 |
| ✅ 罰則は慎重に設定 | 原則は指導・注意レベルにとどめる |
❖ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的義務 | 就業規則に定める義務はない(努力義務) |
| 定めるメリット | トラブル防止・健康経営・方針明確化 |
| 対応の流れ | 現状把握 → 社内ルール化 → 周知徹底 |
受動喫煙防止は「法令遵守」だけでなく、
社員が安心して働ける職場づくりにも直結します。
就業規則で明文化しておくことは、
「企業の信頼性」を高めるための小さくても大切な一歩です。
✅ 初回相談無料|就業規則・職場環境改善のご相談はこちら