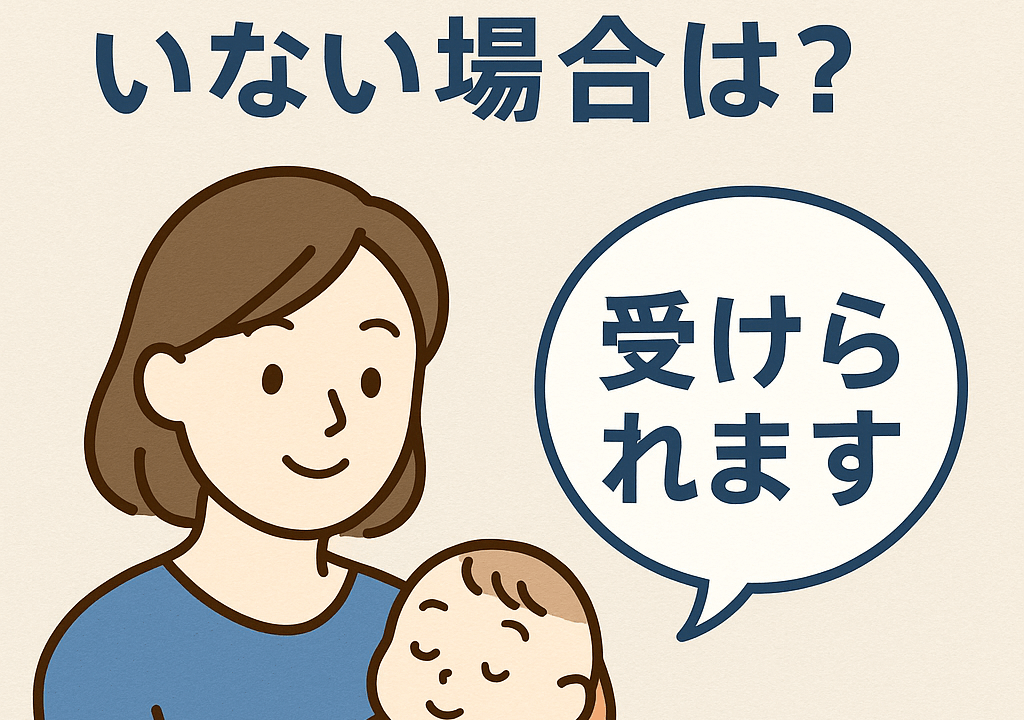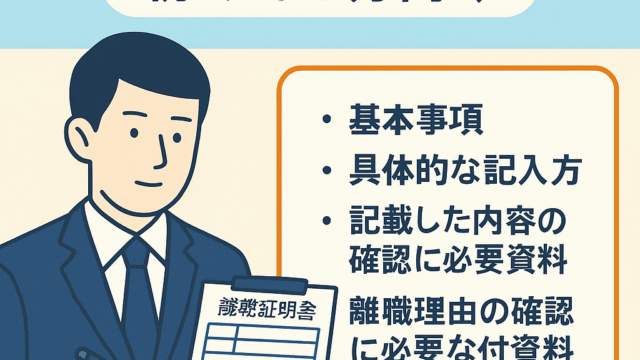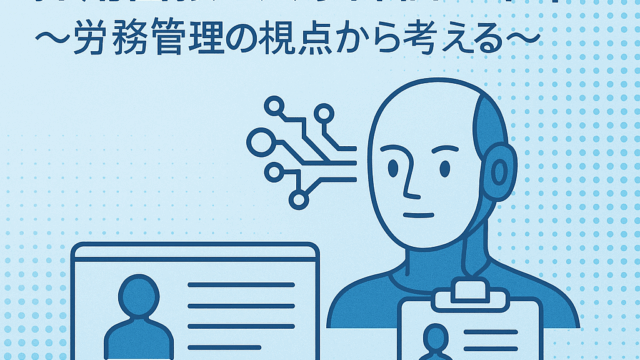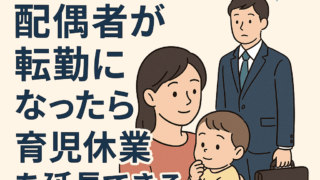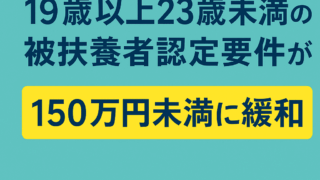結論
就業規則に育児休業の定めがなくても、
本人の申出を会社が認めた場合には、育児休業給付を受けることができます。
つまり、
💡 「就業規則に書かれていない=給付が受けられない」ではありません。
育児休業給付とは?
育児休業給付は、雇用保険に加入している労働者が、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される制度です。
目的は、
「仕事と育児の両立を支援し、育児休業後の職場復帰を促すこと」。
支給額は休業前賃金の一定割合で、一般的には次の通りです。
| 支給期間 | 支給率(賃金月額に対する割合) |
|---|---|
| 休業開始から180日まで | 67% |
| 181日以降 | 50% |
就業規則に定めがなくても大丈夫な理由
雇用保険法上、育児休業給付の支給要件は「育児休業を取得していること」です。
この「取得していること」は、会社が育児休業を認めていれば足ります。
つまり、
- 就業規則に育児休業の条文がない
- 規程整備が追いついていない
といった場合でも、本人が申出を行い、会社が了承すれば、育児休業として扱われます。
実務でのポイント
- 申出書類を残すことが大切
→ 書面またはメールなど、休業の「申出」と「会社の承認」が分かる形で記録しておきましょう。
ハローワークの育児休業給付申請時に必要です。 - 雇用保険加入が前提
→ パートや契約社員であっても、雇用保険の被保険者であれば給付対象になります。 - 育児休業期間中も雇用関係が継続していること
→ 退職予定がある場合は対象外です。
事例①:就業規則に育児休業の規定がない小規模事業所
事例
従業員5名の小規模事業所。
就業規則の整備はまだ行っておらず、育児休業の項目もなし。
従業員Aさん(雇用保険加入者)が「出産後1年程度休みたい」と申し出。
結果
→ 会社が了承し、実際に育児休業を取得した場合、
育児休業給付金の対象になります。
就業規則に定めがなくても問題ありません。
ポイント
ハローワーク申請時に、「会社が育児休業を認めていること」が確認できるよう、
育児休業申出書や承認書の控えを用意しておくとスムーズです。
事例②:会社が規程を整備していないが、申請が認められたケース
事例
B社では育児休業に関する規定がないが、社員が「育児休業を取りたい」と申し出た。
社長は「うちは初めてだけど、いいよ」と口頭で了承。
結果
→ 会社の承諾があるため、育児休業として有効。
ハローワークへの申請も可能です。
ただし、後日トラブル防止のため、書面またはメールで承認内容を残すことが望ましいです。
実務担当者が注意すべき点
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 就業規則の整備 | 就業規則に明文化しておくことでトラブル防止につながります。 |
| ✅ 申出書の保管 | 労働者の申出書、会社の承認記録を必ず残す。 |
| ✅ 育児休業の通知 | 育児休業開始・終了予定日を明確にし、給与・社会保険手続きを連携。 |
| ✅ 社会保険料免除 | 育児休業中の健康保険・厚生年金は免除申請が可能。 |
根拠法令・参考情報
- 東京労働局『雇用保険事務手続きの手引き』
- 雇用保険法 第61条の4(育児休業給付)
- 労働基準法 第89条(就業規則の作成及び届出)
まとめ
| 状況 | 給付を受けられるか | ポイント |
|---|---|---|
| 就業規則に育児休業の規定なし | 〇 受給可能 | 会社が承認していれば対象 |
| 就業規則に規定あり | 〇 受給可能 | 規程に沿って申出・承認 |
| 会社が承認していない | × 対象外 | 「会社の認めた休業」であることが必須 |
初回相談は無料です
育児休業や給付金の申請、就業規則の整備などでお困りの企業様へ。
制度を知らずに手続きをしないと、従業員が損をしてしまうこともあります。
社会保険労務士が実務に即したアドバイスと手続き代行を行います。