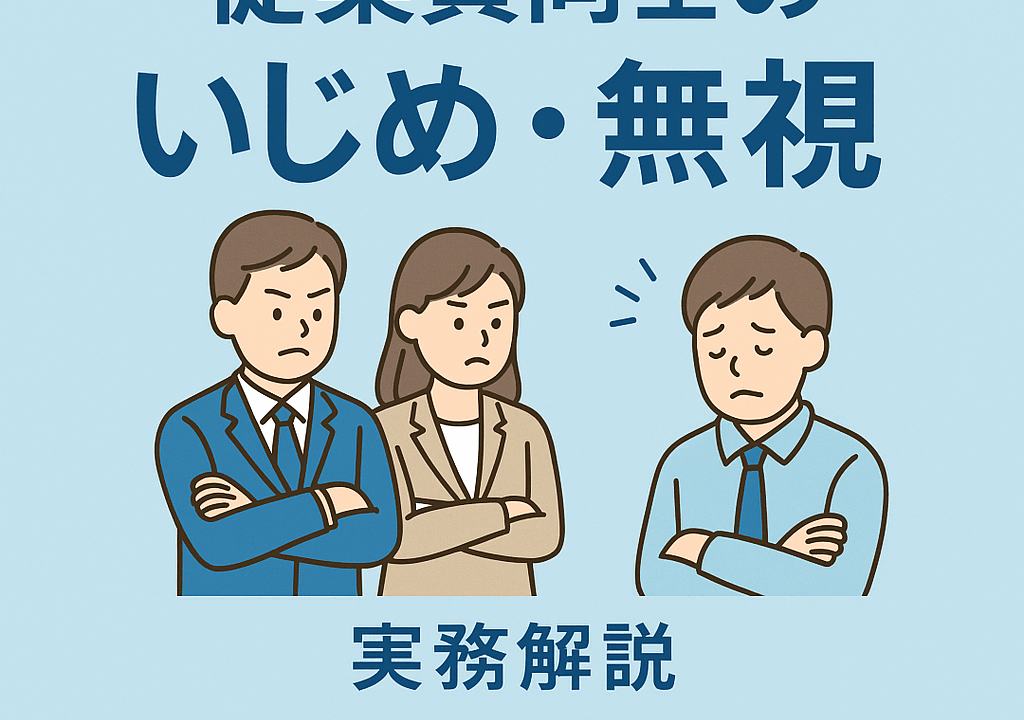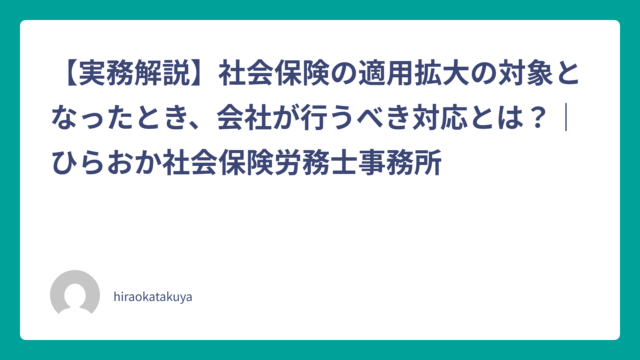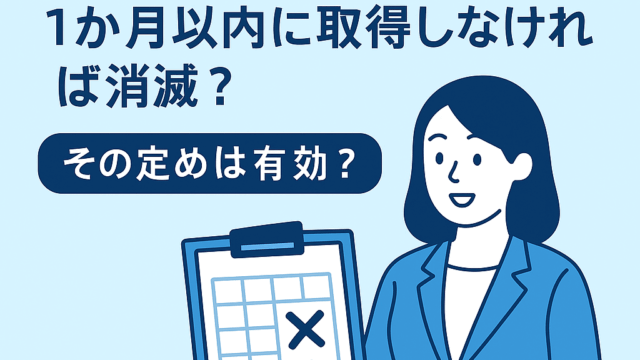職場で、
「特定の従業員が無視されている」
「いじめのような扱いを受けている」
という相談は、中小企業でも増加しています。
こうした行為は、放置すると
パワーハラスメント に該当する可能性が高く、
重大なメンタル不調や退職、労災、法的トラブルへ発展することもあります。
企業には 迅速かつ適切に対応する法的義務 があるため、
本記事では、社労士として押さえるべき
実務手順・注意点・具体的事例 をまとめて解説します。
■ 職場のいじめ・無視はパワハラに該当する可能性が高い
いじめ・無視は、
「業務上必要かつ相当な範囲」を超えて
従業員の心身にダメージを与える行為 であり、
- 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
- 労働契約法5条(安全配慮義務)
などの観点から、
事業主の早期対応が必須 とされています。
■【具体例】このような行為はいじめ・パワハラに該当します
● 1. 会話・連絡を意図的に無視する行為
- 挨拶しても返さない
- 業務連絡を回さない
- グループLINEから除外する
● 2. 集団での孤立化
- 昼休憩で特定の従業員を避ける
- 飲み会や打ち合わせに意図的に呼ばない
● 3. 悪口・陰口・人格否定
- 「使えない」「役に立たない」などの侮辱
- 背後での噂話・悪評の拡散
● 4. 不当な業務の外し方・過小指示
- 本来必要な業務から外す
- 指示を出さず放置する
いずれも、
職場環境を害する行為として企業の対応が義務付けられています。
■【実務事例】実際に企業で起きたケース
◆ 事例①:無視・連絡外しが続き、被害者が体調不良に
同部署の複数名が特定の従業員に連絡を回さず、
会話もしない状態が続いたことで、その従業員が
不眠・頭痛・食欲低下などのメンタル不調 に。
会社が把握していたにもかかわらず対策を取らなかったため、
安全配慮義務違反が問われたケース。
→ 企業の誤りポイント
- 「様子を見る」と放置
- 周囲への注意喚起がされなかった
- 相談窓口への誘導がなかった
◆ 事例②:ライン外しが原因で業務ミスが頻発
グループLINEから特定の社員が外され、
シフト変更・作業指示が届かずミスが発生。
→ 企業が取るべき対応
- 事実確認(誰が・いつ・どのように外したか)
- 関係者へのヒアリング
- LINE利用ルールを見直し
- 再発防止(業務連絡は社内ツールへ統一など)
◆ 事例③:嫌がらせが原因で退職 → 労災請求に
日常的に無視・陰口があり退職。
その後、心因性疾患の労災申請へ。
→ 企業に求められたこと
- 被害者への配慮措置
- 行為者の指導・注意
- 相談体制の整備
- 就業規則の明確化
■ 企業が必ず行うべき「正しい対応の流れ」
いじめ・無視が報告されたら、
企業は次の手順で対応する必要があります。
✔ STEP1:事実確認(ヒアリング)
被害者 → 行為者 → 周囲の従業員 の順が基本。
特に、
- 時期
- 行為の内容
- 具体的な場面
- 業務への影響
を客観的に記録します。
※事実確認をしない「思い込みの判断」はNG
✔ STEP2:被害者への配慮措置
- 必要に応じて配置変更
- メンタルヘルスケアの案内
- 相談窓口担当者からのフォロー
被害者が不利益を受けるような配置転換は絶対に避ける。
✔ STEP3:行為者への適正な対処
- 注意指導
- 文書による厳重注意
- 悪質・継続的な場合は懲戒の検討(就業規則に基づく)
※私的な感情ではなく、客観的事実に基づいて判断する。
✔ STEP4:再発防止策を実施
- 職場内ルールの明確化
- 研修・ミーティングで周知
- 相談体制の強化
- 管理職教育の実施
厚労省指針では、
「職場環境の問題が背景となってパワハラが生じるおそれがある場合も相談に対応すること」
と明記されています。
■ 放置すると「安全配慮義務違反」に該当する可能性あり
労働契約法5条の
「安全配慮義務」 により、
企業は従業員の心身の健康に配慮する義務を負っています。
いじめ・無視を把握していながら、改善措置を取らない場合、
企業には以下のリスクがあります。
- 労災請求
- 損害賠償請求
- 行政指導
- 退職者増加・離職率悪化
- 職場風土の悪化
■ 根拠法令・参考情報
- 労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
- 労働施策総合推進法 第30条の2
- 厚生労働省告示第5号
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011660&dataType=0&pageNo=1
■ まとめ:いじめ・無視は“放置が最も危険”
従業員同士のいじめや無視は、
表面上は些細な問題に見えても
重大なパワハラ に発展する可能性があります。
企業は、
- 迅速な事実確認
- 被害者の保護
- 行為者への指導
- 再発防止策
を確実に行う必要があります。
早めの介入がトラブルの芽を摘む一番の方法です。