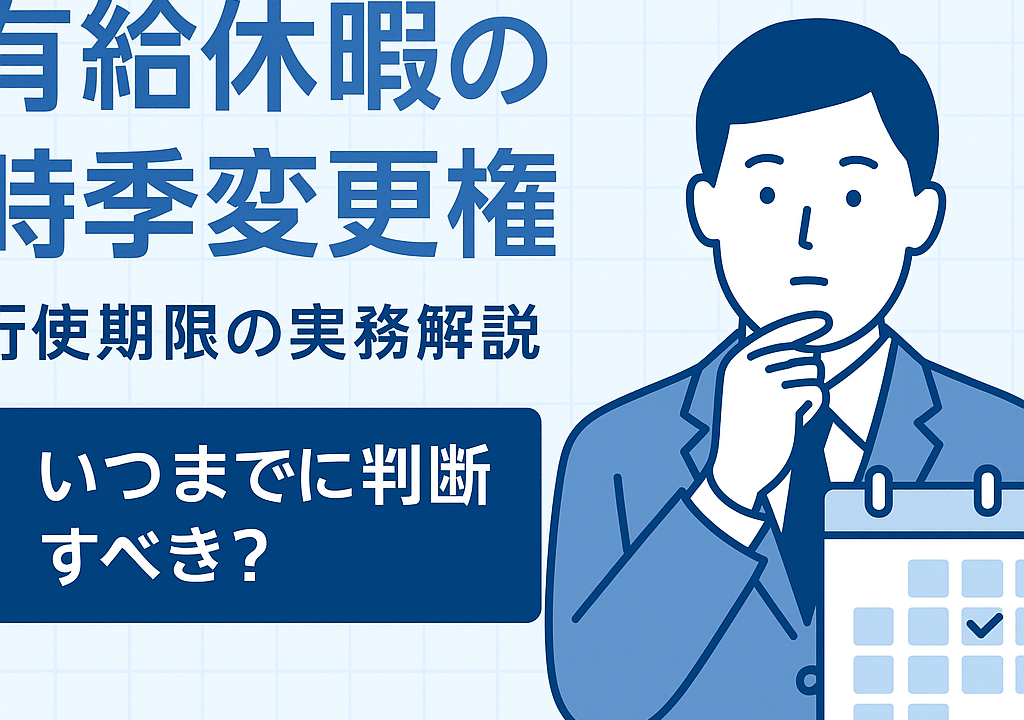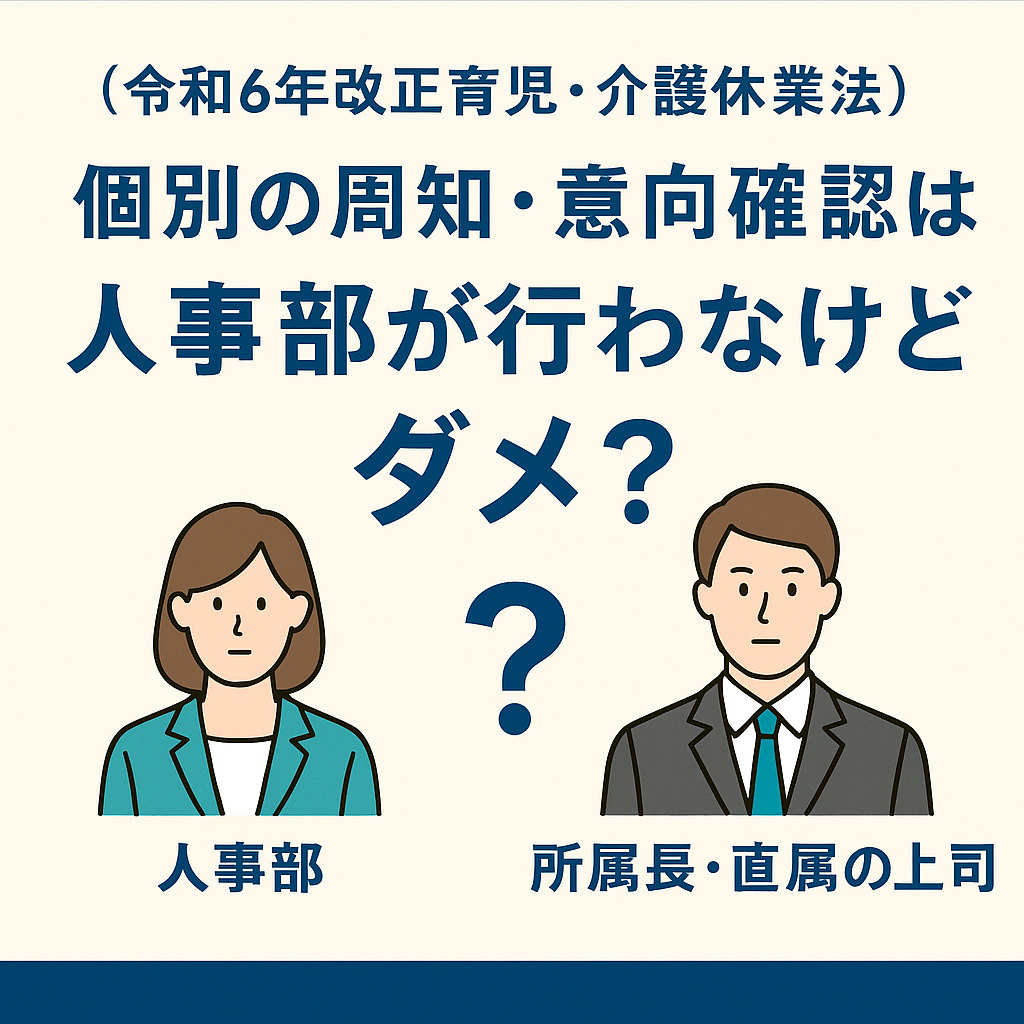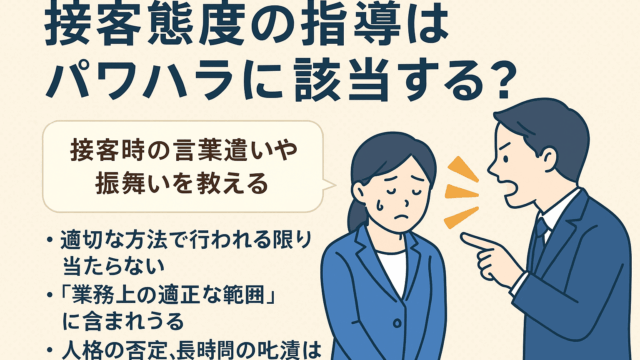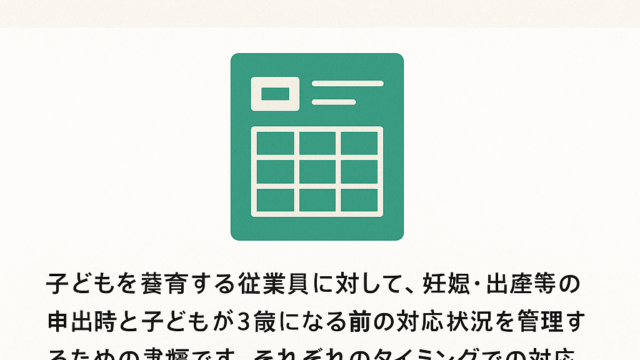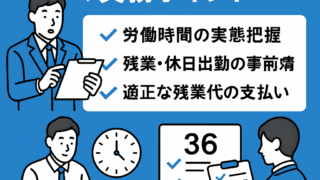「従業員から有給休暇の申請があったけれど、業務が立て込んでいて対応できない…」
このようなときに会社が使うことができるのが、「時季変更権」です。
しかし、「いつまでに判断しないといけないのか?」については、意外と見落とされがちです。
この記事では、判断のタイミング・実務上の注意点・具体的な事例をわかりやすく解説します。
1.そもそも「時季変更権」とは?
労働基準法第39条に基づき、労働者には年次有給休暇を自由に取得できる権利があります。
ただし、会社側にも一定の条件のもとで、時季変更権(じきへんこうけん)を行使できる場合があります。
労働基準法 第39条第5項
使用者は、年次有給休暇の請求があった場合において、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更することができる。
つまり、
「業務に著しい支障が出る場合」には、取得日を変更してもらうよう命じることができるという制度です。
2.判断のタイミング:いつまでに行使すべきか?
時季変更権を行使するか否かの判断は、
従業員から有給休暇の取得希望日(時季指定)がされた後に行う必要があります。
その際の判断は、
「事業の正常な運営を妨げるかどうか」を見極めるために必要な合理的期間内に行わなければなりません【労働基準法第39条】。
📍 ポイント
- 必要以上に判断を引き延ばすのはNG
- **できるだけ速やかに(通常は申請を受けて数日以内)**判断することが望ましい
合理的期間を過ぎてから「やっぱりダメ」と言うのは、
実質的に時季変更権の行使が認められない(無効)と判断される可能性が高くなります。
3.【事例①】繁忙期の直前に申請があったケース
〈状況〉
営業部のAさんが、「来週の木・金に有給を取りたい」と申請。
ただし、その週は新規契約対応が集中しており、代替要員の確保が難しい状態。
〈対応〉
会社は申請翌日にAさんと面談し、業務状況を説明。
翌週ではなく翌々週に変更を依頼。
→ この対応は、「合理的期間内に判断・通知」しており適法。
業務上の支障が明確で、代替日も提示しているため、時季変更権の行使が認められます。
4.【事例②】申請から判断まで1週間放置したケース
〈状況〉
経理担当のBさんが、2週間後の金曜日に有給を申請。
上司は忙しくて確認を後回しにし、休暇予定日の前日に「業務が立て込んでいるから休まないで」と伝えた。
〈結果〉
これは時季変更権の行使として認められない可能性が高いです。
申請から1週間以上経過しており、従業員が旅行等の予定を組んでいた場合、
「合理的期間を超えての行使」であるとして無効扱いになるおそれがあります。
5.「合理的期間」とはどのくらい?
法律上、明確な日数は定められていませんが、
厚生労働省や裁判例の考え方から見ると、以下のような基準が目安です。
| 状況 | 判断・通知までの目安 |
|---|---|
| 通常の申請(2〜3週間前の申請) | 申請から 数日以内(3営業日程度) |
| 繁忙期などで調整が必要な場合 | 1週間以内に結論を出す |
| 前日や直前の申請 | 即日判断(当日中に可否を伝える) |
いずれにしても、「放置せず、迅速に判断・通知する」ことが求められます。
6.実務担当者が押さえておくべきポイント
✅ 時季変更権行使の条件
- 「事業の正常な運営を妨げる」実際の事由があること
(単なる人手不足や忙しいという理由だけでは不十分) - 代替要員確保や日程調整の努力をしても難しい場合に限定
✅ 対応手順
- 申請を受けたら即日上長・人事で共有
- 業務状況と代替要員を確認
- 必要があれば申請者と相談し、代替日を提示
- 判断結果は文書またはメールで通知
✅ 記録を残す
後日トラブルになった場合に備え、
申請日・判断日・理由・通知内容を記録に残しておくことが重要です。
7.まとめ|「速やかな判断」と「合理的な理由」がカギ
有給休暇の時季変更権は、
「例外的」かつ「慎重に」行使すべき制度です。
判断を遅らせたり、根拠のない理由で拒否したりすると、
法違反として行政指導や労使トラブルに発展することもあります。
申請があったら放置せず、
「早めに・合理的に・記録を残して」対応することが、労務トラブルを防ぐ最大のポイントです。
🔗根拠法令
- 労働基準法 第39条(年次有給休暇)
👉 初回相談無料|有給管理・労務トラブル対応のご相談はこちら