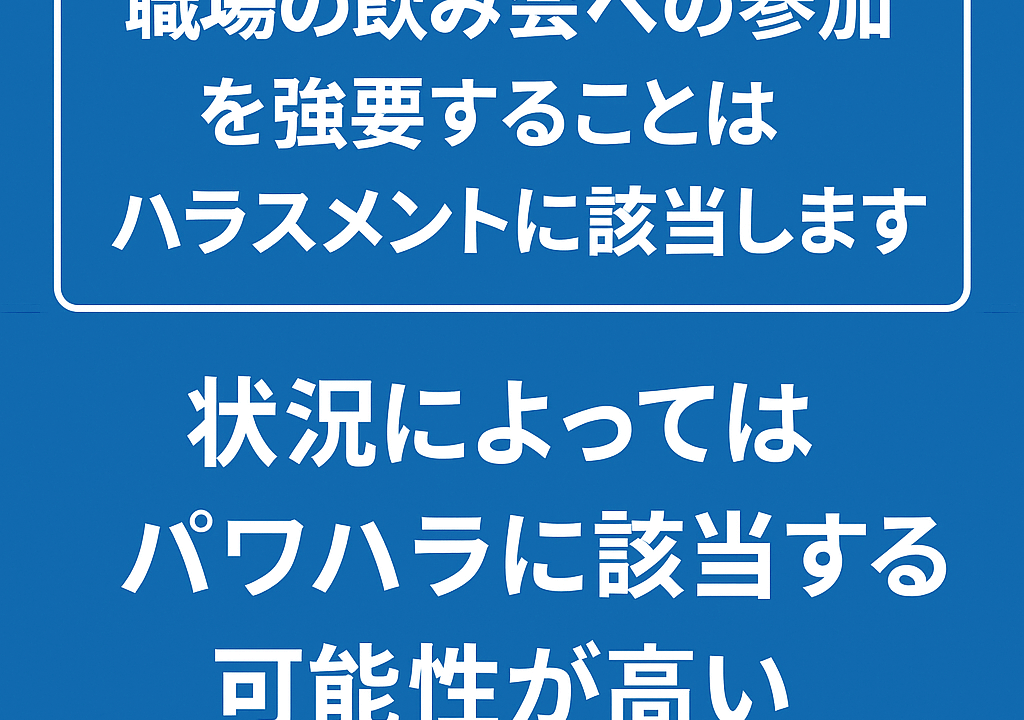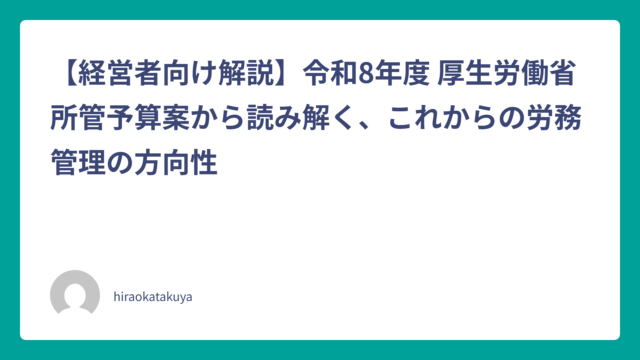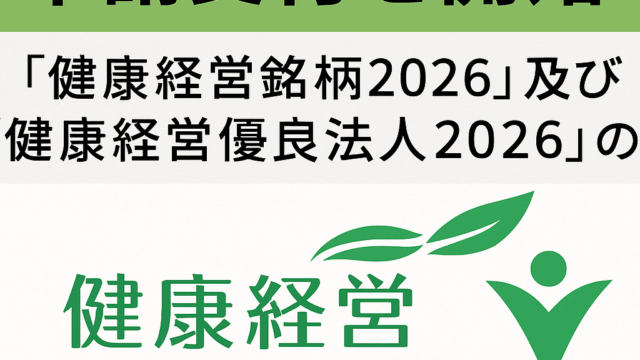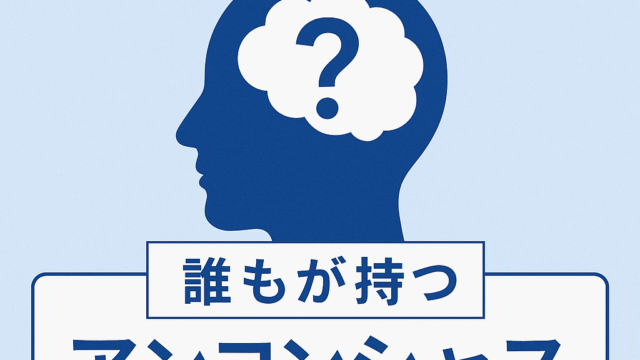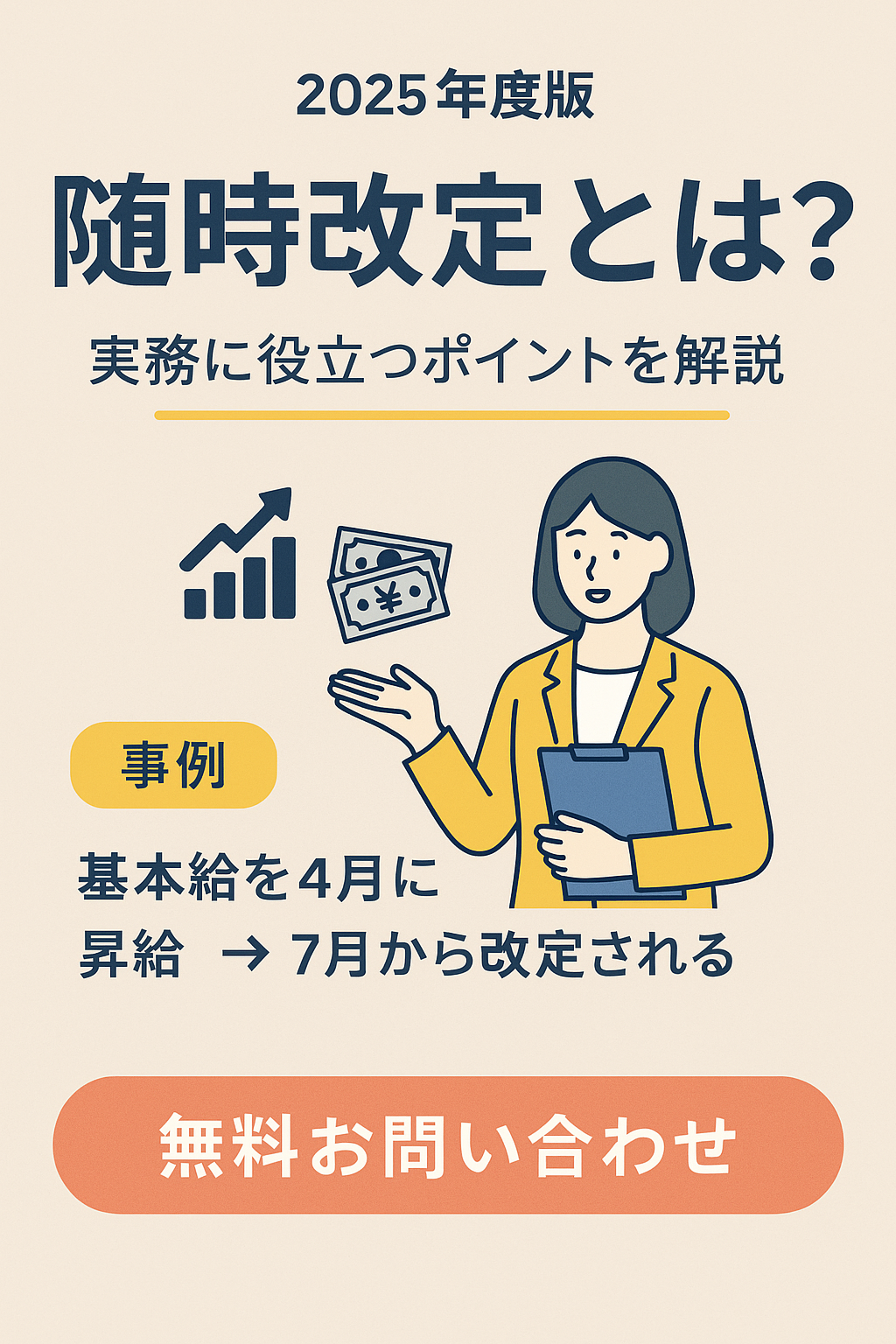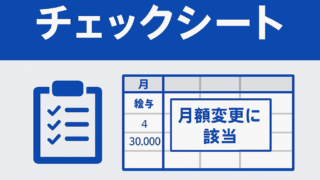職場では懇親会や歓迎会など、飲み会の機会が多くあります。
しかし近年、「飲み会への参加を断りにくい」「強制参加と言われた」という相談が増えています。
では、職場の飲み会への参加を強要することはパワーハラスメントに該当するのでしょうか?
結論としては、状況によってはパワハラに該当する可能性が高いとされています。
本記事では、企業が注意すべきポイントを実務目線でわかりやすく解説します。
■ 結論:職場の飲み会への参加強要は、パワハラに該当する可能性が高い
パワハラスメントの定義は次の3要件です。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 就業環境を害するもの
飲み会は業務外の活動であり、本来は自由意思で参加を選べるものです。
そのため、上司からの強制は「業務上必要とはいえない行為」に該当しやすく、パワハラに認定される可能性が大いにあります。
■ ハラスメントと判断されやすいケース(実務で多い例)
● パワハラと判断されやすい言動の例
- 「絶対参加しないと評価が下がるよ」
- 「新人は飲み会に出て当然だろう」
- 「行かないなら仕事を振らないよ」
- 飲み会を断った従業員に冷遇・無視・嫌味を言う
- 断っているのに何度も強引に誘う
業務と関係のない圧力・不利益の示唆はNGです。
■ 【事例】実際に相談でよくあるケース
◆ 事例1:参加しないと査定に響くと言われた(20代女性)
上司から飲み会参加を求められたが断ったところ、
「若手は参加必須だから。協調性の評価に響くよ」
と言われたケース。
評価への影響を示唆することは、明確にパワハラに該当する可能性が高いと判断されます。
◆ 事例2:飲み会を断ったらシフトを減らされた(飲食店パート)
育児のため飲み会を断ったところ、翌月からシフトが減ったケース。
このような 不利益取扱いはパワハラと労働条件不利益変更に該当するおそれがあります。
労働局や相談機関でも同種の相談は非常に多く、企業側は特に注意が必要です。
◆ 事例3:断っているのにしつこく誘われる(30代男性)
「今日は無理です」と伝えているにもかかわらず、
複数回誘われたり、皆の前で「雰囲気悪くなるから来いよ」と言われたケース。
これは優越的地位を背景とした精神的圧力になり、パワハラとして扱われる可能性が高いです。
■ 事業主が行うべき対応(実務ポイント)
ハラスメント防止措置は法的義務です(労働施策総合推進法 第30条の2)。
企業としては、以下を整えておくことが重要です。
● ① 飲み会は参加自由であることを明示
- 社内ルール(就業規則・ガイドライン)
- 社内掲示
- 管理職研修
● ② 「不利益取扱いは禁止」であることを周知
評価・配置・シフトなどに影響を与えることは厳禁です。
● ③ 管理職への研修を実施
管理職が無意識に圧力をかけてしまうことが多いため、
研修で「言ってはいけない言動」を共有します。
● ④ 相談窓口の設置・対応マニュアル整備
従業員が安心して相談できる環境づくりは必須です。
■ 根拠法令・参考情報
- 労働施策総合推進法 第30条の2
- 厚生労働省告示第5号「事業主が講ずべきハラスメント防止措置」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011660&dataType=0&pageNo=1
■ まとめ
飲み会はあくまで「任意参加」であり、
強制・圧力・不利益取扱いはパワハラに該当する可能性が非常に高い行為です。
特に中小企業では、悪気はなくても「文化として当然」と思っている場合が多いため、
管理職教育とルール整備が重要になります。
従業員の働きやすい環境づくりは、離職防止・採用力向上にも直結します。
ハラスメント防止に向けた規程整備や研修はお気軽にご相談ください。