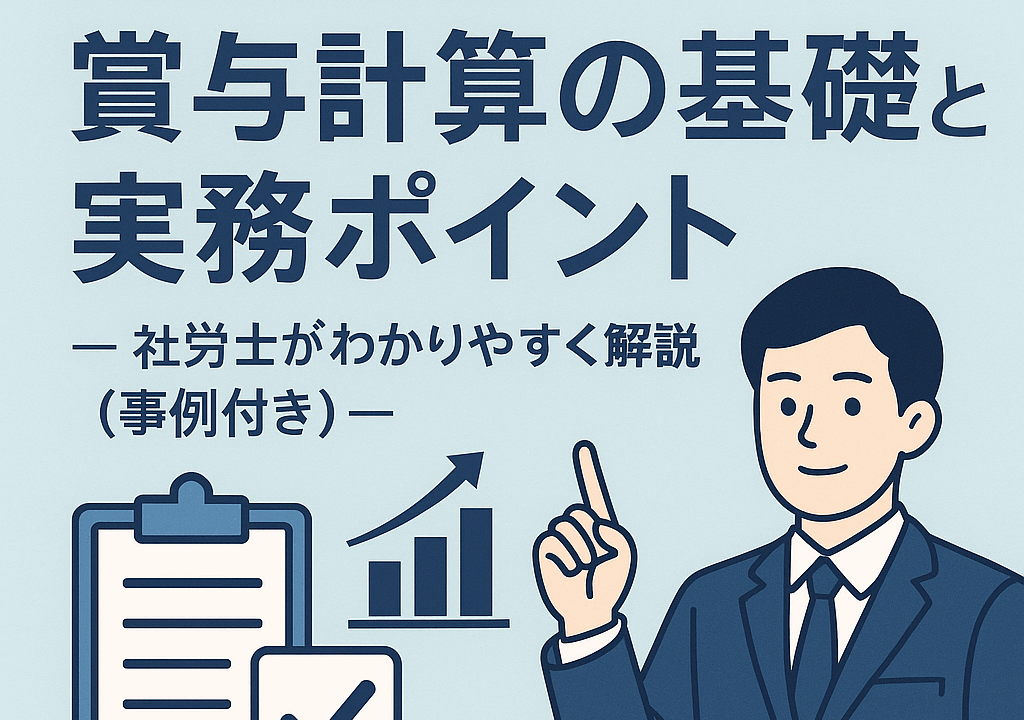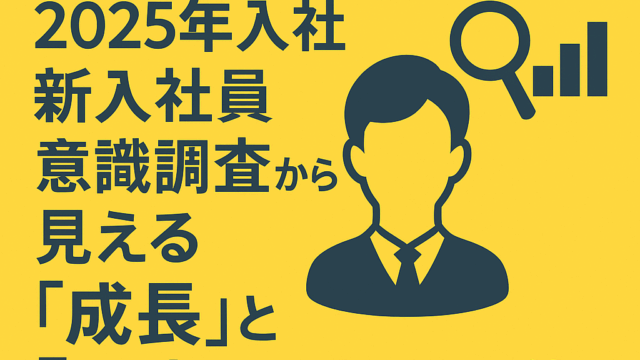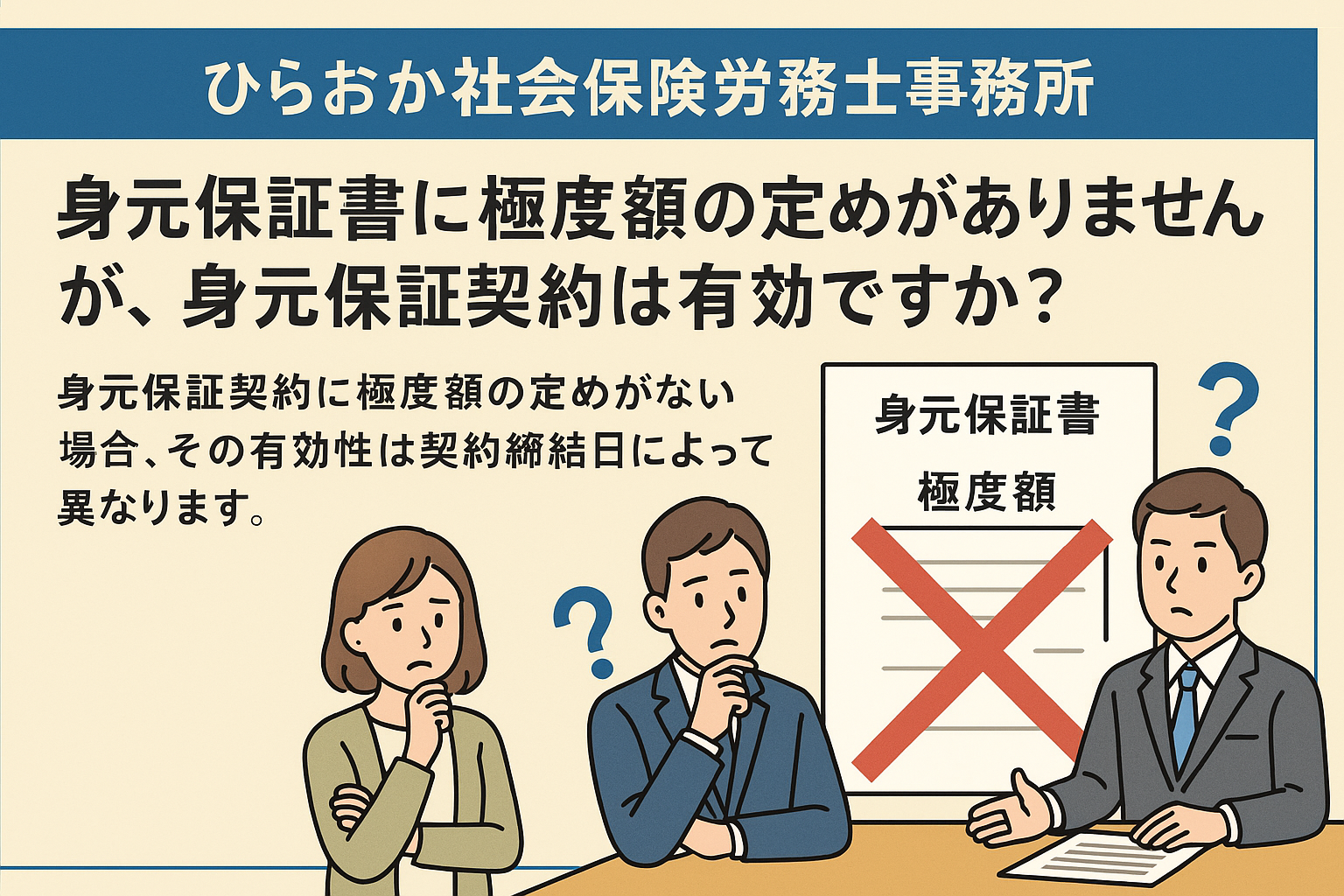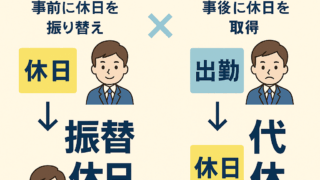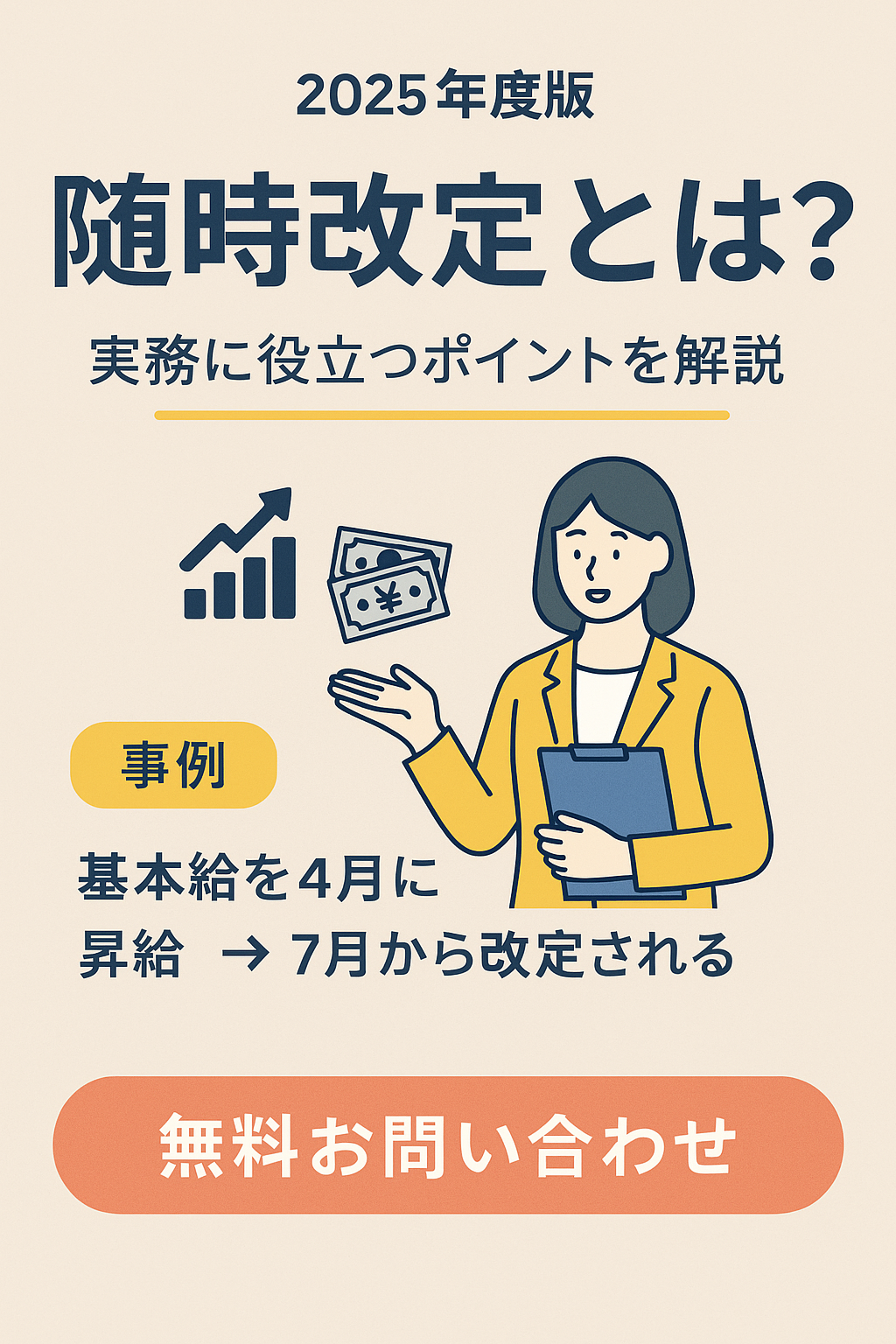― 社労士がわかりやすく解説(事例付き)―
賞与(ボーナス)の時期になると、労務担当者の方から次のような相談をよく受けます。
- 「賞与の社会保険料の計算って給与と何が違うの?」
- 「退職予定の従業員に賞与を払う時はどうなる?」
- 「賞与支払届はいつまでに提出しないといけない?」
賞与の計算には“給与とは違う特有のルール”があるため、毎回悩みがちです。
この記事では、2025年度対応版として、賞与の計算〜賞与支払届の提出までの流れを、事例を交えてわかりやすく解説します。
1. 賞与とは?
賞与とは、名称にかかわらず 「年3回以下」支給される、労働の対償としての金品 をいいます。
年4回以上支給されるものは賞与ではなく、通常の給与(報酬)として扱われます。
例:
- 繁忙期手当 → 年3回以内 → 賞与扱い
- 期末手当 → 年1回 → 賞与扱い
- 住宅手当 → 毎月支給 → 給与扱い
2. 賞与計算の流れ(実務で押さえるべき3ステップ)
STEP1:賞与額の決定
賃金規程や評価制度に基づき、支給額を決めます。
STEP2:社会保険料の計算
賞与は「標準賞与額」を使います。
総支給額から1,000円未満を切り捨てた金額が標準賞与額です。
例:
賞与総額:525,500円 → 標準賞与額:525,000円
控除する保険料は以下のとおりです:
- 健康保険・介護保険(40〜64歳)
- 厚生年金(ただし70歳以上は不要)
- 雇用保険(総支給額×料率)
※注意:社会保険料の“上限”に注意
- 健康保険:年度累計573万円まで
- 厚生年金:1回150万円まで
上限を超えた部分には保険料をかけません。
STEP3:所得税の計算
前月給与を基準に源泉徴収税額表から計算します。
(前月給与がない/10倍超の場合は特例あり)
3. 賞与計算で “よく間違えるポイント” と対策
① 退職予定者への賞与の取扱い
退職日によって社会保険料の扱いが変わります。
✔ 事例
賞与日:12/10 退職日:12/20
→ 資格喪失日は12/21
→ 賞与から社会保険料は徴収しない
賞与日:12/5 退職日:12/31
→ 資格喪失日は1/1
→ 賞与から社会保険料を徴収する
② 育休・産休中の従業員に支給するとき
育児休業を「1か月を超えて連続取得」している期間の賞与は社会保険料免除。
※出産時育休(パパ育休)4週間のみでは免除にならない点に注意。
③ 40歳・65歳のタイミング
誕生日の前日に40歳/65歳に“到達”した月からルールが変わります。
- 40歳到達:介護保険料 徴収開始
- 65歳到達:介護保険料 徴収終了
1日生まれは特に間違いやすいため要注意。
④ 70歳以上の従業員
厚生年金の被保険者ではないため、厚生年金保険料は徴収しません。
4. 賞与支払届の提出(5日以内に必須)
賞与を支給したら 5日以内 に賞与支払届を提出します。
(提出を忘れると未納扱いとなり、督促の対象となるため注意)
■ 提出先
- 管轄年金事務所 または 事務センター
- e-Gov(電子申請)も可
■ 注意
賞与が「0」の場合でも、賞与不支給報告書の提出が必要です。
5. 【実務事例】実際によくあるケース5選
事例①:前月に産休に入った従業員に賞与を支給
状況
- 10月に産休開始
- 12月に賞与を支給
ポイント
前月給与がないため、源泉所得税の“特例計算”を適用。
社会保険料は免除。
事例②:退職予定者に賞与を支給
状況
- 12/20退職予定
- 12/10に賞与支給
結果
→ 社会保険料は徴収不要
→ 雇用保険料は徴収する(退職予定でも同じ)
事例③:賞与の支給が年4回
ルール上「給与扱い」になり、標準報酬月額に加算。
随時改定(月額変更)の対象になる可能性大。
事例④:年度累計573万円を超える賞与
健康保険料は「573万円まで」のみ対象。
超えた分には保険料はかからない。
事例⑤:70歳以上の従業員に賞与
- 厚生年金=徴収なし
- 健康保険=加入者なら徴収
- 雇用保険=加入していれば徴収
まとめ
賞与計算は、給与とは異なる独自ルールが多く、間違いやすいポイントが多くあります。
特に以下の点は要注意です。
- 標準賞与額の計算(1,000円未満切捨て)
- 社会保険料の上限
- 40・65・70歳の保険料の切替
- 退職・育休中の従業員への取扱い
- 賞与支払届の提出期限(5日以内)
正しい知識を押さえることで、スムーズに賞与計算を進めることができます。
📩 無料お問い合わせはこちら
賞与計算や社会保険手続きでお困りのことがございましたら、
社労士が丁寧にサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
👇 クリックしてすぐに問い合わせできます。