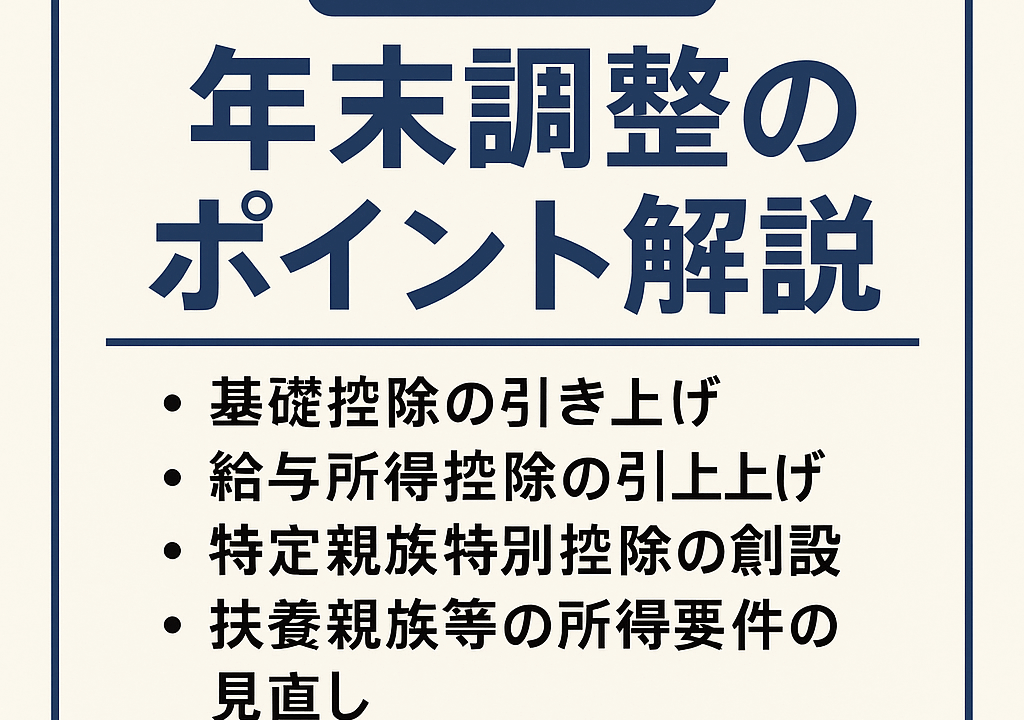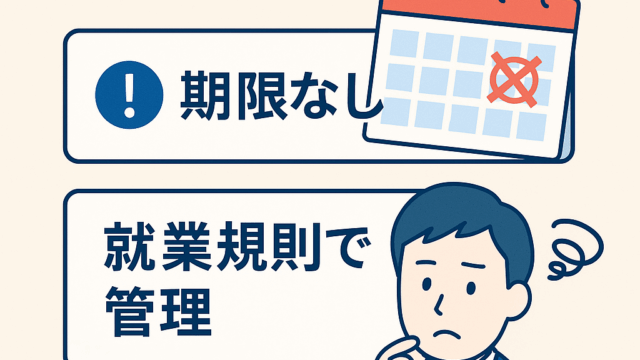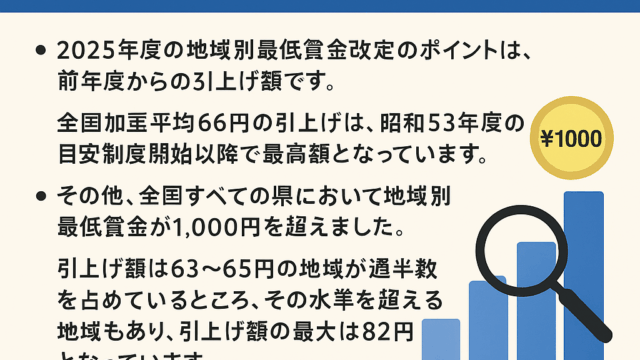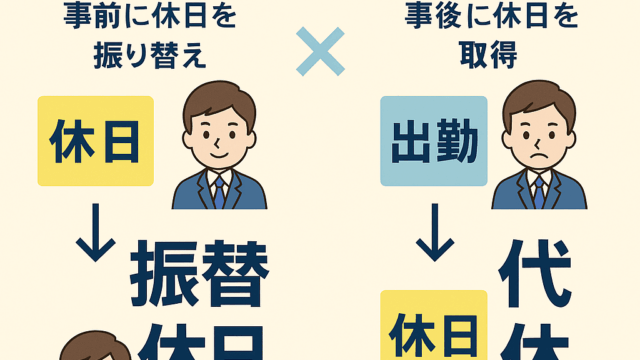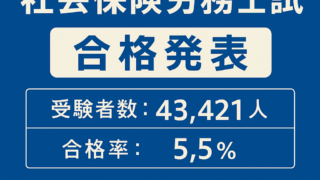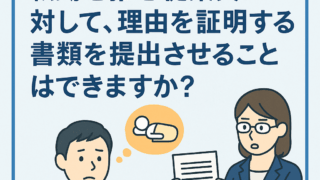こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
令和7年の年末調整では、令和6年に話題となった「定額減税」はありませんが、税制改正による基礎控除や給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の創設など、大きな改正点があります。
今回は、実務担当者が押さえておくべき5つのポイントを整理しました。
1. 基礎控除の引き上げ
基礎控除額が大幅に見直され、合計所得金額に応じて段階的に設定されました。
例:
- 所得132万円以下 → 95万円(従来48万円)
- 所得655万円以下 → 58万円(従来48万円)
※令和9年分以後は一律58万円となります。
➡ 実務では、給与支払報告書や年末調整計算時の控除額に影響します。
2. 給与所得控除の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が 55万円 → 65万円 に引き上げられました。
➡ 給与所得者の課税所得が減り、結果として税負担が軽減されます。
3. 特定親族特別控除の創設
19歳~23歳未満の大学生世代を対象に、新しい控除が設けられました。
- 所得85万円以下(給与収入150万円以下) → 親が63万円の控除を受けられる
- 所得85万円超 → 控除額が段階的に減少
➡ 学生アルバイトの「働き控え」を解消する目的があり、実務上は扶養控除の判定に注意が必要です。
4. 扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除引き上げに伴い、扶養親族の所得要件も変更されました。
- 扶養親族・配偶者 → 58万円以下
- 勤労学生 → 85万円以下
- 配偶者特別控除の対象 → 58万円超~133万円以下
➡ 特に「扶養に入れるかどうか」の判定に直結するため、年末調整の確認ポイントとなります。
5. 年末調整関係書類の様式変更
令和7年分以降の年末調整関係書類が改正されています。
- 「特定親族特別控除申告書」が新設
- 定額減税に関する記載欄を削除
- 各種金額の表が改正後の内容に修正
➡ 書式の差替え・システム対応が必要です。
【事例紹介】
事例A:学生アルバイトを扶養に入れられるか?
22歳の大学生が年間収入140万円(給与所得換算で85万円以下)。
➡ 新設された「特定親族特別控除」により、親は従来どおり63万円の控除を受けられる。
事例B:配偶者特別控除の判定
配偶者の所得が120万円の場合。
➡ 新要件(58万円超~133万円以下)に該当するため、配偶者特別控除の適用が可能。
まとめ
- 令和7年は「基礎控除」「給与所得控除」の引き上げで課税最低限が大幅に緩和
- 新設「特定親族特別控除」で大学生世代の扶養判定に注意
- 書類様式変更に伴い、事前準備(従業員への案内・システム改修)が必須
📌 年末調整や扶養判定でお困りの企業様へ
実務対応や従業員説明のサポートも承っております。お気軽にご相談ください。