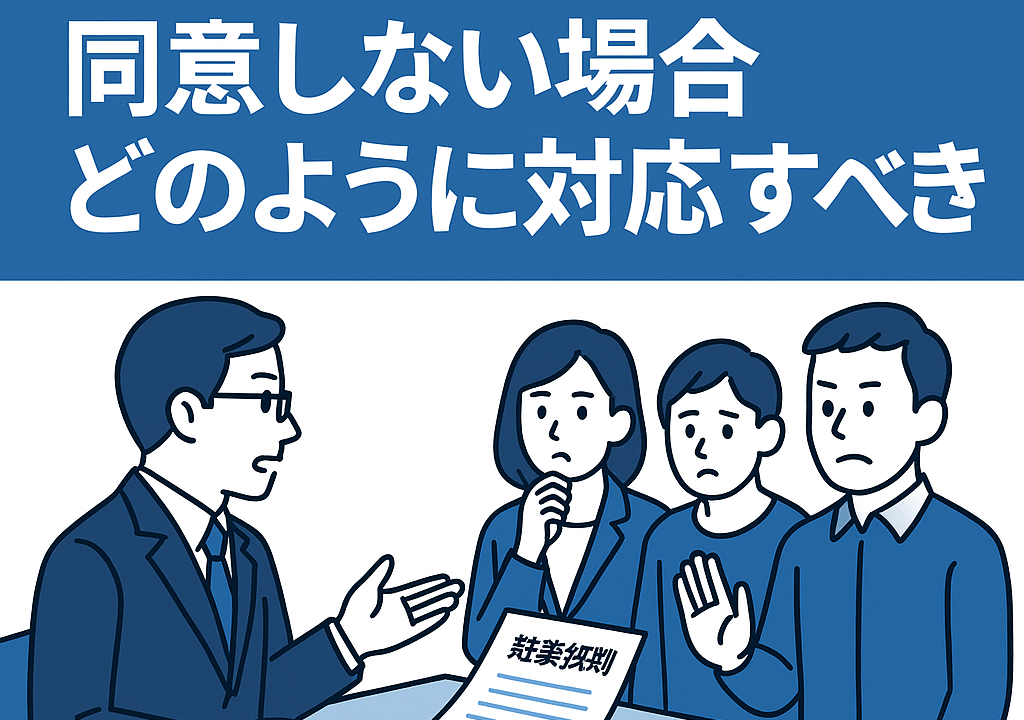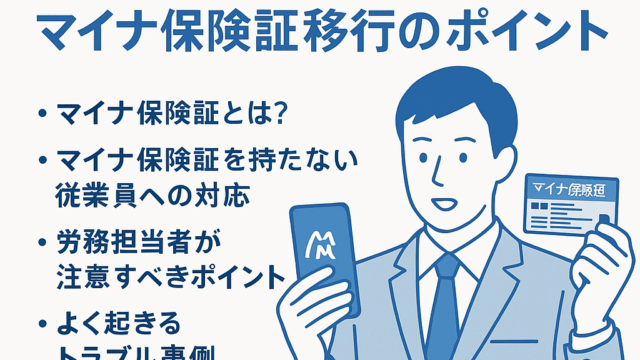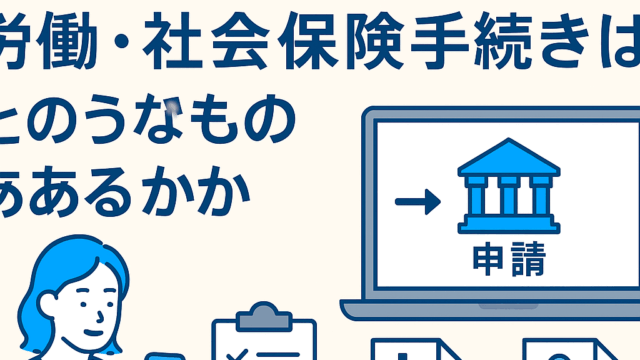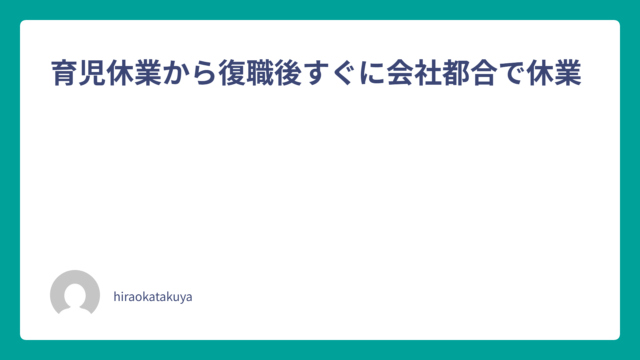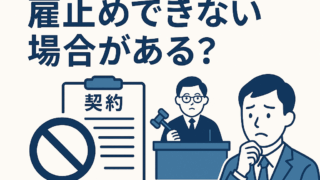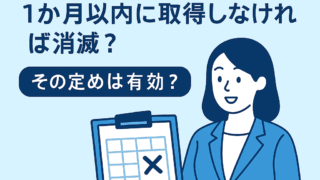こんにちは。ひらおか社会保険労務士事務所です。
就業規則を変更しようとした際、
「一部の従業員からは合意が得られたが、全員の合意が取れない…」
という場面は少なくありません。
特に、退職金制度の見直しや手当の廃止など、
不利益を伴う変更 の場合、慎重な対応が求められます。
今回は、合意が分かれたときに企業はどう動くべきかを、実務目線で解説します。
✅ 結論:まずは合意形成を最優先。それでも無理なら「就業規則による変更」が可能か検討
| ステップ | やるべきこと |
|---|---|
| ① 合意しない従業員と話し合い | 理由・懸念の確認 |
| ② 規則案の修正検討 | 実務上の落とし所を探る |
| ③ 合意形成できない場合 | 労契法9・10条に基づき、一方的変更の可否を判断 |
🗣️ まず行うべきは「対話」と「懸念の把握」
合意が得られない従業員には、以下のような懸念が隠れています。
| よくある拒否理由 | 企業側の対応 |
|---|---|
| 手当が減るのが不安 | 経過措置・補填の検討 |
| 説明が不十分 | 対話・説明会の開催 |
| 特定の人だけ不利益では? | 全員共通ルールであることの説明 |
⚖️ 「どうしても合意できない」場合に検討する法的手段
労働契約法 第9条・第10条において、一定の要件を満たせば 従業員の個別同意がなくても就業規則で労働条件を変更することが可能 とされています。
🔍 裁判所が判断する 5つの要素(不利益変更の合理性判断)
| 判断要素 | 内容 |
|---|---|
| ① 不利益の程度 | 減額幅・影響の大きさ |
| ② 必要性 | 経営維持・制度整合性 |
| ③ 内容の相当性 | 社会通念上妥当か |
| ④ 交渉状況 | 説明努力・協議実績 |
| ⑤ その他事情 | 経過措置・代替策の有無 |
🏢【事例】退職金制度を廃止した会社のケース
背景:経営悪化により退職金制度を見直し
従業員の合意:一部の社員は同意、他は反対結果:
- 会社は半年間説明会を実施
- 経過措置を導入(既得部分は保障)
→ 裁判所は「合理的」と判断し、不利益変更を有効と認めた。
⚠️ 注意:同意を得ていない従業員だけ旧制度のままにする方法は?
原則として同じ就業規則で統一運用すべきです。
人によって制度が異なれば、職場の平等性や秩序が崩れる恐れがあります。
🧭 社労士が推奨する実務対応
| 優先順位 | 対応 |
|---|---|
| 🥇 第1 | 合意形成(対話・修正・補償) |
| 🥈 第2 | 合理的ルール化(経過措置) |
| 🥉 第3 | 最終判断としての就業規則改定(法的検討) |
💬 社労士からのひとこと
就業規則の不利益変更は「説明と納得」が鍵です。
法律だけでなく、人の気持ちにも配慮することで、職場の信頼を守れます。
📩 規程変更・説明文書・同意書の作成でお困りですか?
初回相談は無料です。
業種や実情に応じた「実務的に通る就業規則改定」をサポートします。