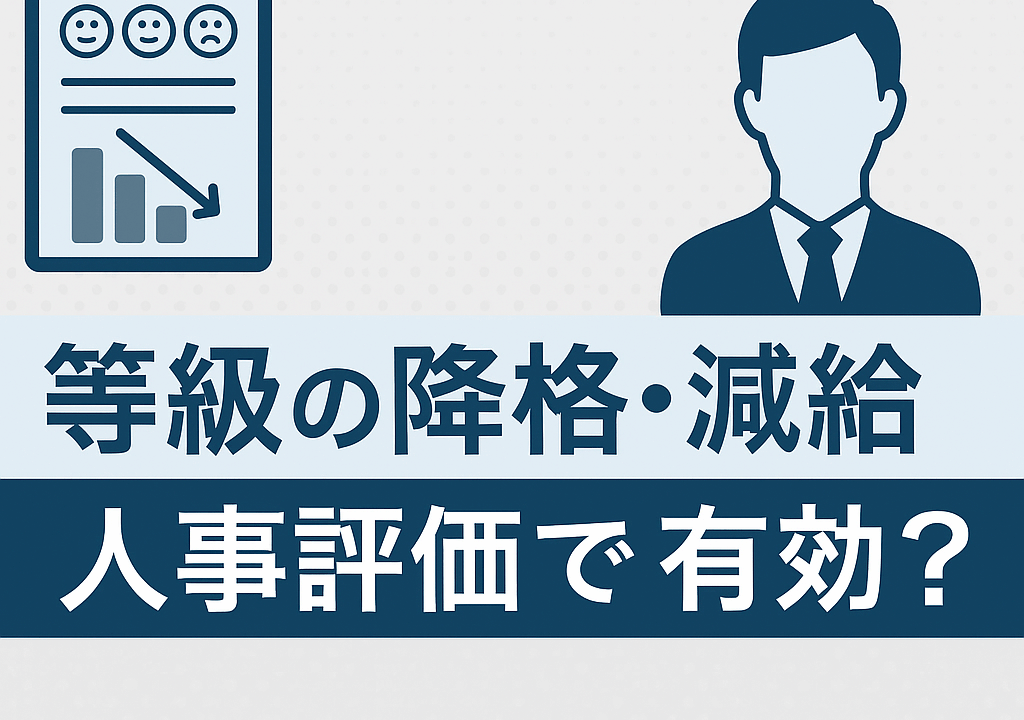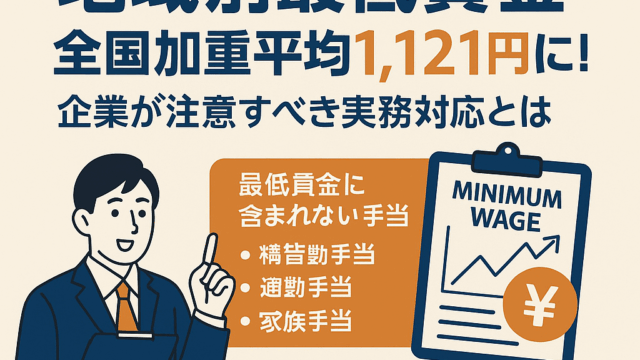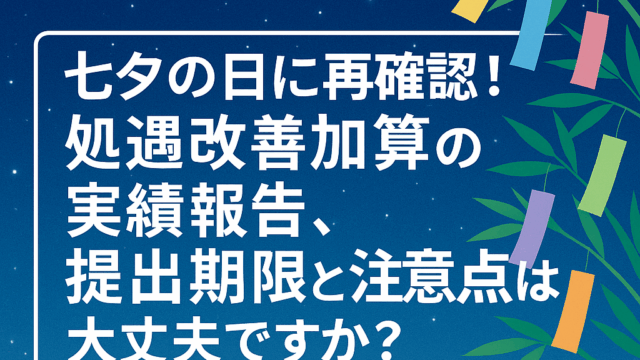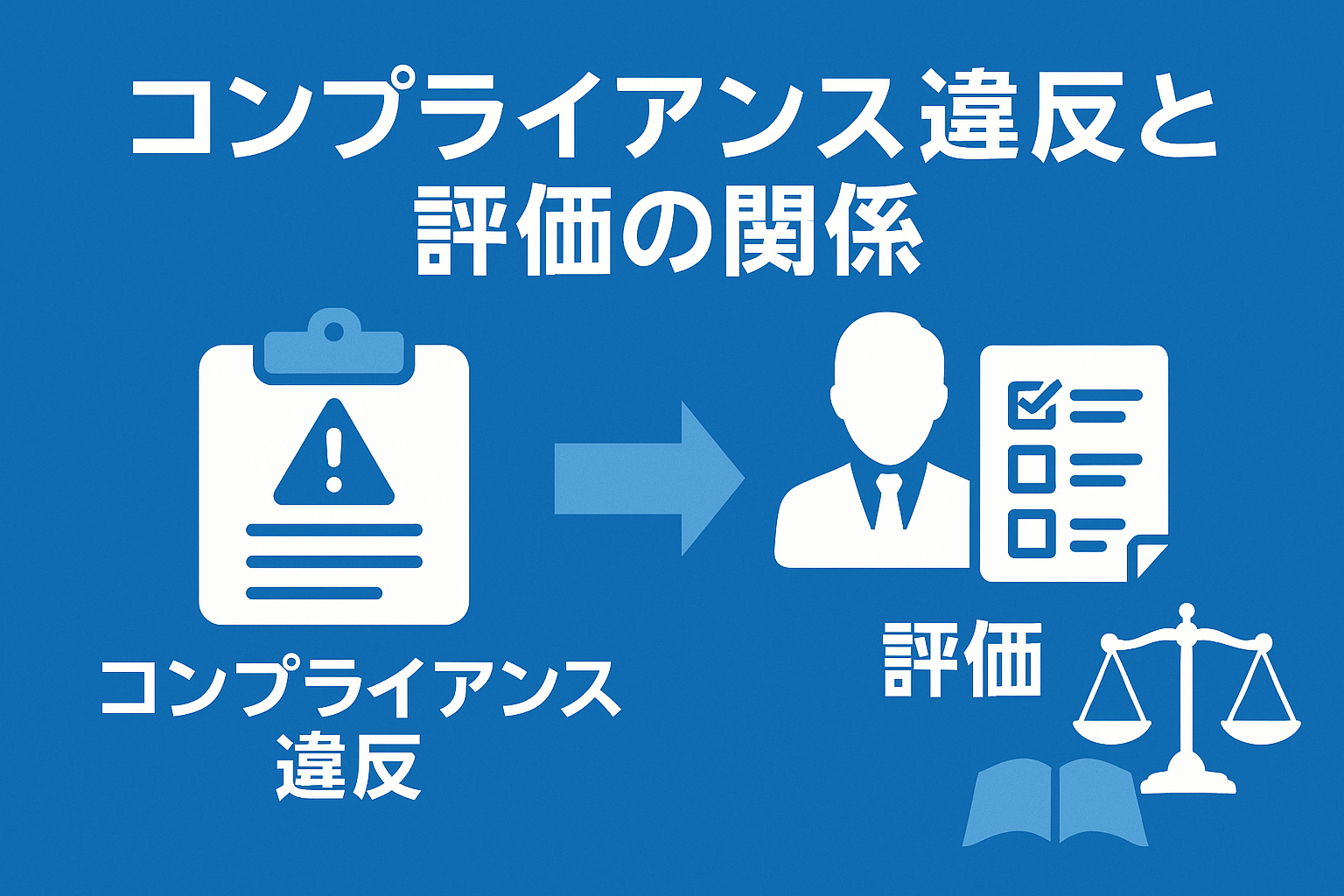「人事評価の結果が低かったから職能等級を下げたい」
「昇格や降格を評価制度に基づいて運用しているが、減給に問題はないか」
──こうしたご相談は、評価制度を運用する企業で非常に多いテーマです。
結論から言えば、就業規則等に根拠があり、かつ評価が合理的に行われていれば有効ですが、
手続や基準が曖昧な場合は、無効と判断されるリスクがあります。
■ 1.降格・降級を行うには「明確な根拠」が必要
職能資格制度を採用している会社では、
従業員の能力・職務遂行レベルに応じて「等級」を設定することが一般的です。
しかし、職能資格等級を下げる(降級)場合には、
就業規則または労働契約上にその根拠が明記されている必要があります。
📘 例:就業規則に次のような規定がある場合
「勤務成績または能力が著しく劣ると認められるときは、降格・降級を命ずることがある。」
このように規定に基づいて適正に運用されていれば、降格命令が認められる可能性があります。
■ 2.評価制度の合理性が問われる
就業規則の定めがあっても、次のような場合には問題が生じます。
- 評価基準が曖昧で、どのように評価されたか説明できない
- 上司の主観や個人的感情に基づいた評価
- 客観的なデータや事実に基づかない査定
- 降格や減給の手続きが本人に説明されていない
これらに該当すると、評価制度の運用が不合理と判断され、
結果として降格・減給が無効とされるおそれがあります。
■ 3.【判例紹介】A社(職能資格等級の降格)事件
〈概要〉
A社では職能資格制度を導入しており、評価の結果により昇格・降格を決定していました。
ある社員に対して「職務遂行力が不足している」として1等級降格・減給を命じたところ、
社員が「評価が不当であり、降格は無効」として訴えを提起しました。
〈裁判所の判断〉
裁判所は、
- 就業規則に降格の定めがあった点
- 評価制度の運用が一定の合理性を有していた点
を踏まえ、降格は有効と判断しました。
ただし、同時に、
「評価制度が客観的かつ公正に運用されていない場合には、
降格・減給が権利濫用に当たる」
と指摘しています。
■ 4.【実務事例】中小企業B社のケース
B社では職能資格制度を導入し、半年ごとに人事評価を実施していました。
ある社員が2期連続で最低評価を受け、上司は「降格+基本給5%減」を決定。
しかし、
- 評価表に具体的な記録がなく、
- 部下の聞き取り内容に誤りがあったことが後から判明。
このため、本人から「評価が不当」との申立があり、結果的に会社が処分を撤回しました。
B社ではその後、
- 評価の基準とプロセスを明文化
- 面談記録を保存
- 評価者研修を実施
することで、再発防止を図りました。
■ 5.実務でのポイント
- 就業規則に「降格・降級の定め」を明記する
→ 「勤務成績が著しく劣る場合」などの文言を入れる - 評価基準を数値・行動指標で明確に
→ 主観的評価にならないようにする - 評価プロセスの説明責任を果たす
→ 面談記録や評価票を残す - 処分内容の妥当性を確認する
→ 減給は「労基法91条」の制限(1回10分の1/月20分の1)にも注意
■ 6.まとめ
人事評価を理由とする降格・減給は、
就業規則に根拠があり、合理的に運用されていれば有効です。
しかし、評価基準が不明確であったり、主観的判断に基づくものである場合、
無効とされるリスクが高まります。
✅ 就業規則の明確化
✅ 評価制度の運用ルール化
✅ 記録と説明の徹底
この3点を整えることが、トラブルを防ぐ第一歩です。
💡 人事評価制度・就業規則の見直しをサポートします
降格・昇格のルールを明文化し、評価制度を公正に運用するための体制づくりを支援します。
中小企業に合った人事評価制度の導入もご相談ください。