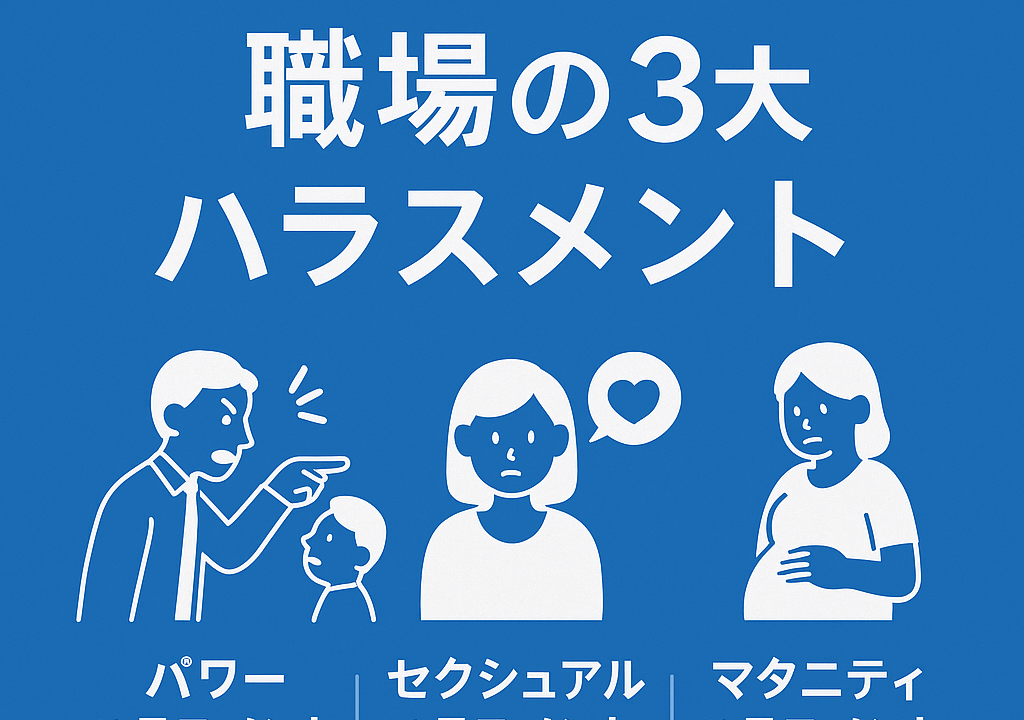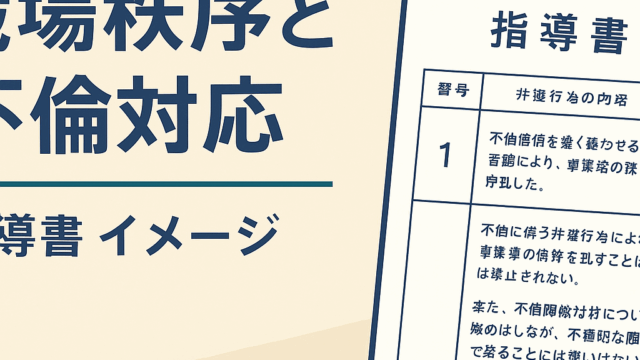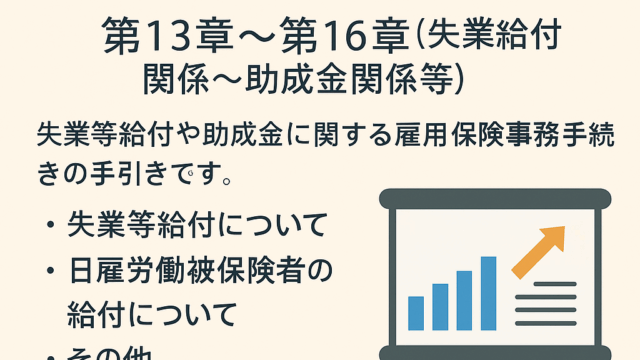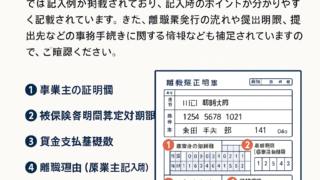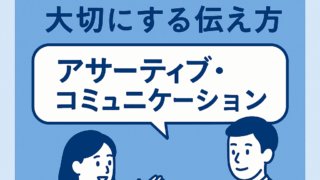~無意識のうちに加害者にならないために~
1.職場の「3大ハラスメント」とは
職場で問題となる3つの代表的なハラスメントは以下のとおりです。
- パワーハラスメント(パワハラ)
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- マタニティハラスメント(マタハラ)
いずれも、相手がどう感じるか」が重要です。
自分では「指導」「冗談」「気づかい」のつもりでも、相手を傷つけたり、職場の雰囲気を壊してしまうケースがあります。
2.それぞれの定義と具体例
パワーハラスメント(パワハラ)
定義:
優越的な立場を利用して、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、相手の就業環境を害すること。
具体例:
- 感情的に怒鳴りつけ、人格を否定するような叱責を繰り返す
- 特定の従業員を無視・排除して孤立させる
- 過大・過少な業務を意図的に与える
- 私的な雑用を強制する
💡 実務の注意点:
「厳しい指導」と「パワハラ」は紙一重。
目的が業務上の成長支援か、それとも感情の発散かを自問することが大切です。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
定義:
職場で性的な言動を受け、拒否や抵抗により不利益を受けたり、不快な職場環境が生じること。
※異性だけでなく、同性間のセクハラも該当します。
具体例:
- プライベートに踏み込む質問(恋愛・結婚・外見など)
- 肩や背中に触れるなどのスキンシップ
- 性的な冗談を言う、SNSでの不適切な発言
💡 実務の注意点:
「冗談のつもりだった」は通用しません。
相手が不快と感じた時点でハラスメントです。
マタニティハラスメント(マタハラ)
定義:
妊娠・出産・育児休業などに関する言動により、就業環境が害されること。
具体例:
- 「育休は取らない方がいい」と助言する
- 「また妊娠?」などの発言をする
- 本人に相談せず、仕事量を大幅に減らす
💡 実務の注意点:
「配慮のつもり」が「差別」になることも。
本人の意思を尊重した対応を心がけましょう。
3.ハラスメントがもたらす影響
| 対象 | 主な影響 |
|---|---|
| 被害者 | メンタル不調、モチベーション低下、退職リスク |
| 加害者 | 懲戒処分・民事責任(損害賠償)・刑事罰 |
| 周囲の従業員 | 職場不信・チーム崩壊・雰囲気悪化 |
| 会社 | 生産性低下・離職率上昇・社会的信用の喪失 |
💡 「誰も得をしない」のがハラスメント。
企業にとっても重大なリスク要因です。
4.注意すべきシーン
勤務時間中だけでなく、以下のような場面でも注意が必要です。
- 社内の懇親会・飲み会
- 社内イベント(運動会・旅行など)
- 休憩室での雑談
- SNSでの発言やメッセージのやり取り
お酒の席や冗談でも、相手を不快にさせる言動はNGです。
「みんなやっているから」「昔は普通だったから」という考え方は通用しません。
5.【実例】実務で起きたハラスメント相談
事例①:励ましのつもりがセクハラに
男性上司が、部下の女性に「頑張ってるね!」と肩を叩いた行為がセクハラ相談に。
➡ 本人に悪気はなくても、「触れられたくなかった」と感じたことでトラブルに発展。
ポイント:
励ます場合は、言葉で伝えるようにしましょう。
事例②:育休復帰後の「配慮」がマタハラに
育児復帰した女性に仕事を任せず、「負担を減らしてあげよう」と判断した上司。
➡ 本人は「成長の機会を奪われた」と感じ、退職に至った。
ポイント:
配慮する場合も、本人の希望を確認することが大切です。
6.ハラスメントを受けたと思ったら
1人で抱え込まず、すぐに上司や社内の相談窓口に相談しましょう。
社内に相談しづらい場合は、労働局や外部相談窓口を利用することも可能です。
すべての会社には「パワハラ・セクハラ・マタハラの相談窓口」の設置が義務付けられています。
7.まとめ
ハラスメントは「意図の有無」ではなく、「相手の受け止め方」で判断されます。
日常のコミュニケーションの中でも、相手の尊厳を大切にする意識が何よりも重要です。
「ちょっとした言葉」「何気ない態度」こそ、注意していきましょう。
📞 ハラスメント防止研修・社内相談体制の構築なら
ひらおか社会保険労務士事務所では、
ハラスメント防止研修や相談窓口体制の整備など、職場の安心づくりをサポートしています。