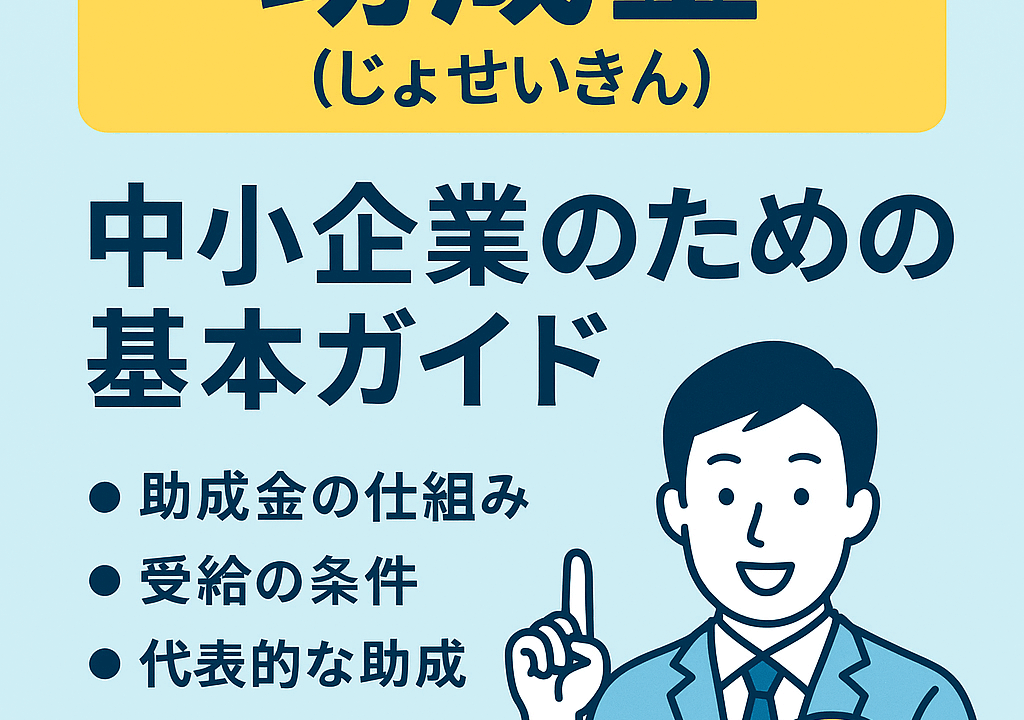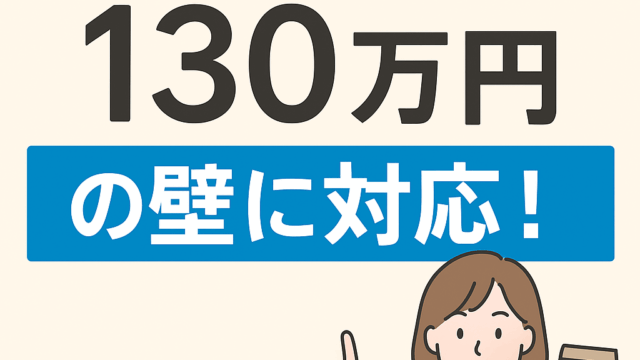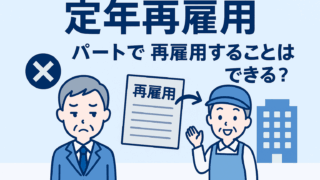「助成金って聞いたことはあるけど、うちは関係ないと思ってる」
「手続きが大変そう」
―そう思っている会社は、もったいないです。
中小企業・クリニック・介護事業所でも、実はかなりの確率で使えるのが“雇用関係助成金”です。
この記事では、はじめての方にもわかるように
- 助成金とは何か
- どんな会社がもらえるのか
- どんな準備が必要なのか
- よくある失敗
まで、実務目線でやさしく解説します。
1. 助成金とは?
助成金とは、国や自治体が企業や個人に「こういう取り組みをしてくださいね」という目的でお金を支援する制度です。
いちばん大きな特徴はこれです。
👉 返済不要(返さなくていい)
銀行融資や借入金とは違い、あとで返す必要はありません。
ただし、「一定の条件を満たした会社・取り組み」にしか支給されません。
たとえば、
- 非正規社員を正社員にした
- 男性社員に育休を取ってもらった
- 最低賃金を上げたうえで設備を入れ替えた
こういった取り組みに対して企業が申請し、条件を満たしていれば支給される、という仕組みです。
※「補助金」とよく似ていますが、ちがいもあります。補助金は「審査で選ばれる・採択される」ことが多く、申し込んでも必ずもらえるわけではありません。一方、助成金は“条件を満たせば原則支給”という考え方です。
2. 助成金の目的は「会社をよくすること」
助成金は、単なるばらまきではありません。目的があります。代表的なのは次の4つです。
- 雇用を守る
- 働きやすい職場をつくる
- 社員を育てる(教育・スキルアップ)
- 生産性を上げる
つまり、会社にとっても従業員にとっても“プラスになる取り組み”を応援する仕組みです。
「義務だからやる」ではなく、「やったほうが会社のためになること」にお金が出るイメージです。
3. 助成金をもらうための基本条件(ここが一番大事)
「うちは申請できますか?」と聞かれたとき、まず確認するのはここです。
以下の条件を満たしていないと、ほとんどの助成金は受けられません。
- 労災保険・雇用保険に入っていること
- 従業員を雇ったら、本来どちらも必要です。
- 役員だけの会社(従業員ゼロ)は対象外です。
- 雇用保険に入っている従業員が1名以上いること
- パートさんでも、週20時間以上・31日以上働く見込みがあれば加入対象です。
- そこに未加入だとアウトになります。
- 労働保険料をきちんと納付していること
- 滞納があると支給されません。
- 労務管理の書類がそろっていること
- 出勤簿(タイムカードなど)
- 賃金台帳(給与明細の元になる一覧)
- 雇用契約書 or 労働条件通知書
- 就業規則(従業員10名以上の事業場は義務)
これらが揃っていないと“そもそも申請できない”ことがあります。
- 法律を守っていること
- 残業代の未払いがないこと
- 長時間労働の放置がないこと
- 有給休暇の義務付与ができていること、など
- 直近に「会社都合退職(解雇)」がないこと
- いわゆる離職票で「1A」「3A」とされる会社都合の離職があると、しばらく対象外になる助成金があります。
💡ポイント
助成金は「紙を書けばもらえるお金」ではありません。
日ごろの労務管理がきちんとしている会社に支給されるお金です。
4. これからはじめて助成金を使いたい会社がやること
「社員を初めて雇いました。助成金もらえますか?」というご相談は本当に多いです。
その場合、次の準備が必須です。
① 社会保険手続きを整える
- 労災保険は、従業員を雇ったら必ず加入。
- 雇用保険は、週20時間以上+31日以上の雇用見込みがある従業員から加入。
→ ここを後回しにしている会社は、助成金の入口で止まります。
② 就業規則を用意する
- 従業員10人以上の事業場は「就業規則を作成し、労基署へ届出」が義務です。
- 10人未満でも、就業規則があると助成金申請がスムーズな場合があります(特に育休や正社員転換など制度系)。
③ 書類を残すクセをつける
- 雇用契約書は口頭ではなく、必ず書面で交わす
- 出勤簿・賃金台帳は「なんとなく」ではなく、記録として残す
- 有給の付与日・残数も管理する
これらは「後からまとめて出してください」と言われる書類そのものです。
逆にいうと、最初から整えておけば、申請で慌てません。
5. 助成金にはどんな種類があるの?
厚生労働省の雇用関係助成金だけでも、毎年70種類ほどあります。
ざっくり分けると、次の8つのジャンルです。
- 採用・正社員化に関するもの
- 研修・人材育成に関するもの
- 雇用を維持するもの(休業手当など)
- 働き方改革・労働時間の見直し
- 障害のある方の雇用
- 高齢者の継続雇用
- 育児・介護と仕事の両立
- 安全・衛生・健康(メンタルヘルスなど含む)
「うちがもらえる助成金はどれ?」というときは、どのジャンルに当てはまる取り組みをやっているかを見ると早いです。
6. よく使われる代表的な助成金(現場で本当に相談されるもの)
ここは実務の現場でニーズが高いものを紹介します。
① キャリアアップ助成金
対象:パート・アルバイト・契約社員などの“非正規”の方を正社員にした会社
内容:正社員化・賃金規程の整備・賞与制度や退職金制度の導入などに対して助成
▶ よくある事例
介護事業所A社では、1年以上働いているパート職員を正社員として登用しました。
登用後の基本給を上げ、就業規則や賃金規程も整備したところ、一定額の助成金の対象となりました。
「もともと戦力の人を正社員にする」という日常的な人事が、助成の対象になるイメージです。
✓ ポイント
・実際に正社員にする前の段階から計画が必要(あと出しは通らないことが多い)
・雇用契約書、賃金規程など証拠書類がそろっていることが必須
② 人材開発支援助成金
対象:従業員に研修や資格取得のための教育訓練を受けさせる会社
内容:研修費用や研修中の賃金の一部を助成。いわゆる“リスキリング”も対象になる。
▶ よくある事例
製造業B社では、新しい生産ラインを導入するにあたり従業員に専門の外部研修を受講させました。
研修費用(講座代など)と、研修中に支払った賃金の一部が助成の対象となりました。
「教育コストが重いから研修を後回しにしたい」という会社ほど相性がいい助成金です。
✓ ポイント
・研修内容が仕事に関連していること
・“研修をやりました”の証拠(カリキュラム、出席記録など)が必要
③ 両立支援等助成金
対象:育児休業・介護休業を取りやすい制度を整えたり、実際に休業を取得させたりした会社
内容:男性育休の取得促進、職場復帰の支援などに助成金が支給される
▶ よくある事例
建設業C社では、男性社員が赤ちゃんの誕生に合わせてまとまった育休を取れるように制度を整備し、実際に取得・復帰までサポートしました。
この取り組みが助成対象となり、支給決定を受けました。
「男性育休をちゃんと取らせたいけど、現場が回るか心配」という会社でも活用されています。
さらに、2025年度からは
「不妊治療や月経・更年期など、女性の健康課題に配慮した勤務制度」を整える企業向けのコースも始まっています。
これまで“育児だけ”だった支援の対象が、より広くなってきています。
✓ ポイント
・社内に「方針を書面で周知したか?」がかなり重視される
・形だけでなく、実際に取得実績が必要なコースも多い
④ 業務改善助成金
対象:最低賃金に近い水準の賃金で働く従業員の時給を引き上げ、生産性向上のために設備投資などを行う中小企業
内容:その設備投資費用などの一部を助成
▶ よくある事例
飲食店D社では、レジ・受注業務をタブレットオーダーに切り替え、同時にキッチンの人件費負担を減らす導線改善を行いました。
一方で、パートさんの時給を地域の最低賃金より高い金額に引き上げました。
この「時給を上げる+生産性を上げる」セットが助成対象になりました。
✓ ポイント
・“賃上げだけ”でも“設備だけ”でもダメで、両方がセット
・導入する機器・制度が生産性向上に関連していることの説明が必要
7. 申請のときによくあるトラブル(失敗例)
正直ここが一番もったいないポイントです。
- タイムカードがバラバラで、実働時間が証明できない
- 雇用契約書が口頭の約束のまま
- 残業代を払っていない(未払いがある)
- 退職トラブルで「会社都合退職」にしてしまった
- 申請期限を過ぎてから相談に来る(申請は“事後”ではなく“事前準備が必要”なものが多い)
特に「残業代の未払い」が見つかると、審査が止まる・不支給になることがあります。
これは中小企業でもかなりシビアに見られます。
8. よく聞かれる質問
Q. 助成金は何に使わないといけないんですか?用途は決まってますか?
→ 多くの助成金は、受け取った後のお金の使い道は縛られません。報告義務もありません。
設備投資に再投資してもいいし、運転資金に回してもかまいません。
Q. いつ入金されますか?
→ すぐではありません。申請から振込まで3〜6か月ほどかかるのが一般的です。
また、振込日はこちらで指定できません。
Q. 一度もらったらもう終わり?
→ 助成金によっては、同じ制度を複数回活用できるものもあります。
ただし回数制限があるものもあるので、個別確認が必要です。
Q. 毎年同じ内容ですか?
→ いいえ。助成金は“年度もの”です。
毎年4月〜翌年3月の間で、内容・金額・対象条件が変わることがあります。
そもそも制度ごと廃止・新設されることもあります。
「去年もらえたから今年も同じ」は通用しないので、最新の情報確認が必須です。
9. 電子申請は進んでいます
昔は紙での申請・郵送・窓口持参が当たり前でしたが、今はかなり変わっています。
- 厚生労働省「雇用関係助成金ポータル」からオンライン申請ができる
- e-Gov経由で申請できるものもある
- 申請の進捗状況や過去の申請履歴もオンラインで確認できる
- 事務負担が下がるので、地方の事業所や小規模事業者でも使いやすくなっている
使うには「GビズID(事業者向けID)」の取得など、事前のアカウント準備が必要です。
ここも初めての会社さんにはハードルになるところなので、専門家に任せる部分でもあります。
10. 相談先はどこ?
助成金についての公式な相談窓口は、
- 各都道府県労働局
- 管轄のハローワーク(公共職業安定所)
です。
制度の説明・必要書類・スケジュール感などを教えてくれます。
一方で、「この社員を正社員化するタイミングで申請できますか?」「うちの就業規則これで大丈夫ですか?」といった、より実務的で会社ごとの内容は、社会保険労務士など専門家に相談されるケースが多いです。
なぜなら、助成金は“テクニック”ではなく“労務管理そのもの”だからです。
まとめ:助成金は「今の働き方」を整える会社ほど使える
助成金は、“裏ワザ”ではありません。
ちゃんと雇って、ちゃんと育てて、ちゃんと休ませて、ちゃんと賃金を払う会社を後押しする制度です。
つまり――
「いい会社にしようとしている会社」ほど取りやすいお金です。
逆に言うと、
- 雇用保険に入れていない
- タイムカードがない
- 残業代があやしい
こういう状態だと、そもそも入口で止まります。
今の会社のやり方で「どの助成金が使えるのか」「まず何から整えればいいのか」は、業種や人の配置によって全く変わります。
【初回相談無料】うちの会社はどの助成金が使えますか?専門家に相談する