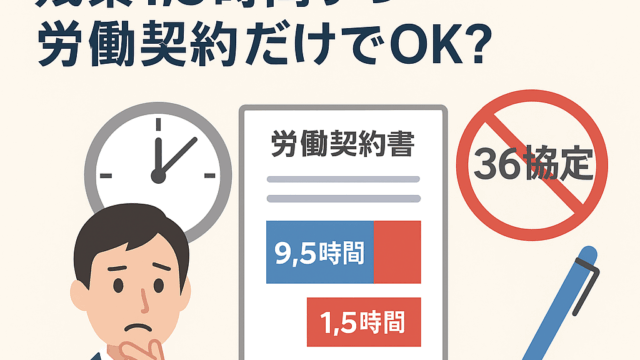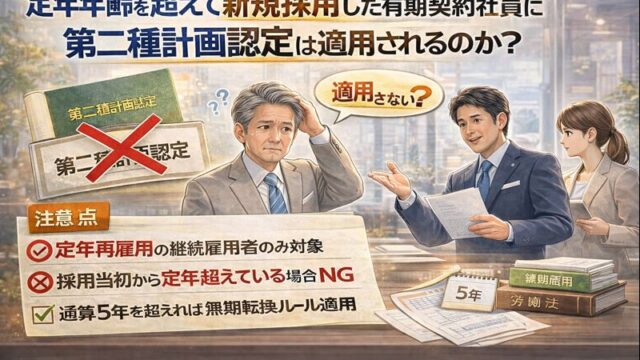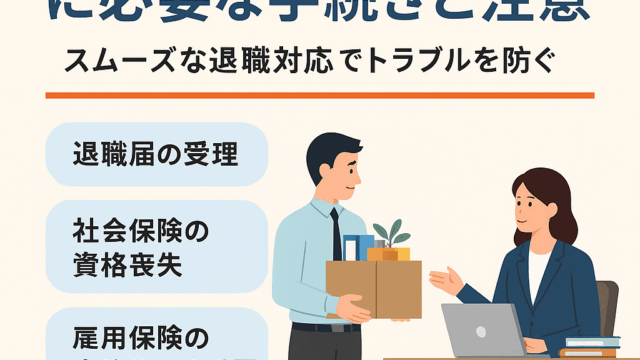企業が労働者を即時解雇したい場合、「解雇予告除外認定」という制度を利用できることがあります。
しかし、この制度を労働基準監督署が認めた=解雇が正当と認められたと誤解してしまうケースが多く見られます。
この記事では、実際の運用やトラブル事例を交えて、正しい理解と実務上の注意点を解説します。
🔹「解雇予告除外認定」とは?
労働基準法第20条では、労働者を解雇する際には少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金の支払い(解雇予告手当)が必要とされています。
しかし、以下のような例外的な場合には、労働基準監督署長の認定を受けることで、予告や手当の支払いが免除されることがあります。
📝除外認定の主な例
- 重大な背信行為(横領、暴行、著しい職務懈怠など)
- 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合
このとき、事業主は「解雇予告除外認定申請書」を労働基準監督署に提出し、調査のうえ認定を受けることになります。
🔹誤解されやすいポイント:「除外認定=正当解雇」ではない!
💡ポイント
解雇予告除外認定は、あくまで「解雇予告手当を支払わなくてよい」という行政上の取扱いを示したものです。
決して、「この解雇は有効である」と法律的に判断されたわけではありません。
🔸つまり、除外認定=裁判で有効と認められる保証ではない、という点が非常に重要です。
労働基準監督署は、個別の労働契約の有効性を判断する権限を持ちません。
解雇の有効性について最終的に判断するのは裁判所です。
🔹実際にあった事例
事例①:窃盗行為を理由に即時解雇
従業員が会社の備品を持ち帰ったため、会社は「懲戒解雇」として解雇予告除外認定を申請。
労働基準監督署は「除外認定」を付与しました。
しかし、後に従業員が提訴し、裁判では「解雇は行き過ぎであり無効」と判断。
→ 除外認定があっても、解雇の有効性は否定されました。
事例②:無断欠勤・業務拒否による解雇
連続無断欠勤5日を理由に、即時解雇を実施。除外認定を受けたが、裁判では「会社側の指導・注意が不十分」として解雇無効の判決。
→ 監督署は「事実確認」しか行っておらず、実体的な判断はしていないことが明確になりました。
事例③:勤務態度不良による懲戒解雇(認定不許可)
従業員の勤務態度の悪さを理由に申請したが、監督署が「除外認定に該当しない」と判断。
→ 結果、会社は30日分の解雇予告手当を支払って解雇。
→ ただし、裁判上は懲戒解雇が「相当な理由あり」として有効認定された。
(認定の有無と裁判の結論が一致しない好例)
🔹実務担当者が押さえるべきポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解雇予告除外認定の効果 | 予告・手当の免除のみ(解雇の正当性とは無関係) |
| 認定の性質 | 行政上の「事実確認」にすぎない(法的拘束力なし) |
| 解雇の有効性判断 | 裁判所のみが判断権を有する |
| 実務対応 | 解雇理由の明確化・懲戒規程との整合・指導記録の保存が重要 |
🔹社労士の実務アドバイス
- 「除外認定=安心」と思い込まず、懲戒解雇の妥当性を冷静に検証する
- 解雇の前に、注意・指導・改善機会の付与を必ず行う
- トラブル防止のため、証拠書類(始末書、警告書、就業規則、指導記録)を整備しておく
- 可能であれば、社労士・弁護士に事前相談し、手続きを慎重に進める
🔹まとめ
| 誤解されがちな点 | 正しい理解 |
|---|---|
| 労基署の認定=正当な解雇 | ❌ 違います。除外認定は予告免除のみ |
| 除外認定があれば裁判で勝てる | ❌ 保証なし。裁判所が独自判断 |
| 除外認定を受ければ書類不要 | ❌ 証拠・記録の整備が必要 |
📘根拠法令・通達
- 労働基準法 第20条(解雇の予告)
- 昭和23年11月11日 基発1637号
- 昭和31年3月1日 基発111号
🟢無料相談・お問い合わせはこちら
懲戒解雇・除外認定の判断に迷ったら、専門家にご相談ください。
ひらおか社会保険労務士事務所では、トラブルを未然に防ぐ労務対応をサポートしています。
初回相談は無料です。