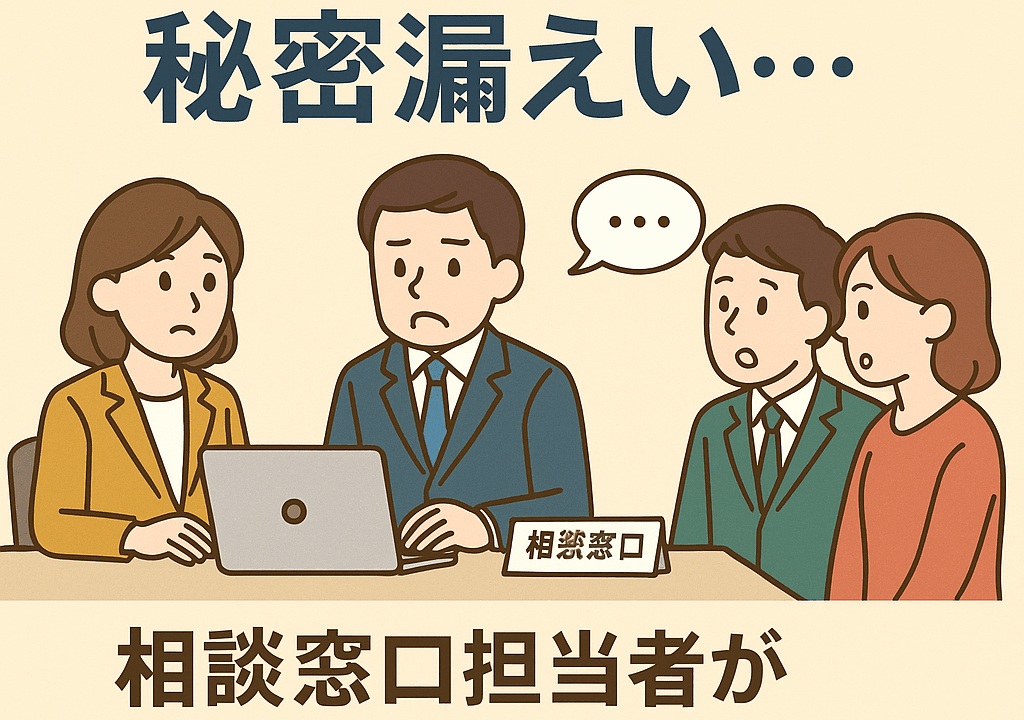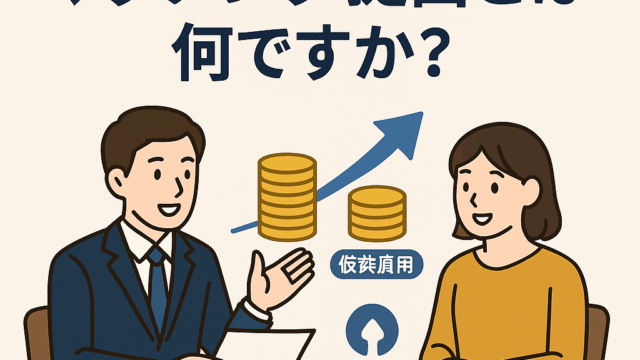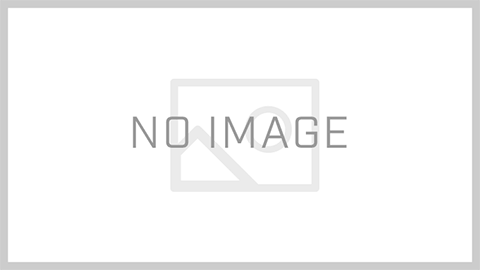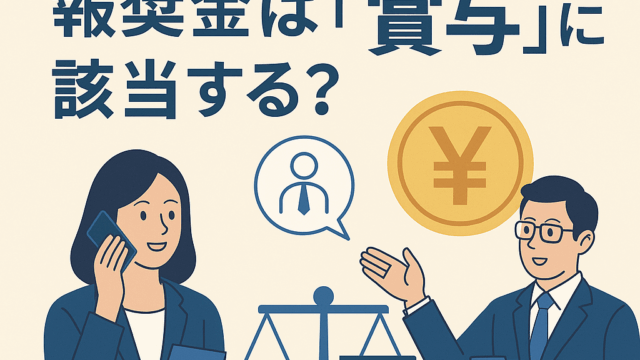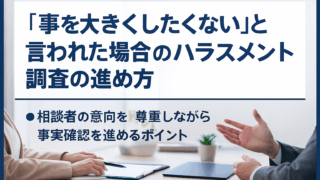ハラスメント相談窓口の担当者が、
相談者の内容を第三者に漏らしてしまう ケースは、実務上非常に重大な問題です。
結論から言うと、
相談窓口担当者による秘密漏えいは、会社の法的責任につながります。
本記事では、
- なぜ会社が責任を負うのか
- 想定される法的リスク
- 具体的な事例
- 企業が取るべき再発防止策
を社労士の視点でわかりやすく解説します。
■ なぜ会社が責任を負うのか?
ハラスメント防止法(労働施策総合推進法)および男女雇用機会均等法では、
企業に対し 「相談体制の整備」 や 「プライバシー保護」 を義務付けています。
つまり、
相談窓口の担当者は会社が選任した立場であり、
担当者の行動は会社の責任として扱われる ためです。
企業には、次のような義務があります:
✔ 相談内容の秘密保持
✔ 相談窓口担当者への教育・研修
✔ 適切な相談対応マニュアルの整備
✔ 社内ルールの明文化と周知
✔ 情報管理体制の構築
これらを怠り、
担当者が軽率に情報を漏らした場合、
会社が直接責任を問われるリスクがあります。
■ 想定される法的責任(企業側)
① 安全配慮義務違反
相談者が精神的ダメージを受け、メンタル不調に至った場合。
② ハラスメント防止措置義務違反
相談窓口体制が整備されていない、研修を実施していないなどの場合。
③ 損害賠償責任
情報漏えいによって相談者に不利益(精神的苦痛・退職など)が生じた場合。
慰謝料の支払い対象になるケースがあります。
④ 企業イメージの悪化
「相談したら情報が漏れる会社」という評判になると、
離職率の上昇・採用難につながるリスクも。
■【実務事例】実際に起きた情報漏えいケース
◆ 事例①:窓口担当者が同僚に“相談内容を雑談” → 精神不調に
相談者が上司のパワハラについて訴えたところ、
窓口担当者が「実はAさんから相談があって…」と雑談の中で他の従業員へ話してしまった。
結果:
- 相談者が職場に居づらくなり休職
- 会社は情報管理体制不備として責任を問われる
ポイント:
担当者の意識不足は、会社の研修不足として扱われる。
◆ 事例②:担当者が上司へ“相談内容を丸ごと報告”
相談者の許可を得ないまま、
加害者とされる上司へ相談内容をそのまま伝えたケース。
結果:
- 加害者が逆恨みし二次被害が発生
- 被害者が退職
- 法的トラブルへ発展
ポイント:
相談情報の扱いは「必要最小限」が原則。
◆ 事例③:パート社員の相談内容がSNSに漏えい
相談窓口担当者が家庭内で相談内容を話してしまい、
そこからSNSで広まり炎上したケース。
結果:
- 会社に重大な安全配慮義務違反の指摘
- 相談体制の不備が問題に
■ 企業が取るべき「再発防止策」
相談窓口担当者のミスを防ぐには、次の4点が非常に重要です。
✔ 1. 担当者向け研修の実施
- 秘密保持の重要性
- 相談者保護の考え方
- 情報管理の基本
- 実際の対応プロセス
✔ 2. 相談対応マニュアルの整備
- 相談受付の流れ
- 記録方法
- 外部への伝達ルール
- 情報の保管方法
- 緊急時対応
✔ 3. 就業規則・ハラスメント規程への明記
- 「相談内容の秘密保持」
- 「漏えいした場合の懲戒」
- 「相談者保護条項」
✔ 4. 情報へのアクセス制限
相談内容は
“担当者と事業主の一部のみに限定”
し、共有範囲を明確にする。
■ 根拠法令(企業の義務)
- 男女雇用機会均等法 第11条
- 男女雇用機会均等法 第11条の3
- 労働施策総合推進法 第30条の2
(相談体制整備・秘密保持の義務)
■ まとめ:相談窓口担当者のミスは「会社の責任」
相談窓口は、
従業員が安心して相談できることが大前提です。
情報漏えいは
- 相談者の信用を大きく損ない
- 二次被害につながり
- 会社が法的責任を問われる重大なトラブル
となります。
企業は必ず「教育」「マニュアル」「秘密保持」を徹底する必要があります。
▼ 無料相談(初回無料・企業向け)