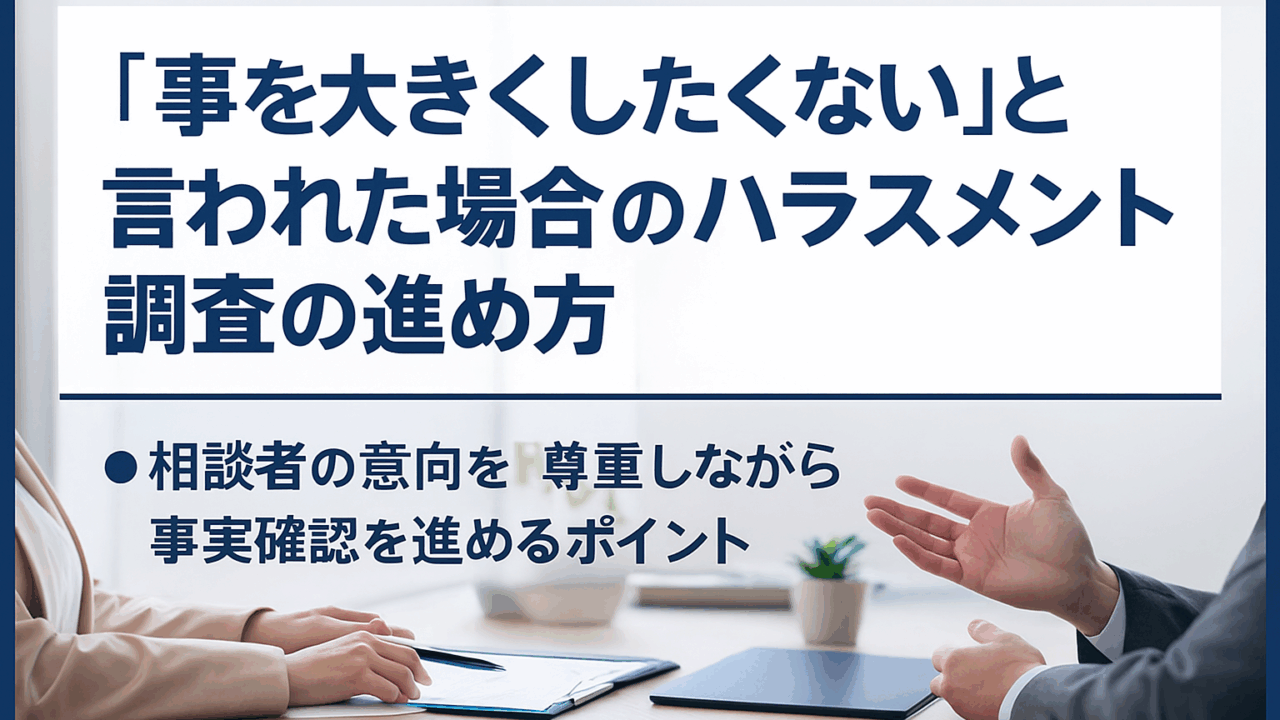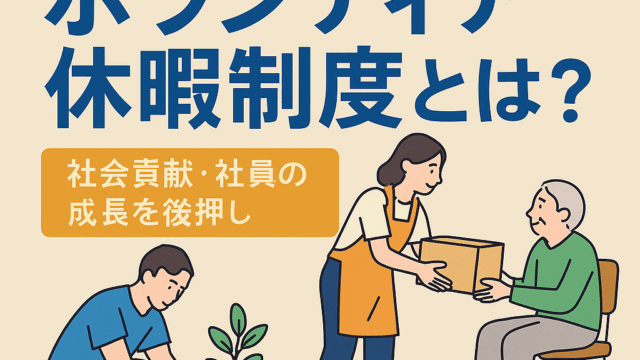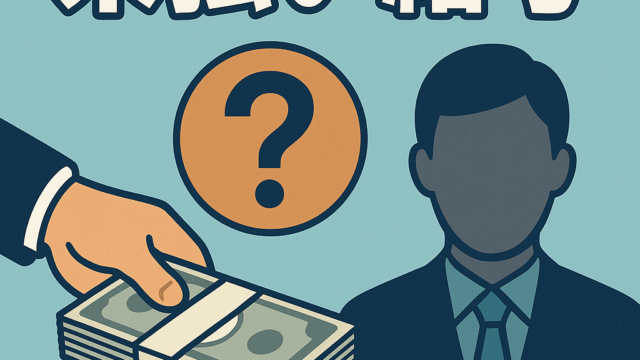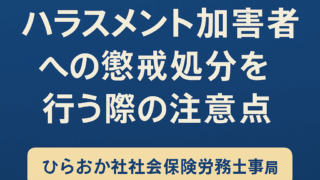職場でハラスメントの相談を受けた際、相談者から
「事を大きくしたくないので…」
と伝えられるケースは非常に多くあります。
しかし、相談者の意向を尊重しつつも、会社には
事実関係の確認・再発防止策を講じる義務
があります。
この記事では、相談者の負担を最小限にしながら、法令に沿って適切に対応するためのポイントをわかりやすく整理します。
1.まず結論:本人の意向を尊重しつつも、会社は調査義務を負う
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では、企業に対し以下が義務づけられています。
- 相談を受けたら迅速かつ正確に事実確認を行うこと
- 相談者のプライバシー保護
- 不利益取扱いの禁止
- 再発防止策の実施
つまり、
「事を大きくしたくない」という相談者の気持ちを尊重しつつ、必要な対応は必ず実施する必要がある
というのが法律上のポイントです。
2.「事を大きくしたくない」の意味を丁寧に確認する
最も重要なのは、相談者の意向を具体的にヒアリングすることです。
▼ヒアリングの例
- 誰に知られたくないのか?(上司、同僚、人事など)
- どこまでの調査なら許容できるか?
- 行為者への処分は望まないのか?
- 関係性の悪化が心配なのか?
- どのような状況が改善されれば安心できるか?
意向が曖昧なまま対応を進めると、「そんなつもりではなかった」というトラブルが起きやすいため、
「範囲」「目的」「期待する結果」を丁寧に確認しましょう。
3.必要最小限の調査で進める(プライバシー保護を徹底)
相談者の許容範囲を踏まえ、会社として必要最小限の調査を行います。
▼調査のポイント
- 調査対象者は最小限に絞る
- 相談者が特定されないよう質問の仕方を工夫
- 記録は厳重に管理
- 調査事実を不用意に共有しない
- 調査を行う理由を相談者に事前に説明し、同意を得る
「相談者が特定されてしまう」ことで精神的負担が増すケースが多いため、
“特定されない調査方法”を取れるかが実務の重要ポイントです。
4.本人への負担を軽減する解決策も併せて提案
相談者が望まない場合、懲戒や厳罰は避ける代わりに、以下のような対応も考えられます。
▼負担を減らすための解決策の例
- 物理的・時間的な配置転換
- 座席異動
- 業務分担の見直し
- 行為者への指導(相談者の名前を出さずに実施)
- チーム全体へのハラスメント防止研修
- 上司の指示の出し方改善指導
相談者本人を巻き込まず、会社側の管理措置として改善する方法はいくらでもあります。
5.処分希望がなくても、会社には再発防止措置の義務がある
相談者が
- 「処分はしないでほしい」
- 「波風を立てたくない」
と言っていても、会社は以下を実施する必要があります。 - ハラスメントを行ってはならない旨の方針の周知
- 行為者への指導・注意
- 相談窓口体制の整備
- 社内研修の実施
- 必要に応じた組織改善
これは懲戒処分とは別の“管理上の措置”であり、相談者の意思に反するものではありません。
【事例】「事を大きくしたくない」と言う相談者への実務対応例
▼事例:飲食チェーン店 A さんの場合
従業員 A さんが店長から
「皆の前で叱責される」「シフトを勝手に変えられる」
という相談をしてきました。
しかし本人は
「店長に知られるのは嫌」「配置換えも希望していない」「ただ環境を少し変えてほしいだけ」
と強い不安を抱えていました。
▼会社が行った対応
- 本人と丁寧に面談
→ 誰に知られたくないか、許容する対応を明確化 - 本人が特定されない形で調査を実施
→ 他のスタッフへのヒアリングでは「最近、店長の叱り方がきつい」との声も - 店長に対して指導
→
- 「叱責は個別に行う」
- 「シフト変更は必ず事前相談」
等のマネジメント指導を実施(相談者の名前は出さない) - 職場環境改善を実施
→ 定例ミーティングで「ハラスメント禁止・適切な指示の出し方」を周知 - 本人には継続的にフォロー
→ 状況は改善し、本人は安心して勤務を継続
▼結果
相談者の要望を尊重した上で、
- 職場環境が改善
- 他の従業員への好影響
- 店長のマネジメントが改善
という良い結果につながりました。
まとめ
「事を大きくしたくない」という相談者の気持ちに寄り添いつつ、
企業としての義務を適切に果たすことが重要です。
ポイントは次の5つです。
- 相談者の意向を丁寧に聞き取る
- プライバシー保護を徹底
- 調査は必要最小限の範囲で実施
- 相談者の負担が少ない解決策を提案
- 処分希望がなくても再発防止策は必ず行う
職場のハラスメント対応は、
“相談者の安心”と“企業の法令対応”を両立させることが鍵です。
ご相談はお気軽にどうぞ(初回相談無料)
ハラスメント相談対応や調査フローの整備について、
実務に精通した社会保険労務士がサポートいたします。
以下のボタンから、いつでもご相談いただけます。