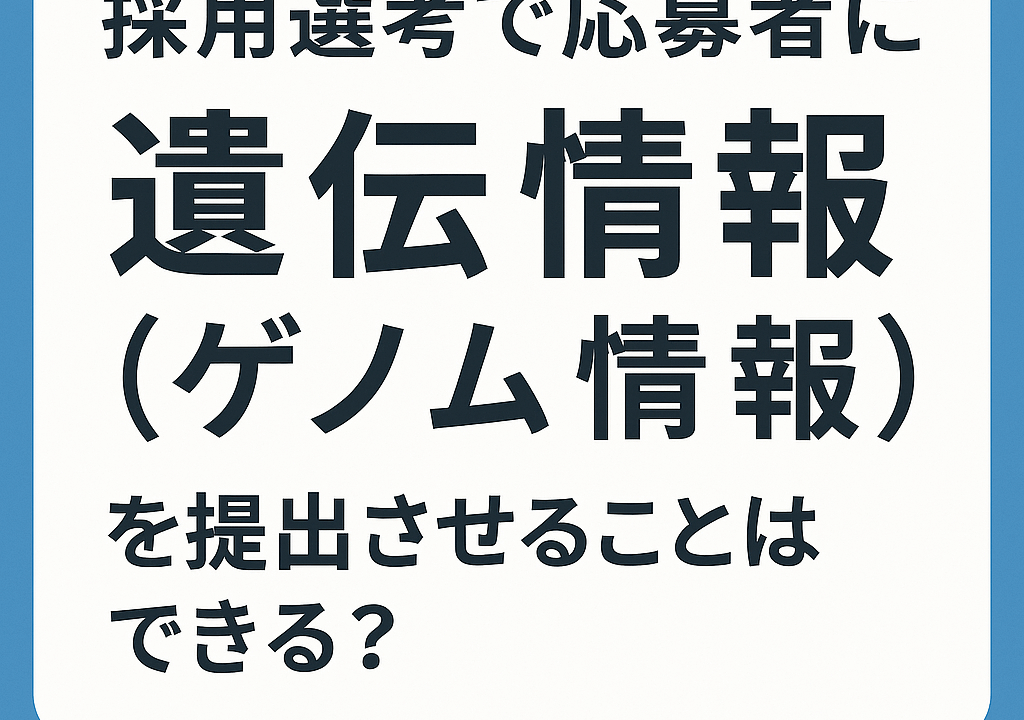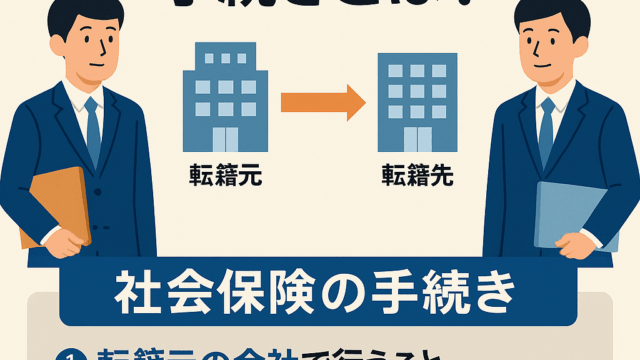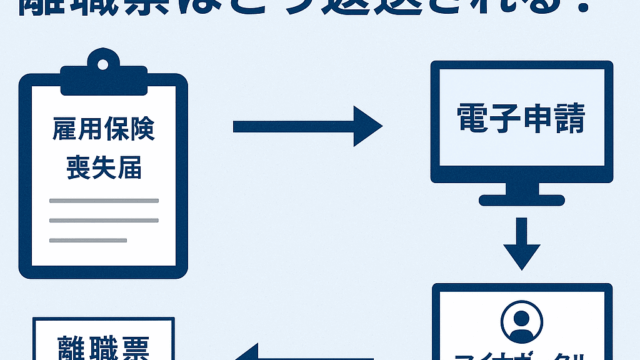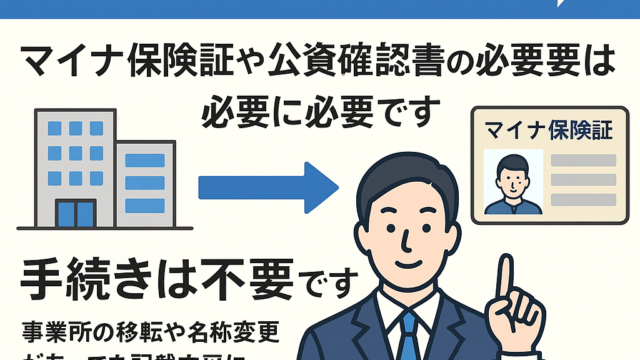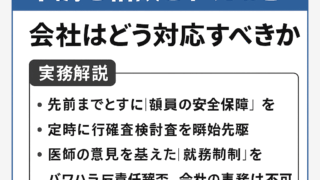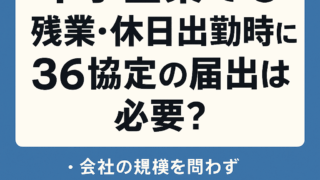採用面接の場で、応募者の健康状態や家族歴などを知りたいと考える企業もあります。
しかし 遺伝情報(ゲノム情報) については、通常の個人情報とは異なり、取り扱いに極めて厳しい規制があります。
この記事では、採用担当者が必ず知っておくべき「遺伝情報の取得禁止」のポイントを分かりやすく解説します。
1.結論:原則として「遺伝情報の提出を求めてはならない」
職業安定法は、求職者の個人情報の収集について
「業務の目的達成に必要な範囲に限る」
ことを義務づけています(第65条)。
遺伝情報(ゲノム情報)は、生まれつきの体質や疾患リスクなど、
本人の努力や責任ではどうにもできない情報 であり、
差別につながるおそれが極めて高いとされています。
そのため、厚生労働省は遺伝情報の取得について、
以下のように明確に制限しています。
✔ 特別な職業上の必要性がある
✔ 目的達成に必要不可欠
✔ その目的を応募者に明示している
これらの条件を満たさない限り、遺伝情報の提出を求めることは認められません。
2.遺伝情報を収集した場合のリスク(企業側)
遺伝情報を採用選考に利用した場合、企業は大きなリスクを負います。
▼法令違反の可能性
- 職業安定法違反(個人情報の不適正収集)
- 厚生労働省からの指導・助言・改善命令の対象
- 改善命令に従わない場合 →
6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
▼社会的リスク
- 「差別的な採用を行っている企業」との社会的批判
- SNSでの炎上
- 求人掲載停止や企業ブランド毀損
近年は求職者の権利意識も高まっているため、
小さな違反でも大きく問題に発展する可能性があります。
3.遺伝情報が「取得してはいけない」理由
厚生労働省は、遺伝情報を次のように位置づけています。
✔ 出身地や本籍地と同じく差別につながる情報
✔ 本人の努力では変えられない情報
✔ 適性・能力とは直接関係がない情報
遺伝情報を採用に使ってしまうと、
- 病気のリスク
- 家系の特性
- 先天的体質
といった要素で不利益な取り扱いをしてしまう危険があるため、
極めて慎重に扱うべきとされています。
4.【事例】実際にあった「遺伝情報に関する不適切な対応」
▼事例:医療関連企業B社の場合(相談例)
医療関係の企業B社では、応募時に健康診断書の提出を求めるなかで、
応募者の既往歴や家族の病気について詳細に記載する欄を設けていました。
そこに、応募者が「遺伝性疾患の家族歴」について記載したところ、
採用担当者がその情報をもとに不採用を決定。
▼問題点
- 業務上の必要性がないにもかかわらず取得していた
- 遺伝情報を採用判断に利用している
- 本人の責任ではない事項を理由に不利益取り扱い
- 職業安定法の趣旨に反する
ハローワークから指導が入り、会社は速やかに書式を変更。
採用担当者は研修を受講することとなりました。
▼企業への教訓
- 取得する個人情報は最小限に
- 採用選考で病歴・家族歴を聞くことも原則NG
- 健康診断書の取り扱いも慎重に行う必要がある
5.企業が採用選考で注意すべきポイント
遺伝情報だけでなく、採用選考で聞いてはいけない事項は多くあります。
▼取得してはいけない情報の例
- 本籍地
- 家族の職業・収入・健康状態
- 住宅状況(持ち家か賃貸か等)
- 宗教・政治信条
- 遺伝情報(ゲノム情報)
これらはすべて「差別につながるおそれ」があるため、
原則として取得・利用してはいけません。
6.まとめ:遺伝情報の取得は原則禁止。企業の法令遵守が必須
採用選考では、
求職者の能力・適性に直接関係する情報のみを取得することが原則
です。
遺伝情報のようなセンシティブな情報は、
企業にとってリスクしかありません。
企業は、
- 個人情報の最小限収集
- 採用担当者の教育
- 書式・選考フローの見直し
を徹底することが重要です。
採用・個人情報の取り扱いに関するご相談は専門家へ(初回相談無料)
ひらおか社会保険労務士事務所では、
- 採用選考のチェック
- 違法リスクのある質問の洗い出し
- 応募書類の見直し
- 個人情報保護規程の整備
- ハラスメント・差別防止教育の実施
など、法令に沿った採用体制づくりをサポートしています。
以下のボタンからお気軽にご相談ください。