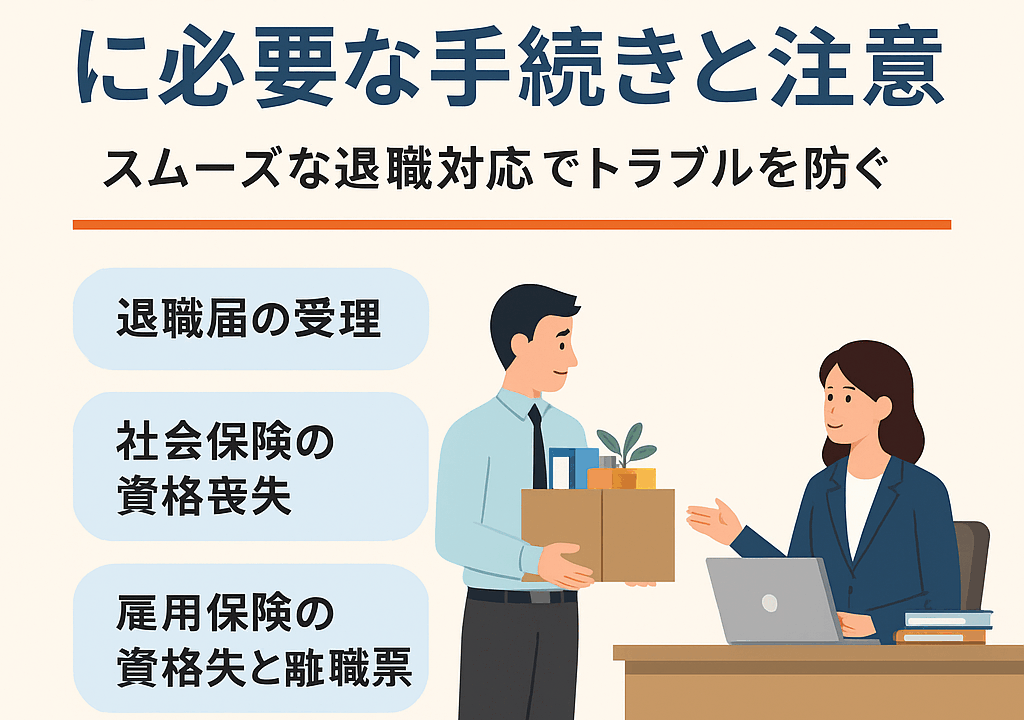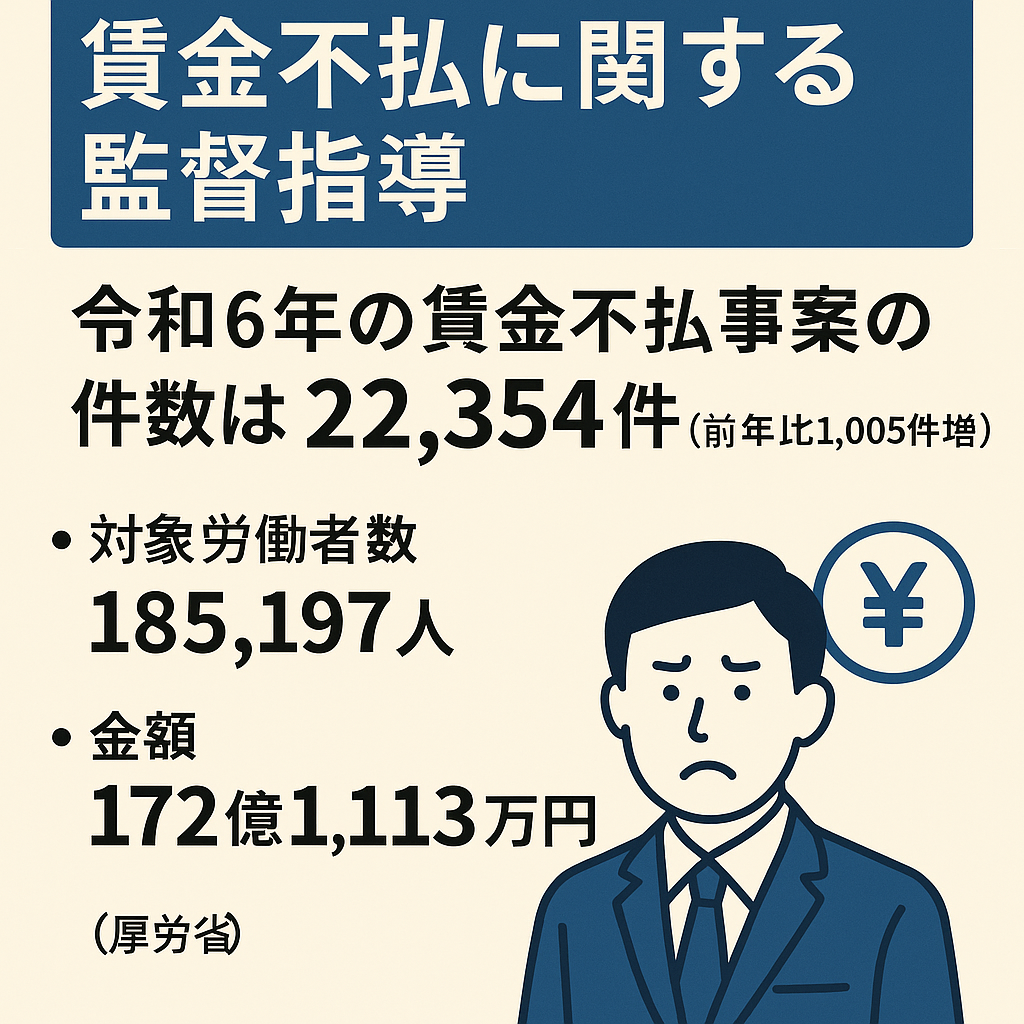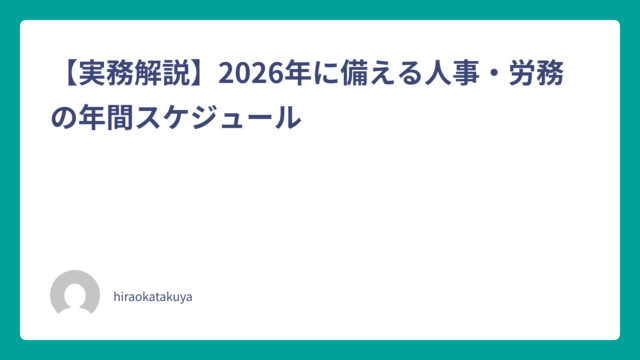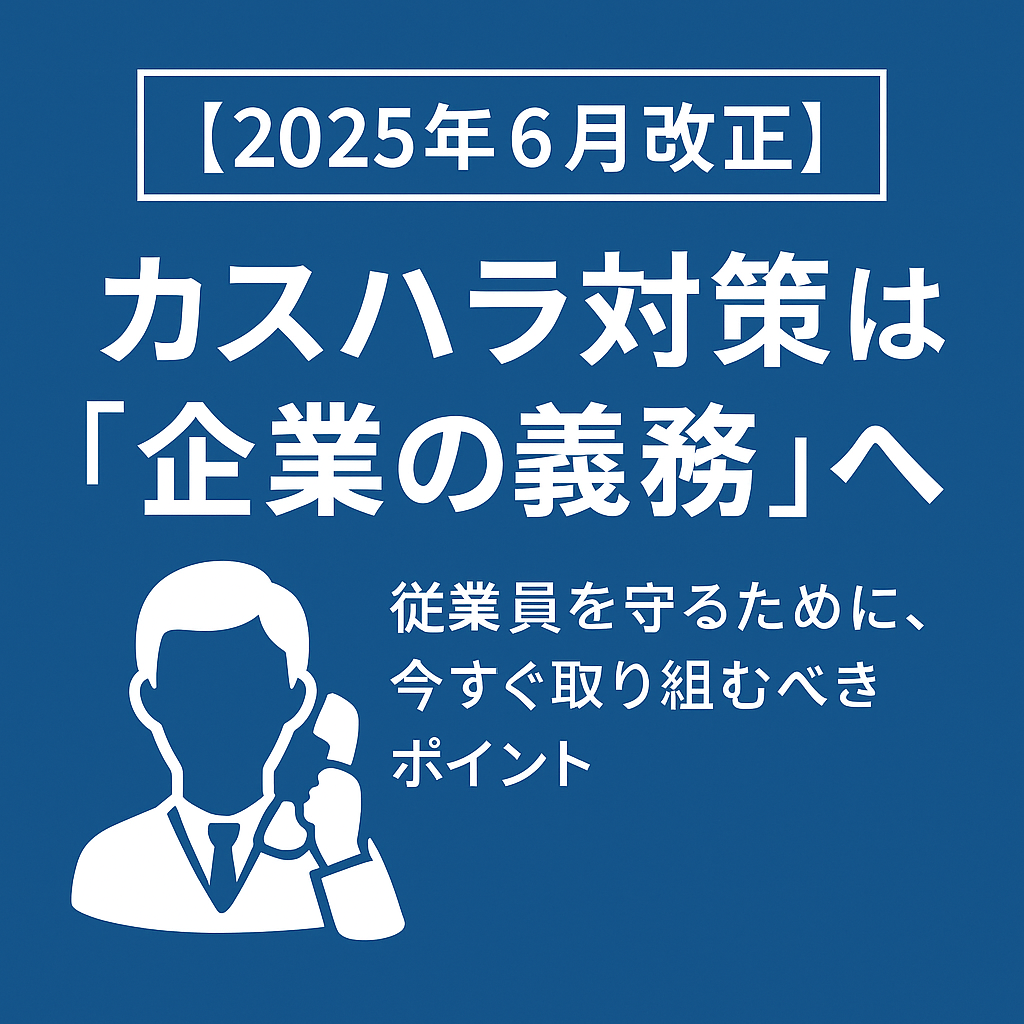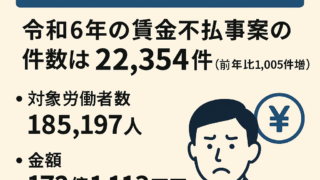~スムーズな退職対応でトラブルを防ぐ~
従業員の退職は、会社にとって避けて通れないイベントです。
しかし、「何をすればいいのか分からない」「書類の準備が間に合わない」など、現場ではバタバタしがち。
今回は、労務担当者が知っておくべき「従業員の退職時に必要な手続き」と「注意点」を、事例付きでわかりやすく解説します。
① 退職届の受理と対応
【ポイント】
退職届の提出は義務ではありませんが、「言った・言わない」のトラブルを防ぐために提出を求めましょう。就業規則に提出期限(例:退職日の30日前)を定めておくのがベストです。
【事例】
AさんがLINEで「辞めます」とだけ伝えてきたが、後日「そんなことは言っていない」と主張。→文書で提出してもらっていれば防げたケース。
② 社会保険の資格喪失と証類の回収
【必要書類】
- 被保険者資格喪失届(退職日の翌日から5日以内に提出)
- 健康保険証や資格確認書、限度額適用認定証などは必ず回収
【注意点】
パソコンや携帯電話などの貸与品が返却されていない場合でも、賃金からの天引きは原則できません。個別合意や労使協定があってもNGです。
③ 雇用保険の資格喪失と離職票の交付
【提出期限】
退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出。
【離職票の交付】
従業員が希望しない限り発行は不要ですが、59歳以上は希望の有無にかかわらず発行義務があります。
【事例】
Bさんが離職票の受け取りを希望せずに退職。その後、失業手当の申請に必要と判明し、「なぜくれなかったのか」とクレームに。→希望の有無を記録しておくことも大切です。
④ 源泉徴収票・退職証明書の交付
- 源泉徴収票は、希望の有無にかかわらず退職日から1か月以内に交付
- 退職証明書は、退職後2年以内なら希望があれば発行義務あり(法令で定めあり)
⑤ 住民税の処理
【時期によって対応が異なります】
- 1~5月退職: 残額を退職金や最終給与から一括徴収(原則)
- 6~12月退職: 普通徴収に切替。希望があれば一括徴収も可能
【事例】
Cさんが6月に退職し、普通徴収への切り替えが行われなかったため、新しい職場で住民税が二重で引かれるトラブルに。
⑥ 有給休暇の扱いと買い上げ
原則として有給休暇の買い上げはできませんが、退職までに取得できない分については「買い上げ可」とされています。
⑦ スムーズな退職のために
- チェックリストで進行管理を
- 手続き漏れがないよう、スケジュールを見える化
- 退職者にとっての不利益を未然に防ぐ配慮も重要
【まとめ】
退職時の対応は、企業の信頼にも関わる重要なプロセスです。
退職手続きの知識をしっかり押さえ、スムーズな対応でトラブルを防ぎましょう。
✅ 初回相談無料|退職手続きのご相談はこちらから