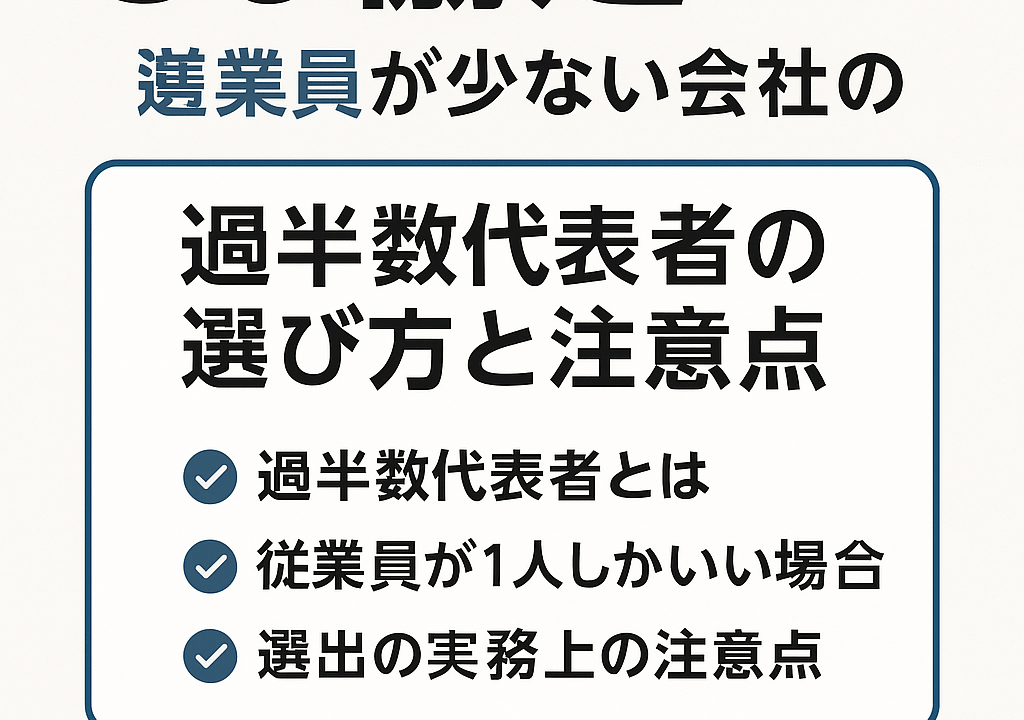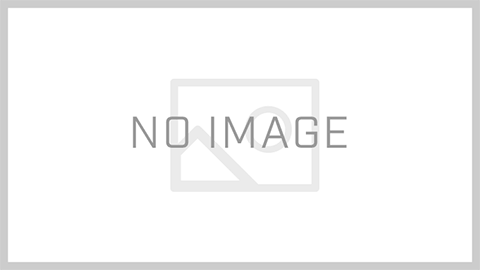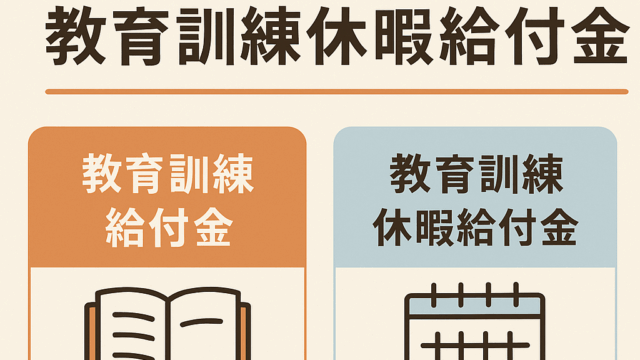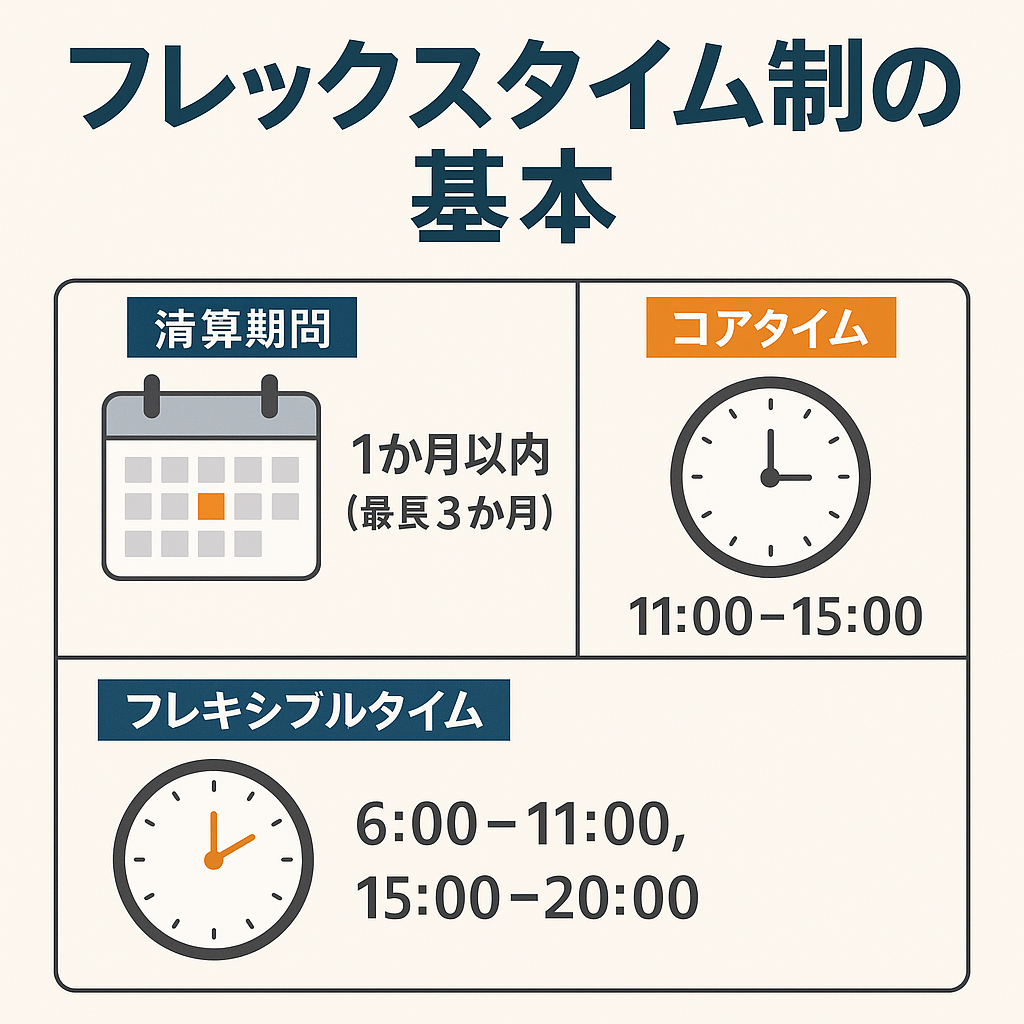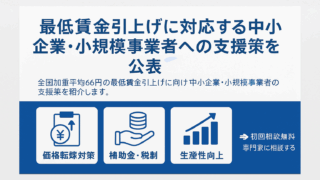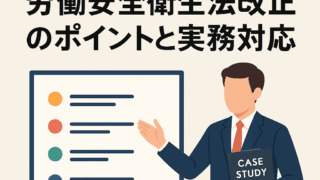労働基準法36条に基づき、時間外労働や休日労働を行わせるには「36協定」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
この協定を締結する際には「労働者の過半数代表者」との合意が必要ですが、従業員が少ない会社では誰を選ぶのか? という相談が非常に多いです。
今回は、少人数事業場での過半数代表者の選出方法や注意点を解説します。
1. 過半数代表者とは?
- 会社と労使協定を結ぶ際、労働者の過半数を代表する者を選出する必要があります。
- 「管理監督者(店長や役員)」は対象外です。現場の労働者から選出する必要があります。
👉 ポイントは 「使用者の意向に左右されない形で選ばれること」 です。
2. 従業員が1人しかいない場合
- 労働者が1人しかいない会社でも36協定は必要です。
- この場合は、唯一の労働者が自ら過半数代表者となり、会社と協定を結ぶ ことが可能です。
3. 従業員が2〜3人の場合
- 労働者が複数いる場合は、労働者の中で選挙や挙手など民主的な手続きにより選出する必要があります。
- 事業主が「この人にして」と指名することはできません。
4. 選出の実務上の注意点
- 選出方法を記録に残す(掲示や投票用紙など)。
- 管理監督者は選べない(店長や経営側に立つ者は不可)。
- 毎回選び直す必要はない(任期を決めて代表を続けてもよい)。
5. 事例紹介
事例①:従業員が1人の飲食店
アルバイト1名を雇用している飲食店では、オーナーが「36協定は不要」と誤解していました。
実際には労働者が1人でも協定は必要であり、そのアルバイト本人が過半数代表者として署名しました。
事例②:従業員3名の介護事業所
介護事業所では、オーナーが特定の従業員に代表を指名しようとしましたが、指名は無効です。
全員に説明のうえ挙手で代表を決定し、その結果を記録に残すことで適正な選出となりました。
まとめ
従業員が少ない会社でも、36協定の届出は必須です。
- 1人しかいない場合 → 労働者本人が代表に
- 複数いる場合 → 民主的な方法で選出
- 管理監督者は不可
- 選出手続きは記録を残すことが大切
この手続きを誤ると、協定が無効となり 違法な時間外労働 となるリスクがあります。
必ず正しい手続きを踏んで36協定を締結しましょう。
👉 関連記事:
✅ 最低人数の会社でも36協定は必要です。ご不明な点は専門家にご相談ください。