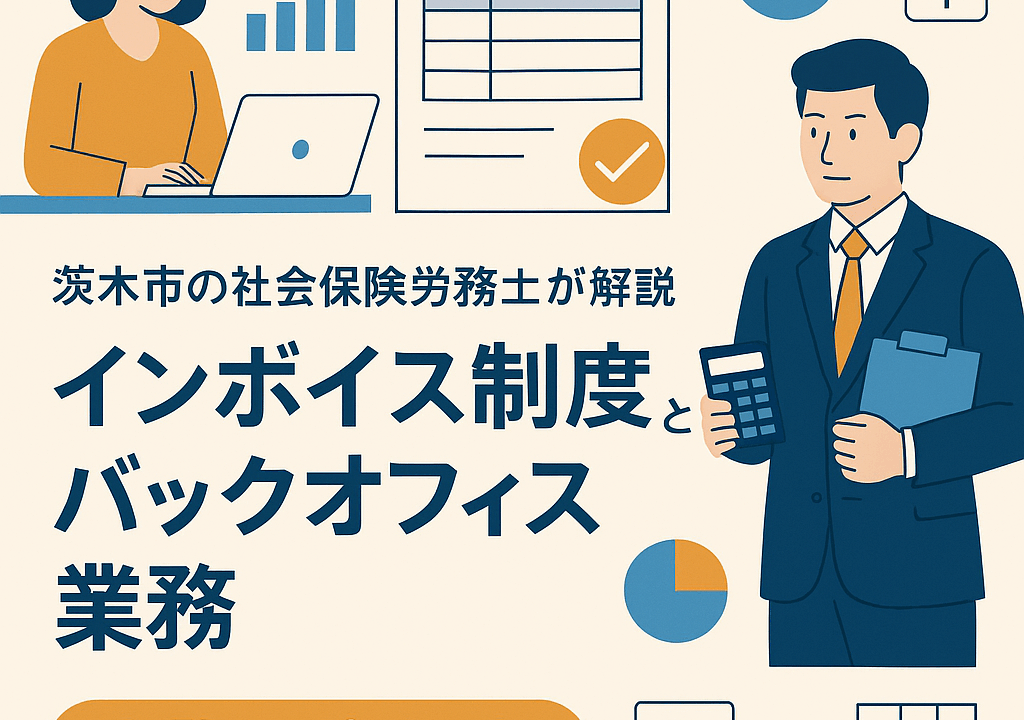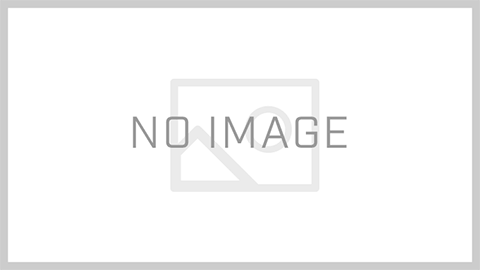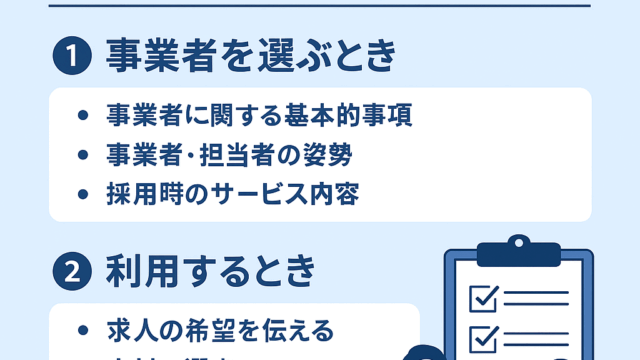2023年10月にスタートした消費税インボイス制度。導入から約2年が経過し、中小企業の対応状況や事務負担について、日本商工会議所(日商)と東京商工会議所が最新の調査結果(令和7年9月)を公表しました。
今回はそのポイントを整理し、茨木市の中小企業でも参考になるよう、実務上の注意点と事例を交えて解説します。
調査結果のポイント
インボイス制度の影響
- 免税事業者から課税事業者への転換(登録)は、
- BtoB企業:78.6%
- BtoC企業:24.6%
- 課税転換を機に価格交渉を行った企業は23.2%で、そのうち76.9%が値上げを実現。
- 一方で、交渉自体を行わなかった企業は76.8%に上り、「取引先から提案がなかった」が主な理由。
- 2割特例(2026年9月末まで)を利用している事業者は68.6%。
- 免税事業者との取引を継続する企業は43.7%で、その理由には「代替先がない」や「地域貢献のため小規模事業者を支援したい」が挙げられました。
- 制度導入により45.8%がコスト増、73.4%が事務負担増を実感。
バックオフィス業務の現状
- 売上高1,000万円以下の事業者の約8割(79.4%)が経理を1人で担当。
- 小規模企業ほど代表者や営業担当者が経理を兼務しており、帳簿作成の頻度も低い。
- 経理システム導入やペーパーレス化は進んでおらず、インボイス対応のツール活用も限定的。
実務での注意点
- 価格交渉を先送りにしないこと
取引先からの提案待ちではなく、自社から交渉を持ち掛けることでコスト転嫁の可能性が広がります。 - 2割特例の終了に備える
2026年9月末で終了予定のため、早めに通常課税の資金繰りをシミュレーションしておく必要があります。 - 経理担当者の負担軽減
小規模事業者は特に、代表者が経理を兼務するケースが多く、インボイス対応による事務量増加でミスのリスクも高まります。システム導入や社労士・税理士へのアウトソーシングも検討すべきです。
事例で学ぶ
事例①:価格交渉で利益を守ったケース
茨木市の製造業A社は、インボイス登録を機に主要取引先と交渉。コスト上昇を理由に単価を3%引き上げることに成功しました。結果的に利益を確保し、従業員への賞与維持につながりました。
事例②:対応が遅れた小規模事業者
一方、BtoC中心のサービス業B社は交渉を行わず、消費税分を内部で吸収。結果、資金繰りが悪化し、新規設備投資が先送りになってしまいました。
👉 ポイント:交渉を避けることが必ずしも「安心」ではなく、将来的な経営リスクにつながります。
まとめ
インボイス制度は「事務負担の増加」と「コスト増」を多くの中小企業に与えています。
- 価格交渉は早めに動く
- 2割特例終了後の準備を進める
- 経理業務はアウトソーシングやツール活用で効率化
これらの対応が、今後の経営安定につながります。
✅ 茨木市で社会保険労務士をお探しの方へ
当事務所では、インボイス制度対応を含むバックオフィス業務の効率化や労務管理のご相談を承っております。