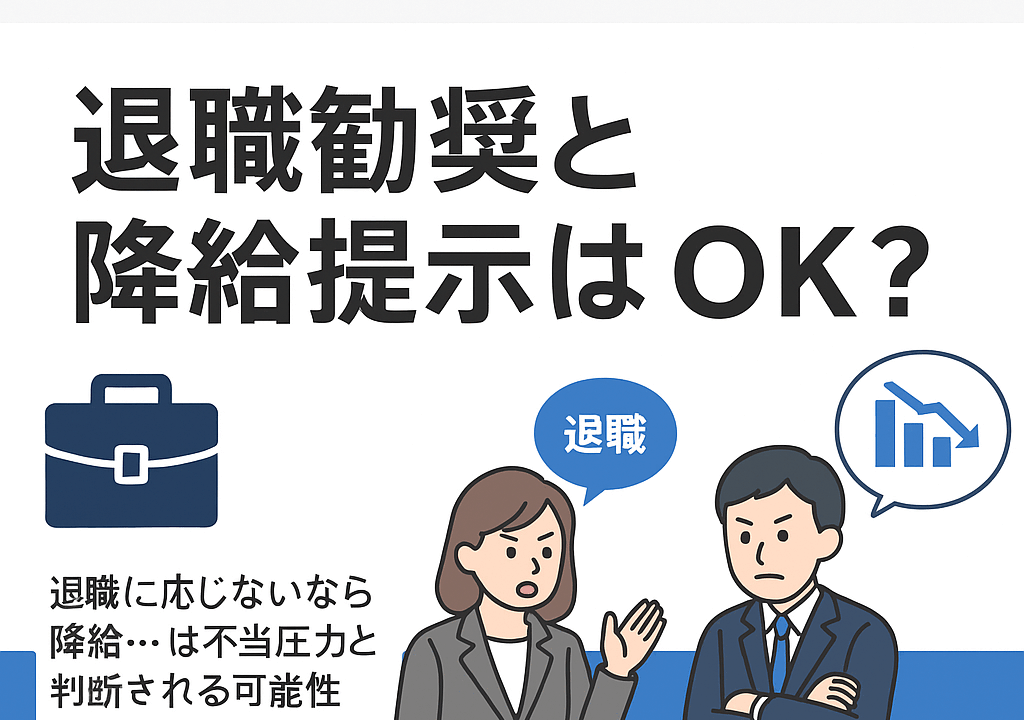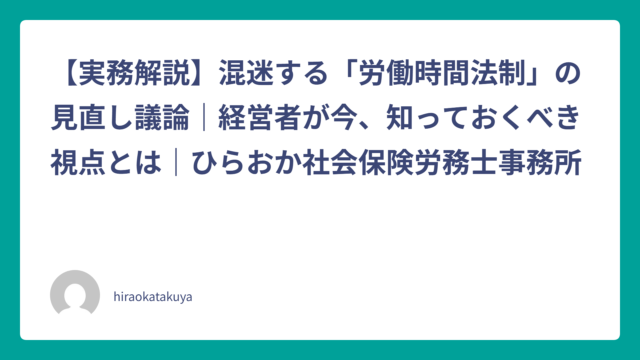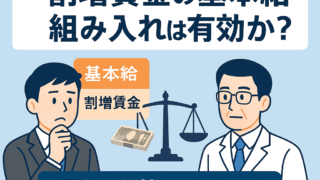こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
企業が人員整理や人材の入れ替えを行う場面では、従業員に対して「退職勧奨(たいしょくかんしょう)」を行うケースがあります。
しかし、その際の対応を誤ると、不当な圧力とみなされ、トラブルに発展する可能性が高いため、慎重な取り扱いが必要です。
今回は、退職勧奨の場面で「退職しないのであれば降給する」と提示することが可能かどうかについて解説します。
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、会社が従業員に対して「退職をお願いする」行為をいいます。
あくまでも 任意の退職意思 を促す行為であり、従業員が自由な意思で退職を選択できることが前提です。
「退職しないなら降給する」のリスク
退職勧奨の場面で、
「退職しないのであれば給料を下げます」
と伝えることは、次のようなリスクがあります。
- 自由意思が否定される可能性
- 退職しない場合に不利益(降給)があると伝えられれば、従業員の同意は「自由な意思」とはいえなくなります。
- その結果、合意退職が無効とされるリスクがあります。
- 不当な心理的圧力と評価される可能性
- 降給の提示は「退職しなければ不利益がある」という強い圧力を与えます。
- これは従業員の自由な意思形成を妨げる行為として、不法行為に該当する可能性があります。
- 不法行為責任(損害賠償)のリスク
- 民法709条(不法行為)に基づき、慰謝料等を請求されるおそれがあります。
実務での事例
事例:A社(製造業)のケース
業績悪化により人員削減が必要となったA社は、50代の従業員Bさんに退職勧奨を実施しました。
しかしBさんは「退職する意思はない」と明確に回答。
そこで人事担当者が「退職しないなら給与を下げざるを得ない」と伝えた結果、Bさんは強い不信感を抱きました。
最終的に退職には至らず、Bさんは「不当な圧力を受けた」として労働組合を通じて会社を提訴。
裁判所は「降給を示唆することは自由意思を奪う不当な心理的圧力にあたる」と判断し、会社に慰謝料の支払いを命じました。
実務上の対応ポイント
- 退職勧奨は「誠実な説明」と「本人の納得」が大前提
- 退職しないことに対して「不利益処分(降給・配置転換など)」を直接結びつけることは避ける
- 退職勧奨を行う際は、記録(経緯・発言内容)を残す
- 一定期間を空けて複数回に分けて説明し、圧力とならないよう配慮する
まとめ
退職勧奨の場面で「退職しないなら降給する」と伝えることは、
従業員の自由意思を侵害し、不法行為としてトラブルにつながる可能性が高いため、極めて危険です。
退職勧奨はあくまで「任意」であり、従業員が納得のうえで退職することが原則です。
人員整理の必要がある場合でも、配置転換や業務改善指導など、正当な人事措置を先行させることが望まれます。
根拠法令
- 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
👉 退職勧奨の進め方や従業員対応でお悩みの企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。