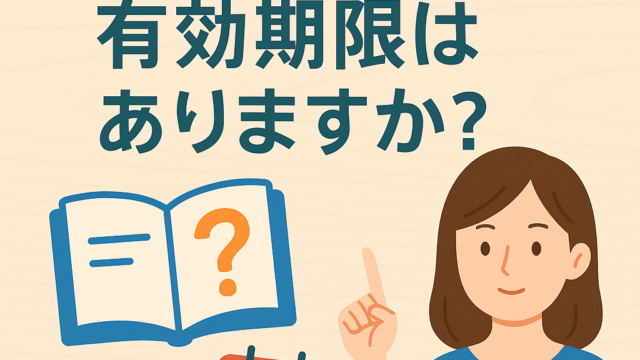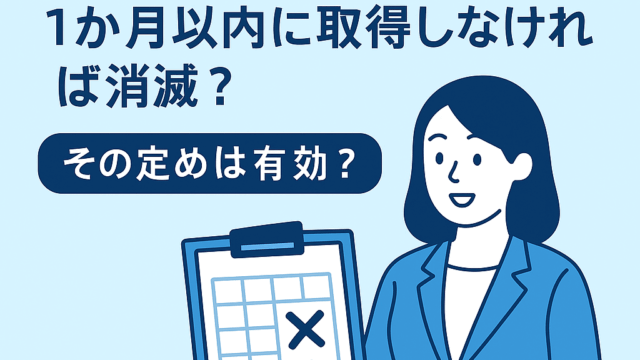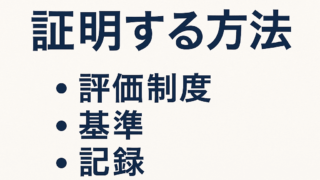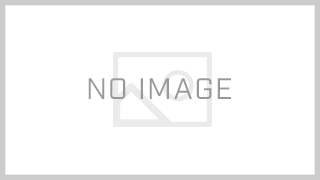こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
人事評価や労務管理を行う中で、
「能力不足の従業員に対して、賃金を下げることはできるのか?」
というご相談をいただくことがあります。
今回は、賃金減額が法的に認められるかどうかを整理し、実務での対応方法を解説します。
賃金減額の可否を分けるポイント
1. 就業規則に定めがある場合
- 就業規則に「賃金減額の基準や方法」が明確に記載されている場合、合理的な評価制度に基づいた運用であれば、賃金減額が認められる可能性があります。
- ただし、次のような場合には無効と判断されるリスクがあります。
- 減額幅が大きすぎる場合(例:30%以上など極端な減額)
- 評価が恣意的で、客観性に欠ける場合
2. 就業規則に定めがない場合
- 原則として、従業員本人との合意が必要です。
- 合意があっても「自由な意思に基づくもの」と裁判所に認められなければ無効とされるリスクがあります。
- 実務上、会社側の一方的な力関係の中で結ばれた「形式的な合意」は覆されることが多いため注意が必要です。
実務での対応事例
事例:販売員Cさんのケース
小売業のCさんは、ミスが多く接客態度も改善されず、売上成績も低迷していました。
会社は次のステップを踏みました。
- 半年間の接客研修を実施し、改善指導を繰り返し記録化。
- 就業規則に基づき、人事評価制度を用いて「成績不良により給与テーブルを1等級下げる」処置を実施。
- 減額幅は5%にとどめ、不利益が過大とならないよう配慮。
→ 結果として従業員との合意も得られ、労務トラブルを避けながら制度運用ができました。
一方で、就業規則に明確な根拠がないまま賃金を下げてしまった事例では、労働者から訴えを受け、裁判所で減額が無効と判断されたケースも存在します。
実務対応のポイント
- いきなり賃金減額ではなく、教育・指導・配置転換など解雇回避の努力を優先する。
- 就業規則や賃金規程に、明確で合理的な定めを設ける。
- 賃金減額幅は、従業員にとって「生活に著しい不利益」とならない範囲に抑える。
- 合意を得る場合には「自由意思で署名した」ことが明らかになる文書化が重要。
まとめ
- 就業規則に合理的な定めがあれば、賃金減額が認められる可能性はある。
- 定めがなければ、従業員との自由な合意が必須。
- 能力不足対応の第一歩は「教育・改善指導」であり、減額は最終手段。
根拠法令
- 労働契約法 第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
- 労働契約法 第10条
👉 能力不足社員への対応や賃金制度の整備にお悩みの企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。