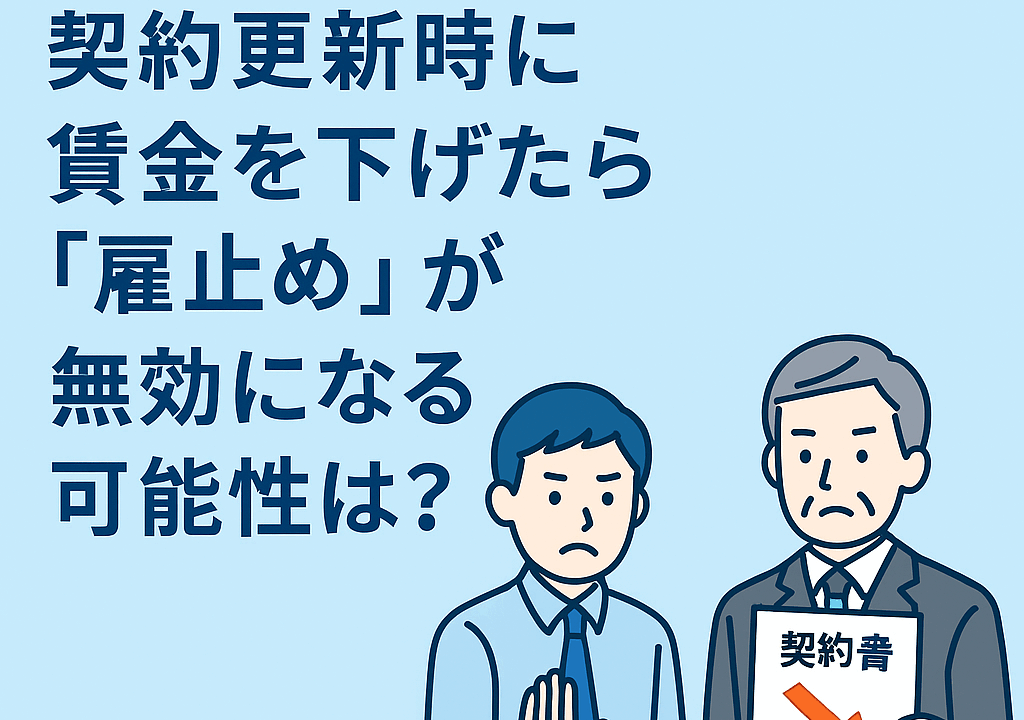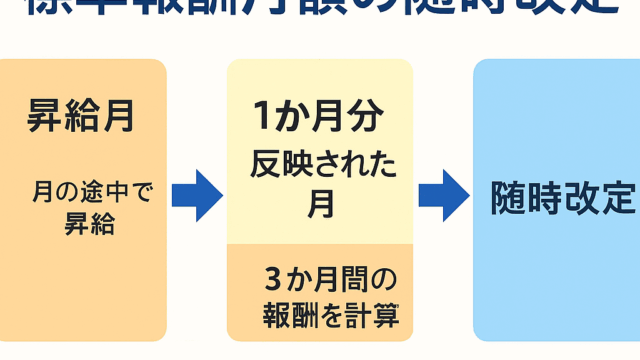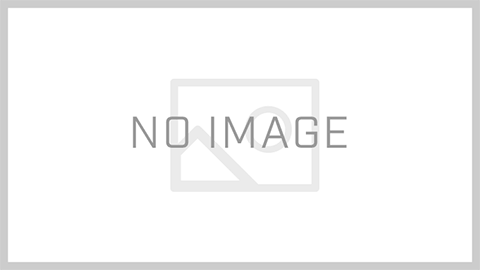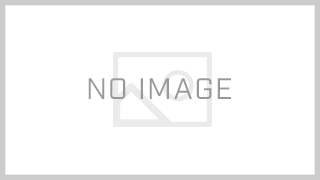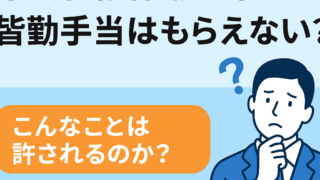有期労働契約の更新の場面で、会社が賃金額を引き下げたことに従業員が反発し、契約更新ができなかった――。
このようなケースでは、雇止め(契約更新の拒絶)が無効とされる可能性があります。
雇止めが無効となるケース
労働契約法第19条では、以下の場合に「雇止め法理」が適用されると定めています。
- 有期労働契約が反復更新され、実質的に無期契約と同視できる場合
- 契約更新への従業員の期待が合理的である場合
このような場合に、会社が更新を拒絶するためには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
実務での事例
事例:賃金引下げを理由とした契約更新拒否
飲食業のA社では、アルバイト従業員と1年更新の契約を5年以上繰り返していました。
次回更新時に「業績不振」を理由に時給を100円下げると提示したところ、従業員は同意せず、契約は更新されませんでした。
従業員が「雇止めは無効」と訴えた結果、裁判所は以下の点を考慮しました。
- 5年以上更新を繰り返し、無期契約と同視できる状態だった
- 従業員に「次回も更新されるだろう」という合理的期待があった
- 賃金引下げについて、会社が合理的な説明を十分にしていなかった
結果として、雇止めは無効と判断され、従業員は従前の労働条件(時給引下げ前の水準)で契約更新が認められました。
実務への影響と注意点
- 有期契約従業員に対して 一方的な賃金引下げを提示することはリスクが高い
- 契約を繰り返している従業員ほど、「更新への期待権」が強く認められる
- 賃金や労働条件を変更する場合は、合理的な理由と丁寧な説明が不可欠
まとめ
契約更新時の労働条件変更(特に賃金引下げ)は、慎重に対応する必要があります。
不当な雇止めと判断されれば、会社は大きなリスクを負うことになります。
労働契約の更新や条件変更をご検討の際には、ぜひ専門家にご相談ください。