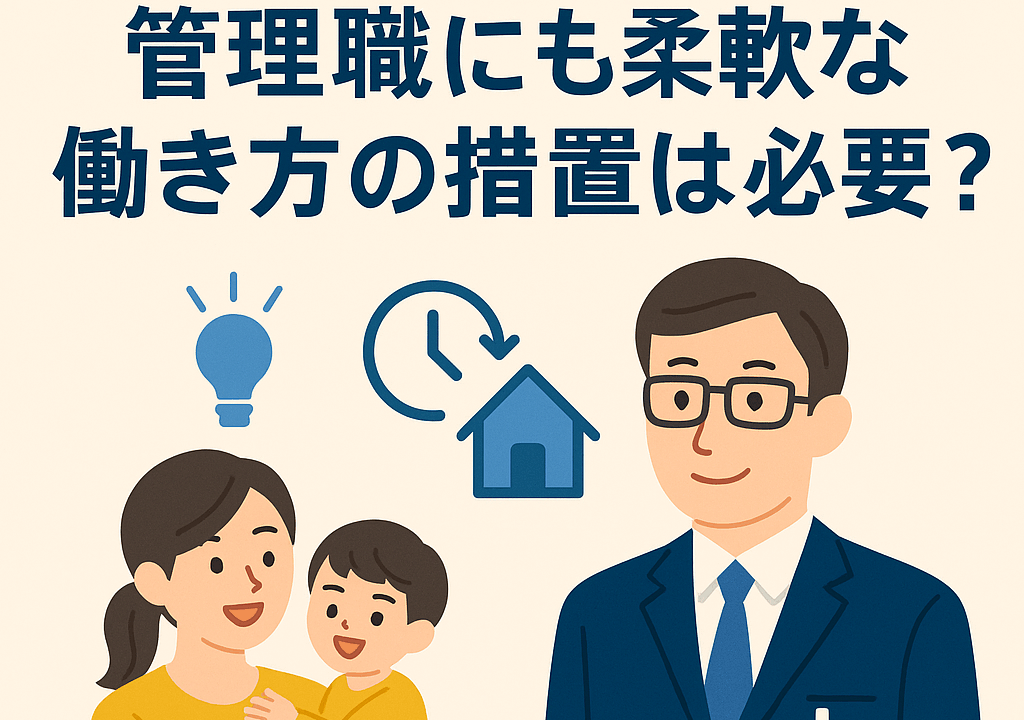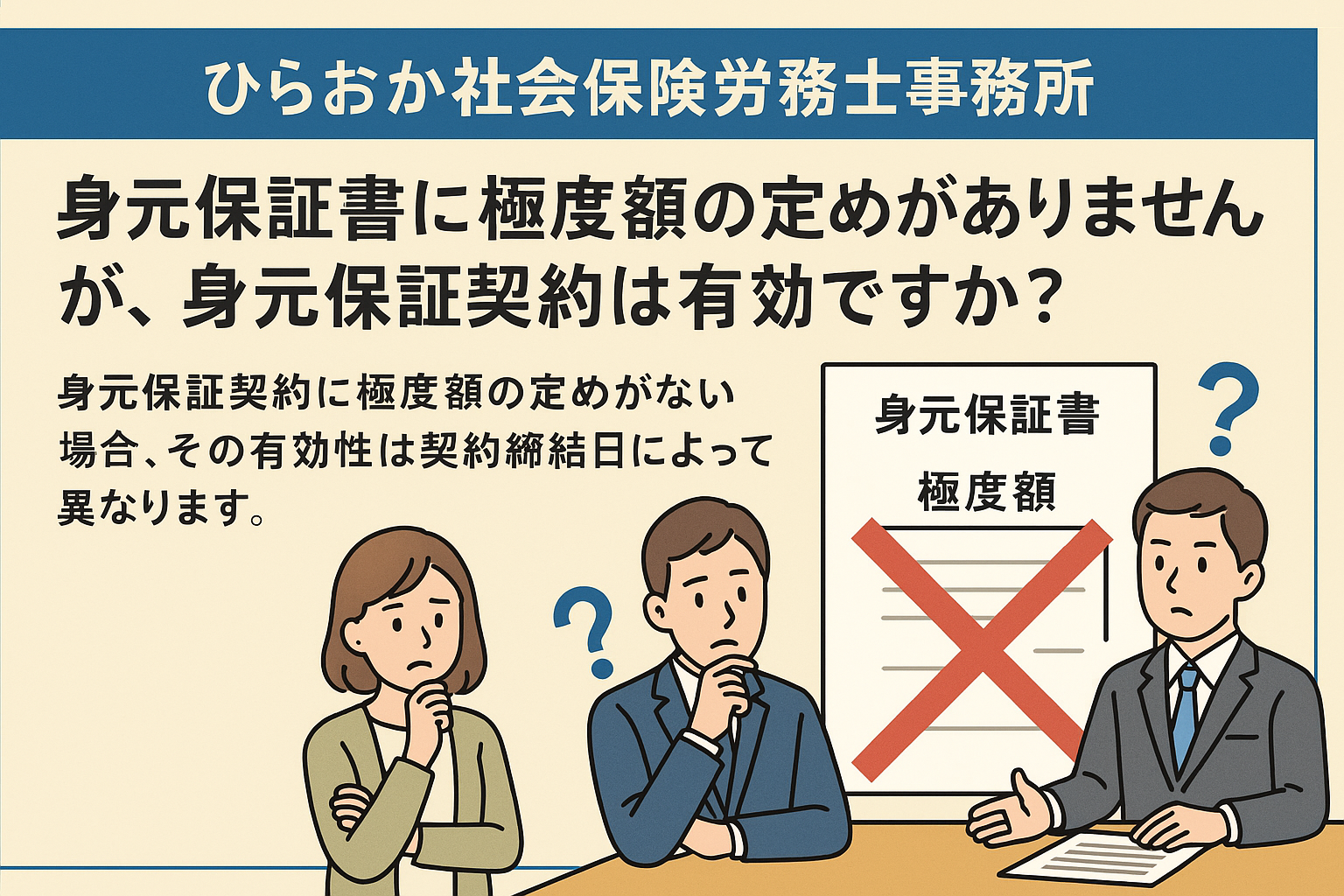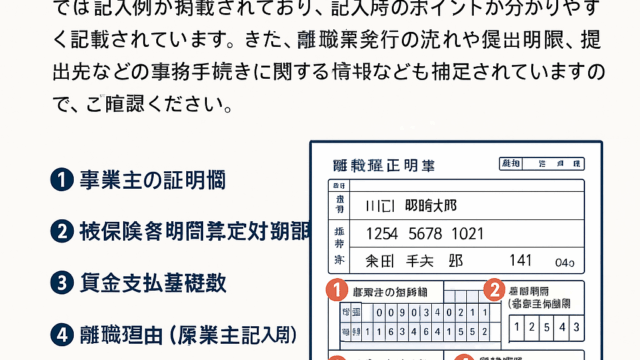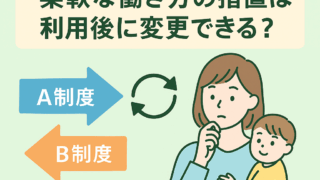こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
今回は、令和6年改正育児・介護休業法における「柔軟な働き方を実現するための措置」が、労基法41条2号に規定される管理監督者についても必要かどうかを解説します。
管理監督者も対象となる
改正法では、管理監督者であっても「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象です。
そのため事業主は、管理監督者に対しても、他の従業員と同様に以下の5つのうち2つ以上の措置を講じる必要があります。
選択肢となる5つの措置
- 始業時刻等の変更
- 在宅勤務等の措置
- 養育両立支援休暇
- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
- 所定労働時間の短縮
対象期間は、子どもが3歳以降、小学校就学前までの養育期間です。
注意点:管理監督者の労基法上の扱い
労基法第41条第2号に規定される「管理監督者」は、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となるため、始業・終業時刻について広い裁量が認められています。
しかし、
- 「裁量がある=すでに柔軟な働き方を認めている」とは解されない
- 改正法が求める5つの措置の中から、2つ以上を制度として設ける必要がある
点に留意が必要です。
さらに、いわゆる「管理職」と呼ばれていても、実態として経営者と一体的な立場にない場合は、労基法上の管理監督者に該当しません。
その場合、所定労働時間の短縮などの措置を申し出られた際には、対応義務が発生します。
【事例】管理職からの短時間勤務の申出
ある企業で、課長職の社員(名目上は管理職)が、子どもが4歳になったタイミングで「所定労働時間の短縮」を希望しました。
会社としては「管理職だから対象外では?」と考えましたが、実態を確認すると、
- 勤務時間の裁量は限定的
- 労働条件の決定権も持っていない
つまり労基法上の「管理監督者」には該当しませんでした。
結果として、会社は制度を適用し、1日6時間勤務への短縮を認めました。これにより、当該社員は退職せずに育児と仕事を両立でき、企業としても経験豊富な人材の流出を防ぐことができました。
実務でのポイント
- 「管理監督者だから対象外」とはならない
→ 制度設計時には管理監督者も対象に含める必要があります。 - 「名ばかり管理職」の確認が重要
→ 実態として管理監督者に該当しない場合は、柔軟措置を講じる義務があります。 - 2つ以上の措置を必ず整備する
→ 就業規則や育児介護休業規程に明記しておくと安心です。
まとめ
- 管理監督者も「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象
- 5つの選択肢から2つ以上を整備する必要がある
- 名称にかかわらず、労基法上の管理監督者に該当しない場合は制度の適用が必須
制度整備は、育児中の従業員の離職防止につながり、企業の持続的な成長にも直結します。
✅ 初回相談は無料です
就業規則や育児介護休業規程の改正対応について、お悩みの際はぜひご相談ください。