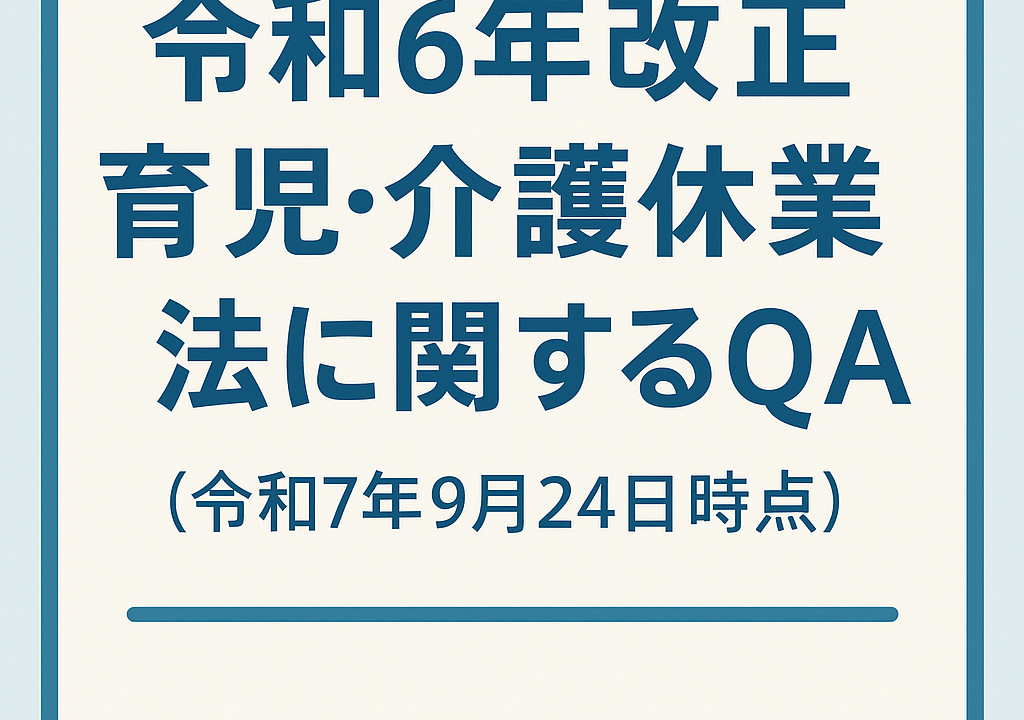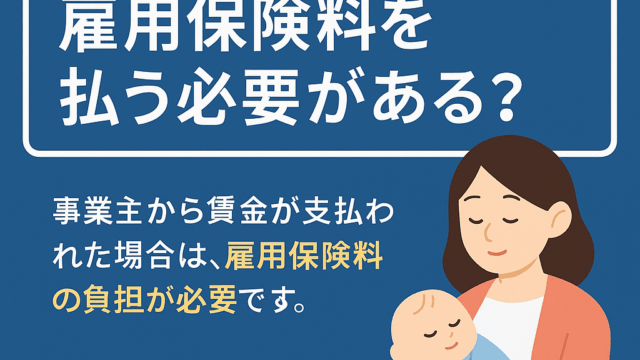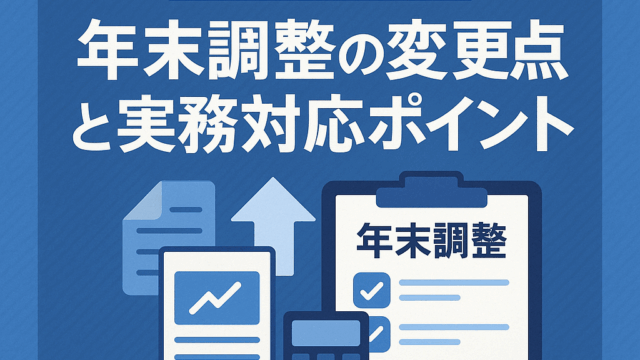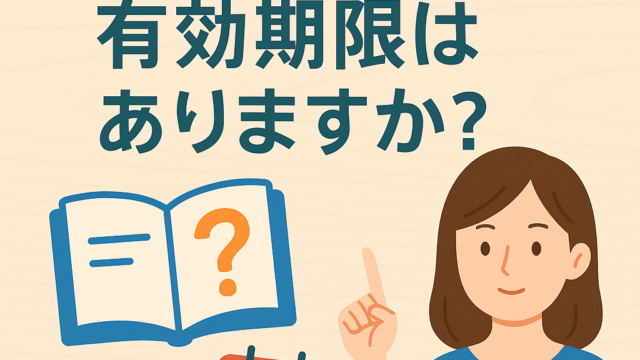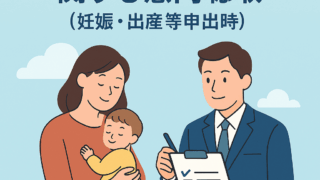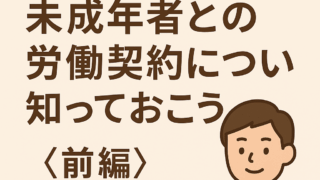こんにちは、ひらおか社会保険労務士事務所です。
2024年(令和6年)から順次施行されている「育児・介護休業法の改正」。2025年9月24日時点の厚生労働省Q&Aが公表され、企業が対応すべきポイントが整理されています。今回は、実務で押さえておきたい重要な点をQ&A形式でご紹介します。
改正の主な内容と施行スケジュール
今回の改正は「男女ともに仕事と育児・介護を両立できる社会」を目指すもので、次のようなポイントが盛り込まれています
- 柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月施行)
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(2025年4月施行)
- 育児テレワーク導入の努力義務(2025年4月施行)
- 子の看護休暇の取得事由・対象拡大(2025年4月施行)
- 個別の意向聴取・配慮の義務化(2025年10月施行)
- 育児休業取得状況の公表義務(対象300人超に拡大)
- 介護離職防止のための雇用環境整備の義務化
よくある質問と実務ポイント
Q1. 3歳以上小学校就学前の子を持つ従業員に対し、どのような柔軟な働き方を用意する必要がありますか?
A1. 事業主は、以下から2つ以上の制度を用意する必要があります。
- 始業・終業時刻の変更(フレックス・時差出勤)
- テレワーク(月10日以上利用可能)
- 短時間勤務制度(所定時間を6時間程度に短縮)
- 養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位で取得可)
- 保育施設の設置・ベビーシッター費用補助など
Q2. 従業員が一度選んだ制度を途中で変更したいと申し出た場合、認めなければなりませんか?
A2. 法律上は義務ではありません。ただし、家庭や仕事の状況が変化することも多いため、定期的な面談で意向を確認し、柔軟に対応することが望ましいとされています
Q3. 正社員とパートで異なる措置を設定しても大丈夫ですか?
A3. 異なる措置を設定することは可能ですが、待遇差が「不合理」とならないよう注意が必要です。不合理な差とならないよう、職務内容・配置の範囲・その他事情を考慮し、従業員に合理的な説明ができるよう準備しておきましょう。
【事例】小規模クリニックでの対応例
大阪市内の小規模クリニックでは、看護師から「子どもが4歳になったので、フルタイム勤務に戻りたいが、保育園の送り迎えもあり不安」と相談がありました。
院長は法改正を踏まえて、
- 「時差出勤(8:30~16:30勤務)」
- 「養育両立支援休暇(保育園行事や急な対応に利用可)」
を制度として整備。看護師は柔軟に働きながらフルタイム復帰を果たしました。
実務上のアドバイス
- 就業規則の見直し:新たな制度を規程化しておくことが重要。
- 従業員との面談記録:変更希望や意向聴取の内容を記録し、後日のトラブル防止につなげる。
- パート・有期雇用者への説明:合理的理由のある取扱いであっても、説明責任がある点に注意。
まとめ
令和6年改正の育児・介護休業法は、制度を「作る」だけでなく、従業員一人ひとりの状況に合わせて「活用しやすい形に整える」ことが求められています。企業にとっては制度整備の負担も増えますが、人材定着や採用力強化につながる投資でもあります。
今のうちに就業規則・社内制度を見直し、従業員との丁寧な対話を進めていきましょう。
📌 根拠法令・参考情報
厚生労働省『育児・介護休業法について』
👉 公式ページはこちら
➡️ 初回相談は無料です。制度整備・就業規則改定のご相談はお気軽にどうぞ!